|
この記事でわかること ・マンション売却時にかかる税金の種類と全体像 |
マンションの売却を考え始めたとき、「結局、税金はいくらかかるんだろう?」と不安に感じる方は多いでしょう。
特に、税金は専門用語が多く、複雑に思えがちですが、仕組みを理解し、正しい知識を持っておけば、余計な税金を払うことなく賢く売却を進められます。
この記事では、マンション売却にかかる税金の種類から、ご自身のケースでの具体的な計算方法、そして手元に残るお金を増やすための税金対策まで、徹底的に解説します。
税金に関する不安を解消し、安心して次のステップに進むために、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
【種類別】マンション売却でかかる税金一覧と基礎知識

マンションを売却した後、一体どんな税金がかかるのか気になりますよね。
マンション売却にかかる税金は、大きく分けて「必ず発生する税金」と、売却で利益が出た場合に課される「譲渡所得税」の2種類があります。
具体的な税金の種類とその特徴を見ていきましょう。
| 分類 | 税金・費用の種類 | 概要 |
|---|---|---|
| 必ず発生する税金 | 印紙税 | 売買契約書などの書類に貼る税金。売買金額で税額が変わる。 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消など登記変更の際にかかる税金。 | |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬。(※税金ではありません) | |
| 利益が出た場合に課される税金 | 譲渡所得税 | マンション売却で得た利益(譲渡所得)に課される税金。(所得税・住民税・復興特別所得税の総称) |
| 消費税 | 事業用マンション売却の場合に建物部分にかかる税金。 |
印紙税|契約時にかかる税金
印紙税とは、不動産の売買契約書のような「課税文書」に課される国税です。
売買契約書に収入印紙を貼り、消印をすることで納税したとみなされます。
印紙税の金額は、契約書に記載される売買金額によって異なります。
【不動産売買契約書にかかる印紙税額】
| 売買契約書に記載される金額 | 印紙税額(軽減税率) |
|---|---|
| 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
| 10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 |
※上記の税額は、軽減税率が適用されたものです(2027年3月31日まで適用)。
※記載金額が1万円未満の場合は非課税です。記載金額のないもの(契約金額の記載がない場合)は一律200円です。
出典:「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」-国税庁を参考に作成(2025年7月時点)
|
【補足】電子契約の場合 近年普及している電子契約では、紙の契約書を作成しないため、印紙税は課税されません。 印紙税の節約にもつながるため、電子契約の利用が可能な不動産会社を選ぶのも一つの方法です。 |
登録免許税|抵当権抹消でかかる税金
マンションを売却する際には、不動産の名義を買主へ変更する「所有権移転登記」など、さまざまな登記手続きが必要になります。
この登記を行う際に国に納めるのが「登録免許税」です。
売主と買主、双方に支払い義務が発生する登録免許税ですが、売主が主に負担するのは「抵当権抹消登記」にかかる税金です。
「抵当権」とは、マンションを購入する際に組んだ住宅ローンに対し、万が一返済が滞った場合に銀行がマンションを担保として貸付金を回収する権利のことです。
このローンを完済した際に、登記簿から抵当権の記載を消す手続きが「抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1つにつき1,000円と定められています。
マンションの場合は、建物と土地がそれぞれ独立した不動産として扱われるため、合計で2,000円かかるのが一般的です。
抵当権抹消登記は司法書士への依頼が一般的
抵当権抹消登記の手続きは、専門的な知識と多くの書類を要するため、一般の方がご自身で行うには複雑に感じられるかもしれません。
そのため、多くの場合、司法書士に手続きの代行を依頼します。
司法書士にこの業務を依頼する際は、法務局に納める登録免許税とは別に、専門家への報酬が発生します。
この報酬額は依頼する司法書士によって異なりますが、おおよそ1.5万円から2万円程度が相場とされています。
仲介手数料|売却活動の対価としてかかる費用
マンション売却の際、個人で買主を探し、契約交渉や引き渡し手続きまですべて行うのは非常に難しいものです。
そのため、多くの方が不動産会社に売却活動の仲介を依頼します。
この不動産会社に支払う報酬が「仲介手数料」です。
これは税金ではありませんが、売却にかかる費用の中でも特に大きな割合を占めるため、事前に把握しておくことが大切です。
仲介手数料は不動産会社ごとに異なりますが、宅地建物取引業法で上限額が定められています。
この上限額は、売買金額に応じて以下のように計算されます。
| 売買金額(税抜) | 仲介手数料の上限額(税抜) |
|---|---|
| 400万円を超える部分 | (売買金額×3%+6万円) |
| 200万円を超え400万円以下 | (売買金額×4%+2万円) |
| 200万円以下 | (売買金額×5%) |
※上記は法律で定められた上限額であり、これを超える手数料を請求されることはありません。
※実際に支払う仲介手数料には、別途消費税が加算されます。
また、仲介手数料は、一般的に売買契約が成立した際に半額、引き渡しが完了した際に残りの半額を支払うケースが多いです。
契約前に不動産会社からしっかりと説明を受け、納得したうえで依頼しましょう。
譲渡所得税|利益が出た場合にかかる税金
マンションを売却して利益(売却益)が出た場合に課されるのが譲渡所得税です。
この税金は、所得税、住民税、そして復興特別所得税の3つを合わせた総称です。
譲渡所得税は、給与所得など他の所得とは合算されない「分離課税」という方式がとられます。
これは、不動産の売却益が多額になる場合に、急激な税負担の増加を避けるためです。
譲渡所得税を計算するには、まず「譲渡所得」の金額を算出する必要があります。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得とは、マンションを売却して得た利益のことです。以下の計算式で求められます。
この計算で譲渡所得がマイナスになった場合、譲渡所得税は課税されません。
取得費における減価償却
譲渡所得の計算で特に重要で複雑なのが「取得費」の算出です。
取得費は購入額だけでなく、購入時の仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、リフォーム費用なども含みます。
また、建物は時間の経過とともに価値が減少するという考え方(減価償却)が適用されます。
この減少分が「減価償却費相当額」として取得費から差し引かれます(土地には減価償却はありません)。
【マンション(マイホーム)の構造別償却率】
| 構造 | 非事業用(マイホームなど)の償却率 |
|---|---|
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
| 木造 | 0.031 |
| 木造モルタル | 0.034 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 0.036 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 0.025 |
| 鉄骨造(4mm超) | 0.020 |
出典:「減価償却費」の計算について-国税庁 を参考に作成(2025年7月時点)。
取得費が不明な場合
相続で引き継いだ古いマンションなどで、購入時の契約書が見つからず取得費がわからないケースもあります。
その場合、「概算取得費」として譲渡価格の5%を取得費とすることができます。
しかし、概算取得費を用いると、譲渡所得が大幅に大きくなり税金が高くなる可能性が高いため注意が必要です。
古い書類を探したり、不動産会社や税理士に相談したりして、正確な取得費を把握するための対処法を検討することをおすすめします。
譲渡所得税の税率
不動産を売却して利益が出た際の譲渡所得にかかる税率は、マンションの所有期間によって変わります。
具体的には、所有期間が5年以下か5年超かで、適用される税率が大きく異なります。
・5年以下:「短期譲渡所得」に分類され、高い税率が適用されます。
・5年超:「長期譲渡所得」に分類され、短期譲渡所得よりも税率が低く設定されています。
【譲渡所得税の税率】
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 合計税率(復興特別所得税含む) |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 30.630% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |
※復興特別所得税(所得税額の2.1%)は、東日本大震災の復興財源確保のため、2037年(令和19年)12月31日まで所得税と合わせて課税されます。
消費税|事業用マンション売却の場合にかかる税金
マンション売却で消費税が課税されるのは、売主がその不動産を事業用として扱っていた場合に限られます。
対象となるのは建物部分のみで、土地は非課税です。
ご自身の居住目的で所有していたマイホームを売る場合は、原則として消費税の課税対象ではありません。
ご自身のマンションを売却する際に消費税がかかるかどうか、またその場合の詳しい注意点については、後述のQ&Aセクションをご確認ください。
マンション売却でかかる税金のシミュレーション

ここでは、さまざまなケースを想定した税金シミュレーションを見ていきましょう。
ご自身の状況に近い例を参考に、税額のイメージを掴んでみてください。
【シミュレーション共通条件】
| ・購入時建物価格:3,000万円 ・購入時土地価格:3,000万円 ・購入時の諸費用合計:100万円 ・売却時の譲渡費用(仲介手数料、印紙税など):100万円 ・固定資産税清算金:5万円 ※固定資産税清算金とは、購入後の所有日数分に応じて買主が負担する金額のこと。 |
シミュレーション1.利益が出た場合の税金(長期譲渡所得)
【条件】
・売却価格:5,800万円
・所有期間:10年(長期譲渡所得)
・構造:鉄筋コンクリート造(償却率:0.015)
【計算】
|
1.減価償却費の計算 2.取得費の計算 3.譲渡価格の計算 4.譲渡所得の計算 5.譲渡所得税の計算 6.その他の税金 【合計税額】 |
シミュレーション2.譲渡所得がマイナスになった場合
【条件】
・売却価格:5,000万円
・所有期間:10年(長期譲渡所得)
・構造:鉄筋コンクリート造(償却率:0.015)
※その他の条件はシミュレーション1と同じ
【計算】
|
1.減価償却費、取得費、譲渡費用はシミュレーション1と同じ 2.譲渡価格の計算 3.譲渡所得の計算 譲渡所得がマイナス(▲1,790万円)になったため、譲渡所得は0円とみなされ、譲渡所得税はかかりません。 |
シミュレーション3.3,000万円特別控除を適用した場合
【条件】
・売却価格:6,500万円
・所有期間:8年(長期譲渡所得)
・構造:鉄筋コンクリート造(償却率:0.015)
・マイホームとして居住(3,000万円特別控除適用要件を満たす)
※その他の条件はシミュレーション1と同じ
【計算】
|
1.減価償却費、取得費、譲渡費用はシミュレーション1と同じ 2.譲渡価格の計算 3.譲渡所得の計算(3,000万円特別控除適用) 譲渡所得がマイナス(▲290万円)になったため、譲渡所得は0円とみなされ、譲渡所得税はかかりません。 |
マンション売却で役立つ!節税対策と活用ポイント

マンション売却で発生する税金は、可能な限り抑えたいものですよね。
実は、国が定めているさまざまな特例を上手に活用することで、税負担を大きく軽減できます。
これらの特例は自動的に適用されるわけではなく、ご自身で要件を確認し、確定申告を行うことで初めて恩恵を受けられますので、しっかりと理解しておきましょう。
1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
ご自身が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
譲渡所得税が3,000万円以下であれば、譲渡所得税はかかりません。
【主な適用要件】
・ご自身が住んでいる家屋やその敷地を譲渡すること
・転居してから3年後の12月31日までに売却すること(※この間に貸付けや事業用に供していても適用可)
・売主と買主が、配偶者や直系血族(親、子、孫など)、生計を一にする親族などの特別な関係でないこと
・この特例は「3年に1度だけ」適用可能
|
【注意】住宅ローン控除との併用不可 マイホームの買い換えで新たに住宅ローンを組む場合、「3,000万円特別控除」と「住宅ローン控除」は併用できません。 通常、住宅ローン控除の方が節税額が大きくなるケースが多いため、どちらが有利になるか慎重に比較検討が必要です。 |
2.譲渡損失が出た場合の損益通算・繰越控除の特例
マンションの売却価格が取得費や譲渡費用を下回り、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合でも、税金の還付を受けられる可能性があります。
これを「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の特例と呼びます。
「損益通算」、「繰越控除」については、以下の通りです。
・損益通算
売却で生じた譲渡損失を、その年の他の所得(給与所得や事業所得など)から差し引くことができます。
これにより、その年の総所得が減り、所得税や住民税が還付される場合があります。
例:給与所得500万円の人が、マンション売却で200万円の譲渡損失が出た場合、その年の所得は300万円として税金が計算されます。
・繰越控除
損益通算しても控除しきれなかった譲渡損失がある場合、その残額を翌年以降3年間繰り越して、将来の所得から差し引くことができます。
これらの特例には、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など、いくつかの種類があり、それぞれ適用要件が異なります。
詳しくは、以下の国税庁ホームページをご参考ください。
出典:「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」-国税庁
出典:「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」-国税庁
3.相続したマンション売却で使える「取得費加算の特例」
相続や遺贈によって取得した不動産を売却する際に、支払った相続税の一部を譲渡所得の「取得費」に加算できる特例です。
取得費が増えることで譲渡所得が減少し、結果として譲渡所得税の負担を軽減できます。
【主な適用要件】
・相続または遺贈により取得した不動産であること
・その不動産を取得した際に相続税が課税されていること
・相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること
|
【注意点】特定の空き家特例との併用不可 この特例は、相続した空き家を売却した場合に適用できる「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)とは併用できません。 相続したマンション売却ではどちらの特例も検討対象となることが多いため、ご自身の状況でどちらがより節税効果が高いか、慎重に判断することが重要です。 出典:「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」-国税庁 |
取得費加算に関する相続税の計算については、以下の記事の中で詳しく紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
4.所有期間10年超の軽減税率の特例
マイホーム(居住用財産)を売却し、売却した年の1月1日時点でその所有期間が10年を超えている場合、特定の条件下で譲渡所得税の税率が通常よりも軽減される特例です。
この特例は、前述の3,000万円特別控除と併用することが可能です。
【適用後の税率】
| 課税譲渡所得金額 (3,000万円特別控除後) |
所得税 (復興特別所得税含む) |
住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% | 14.21% |
| 6,000万円超の部分 | 15.315% | 5% | 20.315% |
【主な適用要件】
・売却した年の1月1日現在で、その家屋と敷地の所有期間が10年を超えていること
・以前にこの特例を適用している場合、前回の譲渡から3年以上経過していること
・売主と買主が、配偶者など特別な関係でないこと
|
【注意】住宅ローン控除との併用不可 この特例も、購入物件で住宅ローン控除を利用する場合は併用できません。 |
マンション売却後の確定申告|流れ・必要書類・注意点

マンションを売却した後には、確定申告が必要になるケースがほとんどです。
確定申告と聞くと複雑に感じるかもしれませんが、流れを把握し、必要な準備をすることでスムーズに進められます。
ここでは、確定申告の具体的な流れや必要書類、そして知っておくべき注意点を詳しく解説します。
確定申告はどんな時に必要?
マンション売却における確定申告は、主に以下のいずれかのケースに該当する場合に必須となります。
・譲渡所得(売却益)が出た場合
税金を納めるために確定申告が必要です。
・特例を適用する場合
前述した「3,000万円特別控除」や「譲渡損失の損益通算・繰越控除」などの特例を利用するには、たとえ譲渡所得税が0円になる場合でも確定申告が必須です。
確定申告は、原則としてマンションを売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。
この期限が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となりますので注意しましょう。
また、譲渡損失が出て、かつ特例を適用しない場合は、確定申告は不要です。
|
申告しないとどうなる? 売却益が出たにもかかわらず確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。 必ず期限内に申告を済ませましょう。 |
確定申告の流れ
不動産を売却した際の確定申告は、主にいくつかの段階を経て進められます。
確定申告の詳しい流れについては、以下の記事でも紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。
確定申告に必要な主な書類
確定申告では、売却した不動産に関する詳細な情報を提出するため、多くの書類が必要になります。
主な必要書類は以下の通りです。
| 書類の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 申告書類 | ・確定申告書B様式 ・確定申告書第三表(分離課税用) ・譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)など |
| 売却時の書類 | ・マンション売却時の売買契約書のコピー ・仲介手数料や登記費用など譲渡費用が確認できる領収書 |
| 購入時の書類 | ・マンション購入時の売買契約書のコピー ・購入時の仲介手数料や登記費用など取得費が確認できる領収書 ・登記事項証明書など(取得費不明の場合は代替書類を検討) |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードのコピー(表面・裏面)、または通知カードと運転免許証などの身元確認書類のコピー |
| その他の書類 | ・源泉徴収票(給与所得者の場合) ・住民票の除票(転居済みの場合) ・特例適用に必要な書類(例:住宅用家屋証明書など) |
※上記の他にも、ケースによっては別途書類が必要になる場合があります。
住民税の課税タイミングと支払い方法
譲渡所得税に含まれる所得税は、確定申告の際に納税しますが、住民税は所得税と課税タイミングが異なるため、注意が必要です。
住民税は、売却した年の所得に基づき翌年度の6月以降に課税されます。
会社員で給与から住民税が天引きされている方(特別徴収)は、翌年度の給与から増額されて天引きされます。
一方、給与天引きでない方(普通徴収)は、市区町村から納税通知書が送付され、通常年4回に分けてご自身で納付する必要があります。
マンション売却による増額分は翌年の住民税に反映されるため、「翌年の住民税が急に高くなった」と感じる方もいるかもしれません。
そのため、事前に支払い時期と金額の目安を把握しておくと安心です。
【Q&A】マンション売却の税金に関するよくある疑問と注意点

ここまで、マンション売却にかかる税金の種類や計算方法、節税対策、確定申告の流れを解説してきました。
ここでは、売却を検討している方が抱きやすい、税金に関する「よくある疑問」や「見落としがちな注意点」をQ&A形式でご紹介します。
Q1.マンション売却時の税金はいつ支払うの?
A.マンション売却で発生する税金は、以下のように種類によって支払うタイミングが異なります。
| 税金の種類 | 支払うタイミング |
|---|---|
| 印紙税 | 売買契約書を締結する際 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消などの登記手続きを行う際(決済・引き渡し時) |
| 譲渡所得税 | 売却した年の翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間中に納税(所得税) 住民税は翌年度6月以降に納付開始 |
| 仲介手数料 | 一般的に売買契約成立時と引き渡し完了時に分けて支払う |
| 消費税 | 課税対象となる費用(仲介手数料など)は、その支払い時に発生 事業用不動産売却の場合は引き渡し時など |
Q2.譲渡所得税がかからない場合でも確定申告は必要?
A.はい、税金がかからない場合でも確定申告が必要なケースがあります。
特に、本記事で紹介している「3,000万円特別控除」や「譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例」などの税金軽減特例を利用する際には、たとえ譲渡所得税が0円になる場合でも確定申告が必須です。
確定申告の必要性に関する詳しい内容は、「確定申告はどんな時に必要?」のセクションをご確認ください。
Q3.ローン残債がある場合、費用や手続きで注意することは?
A.マンション売却時に住宅ローンが残っている場合は、売却代金でローンを一括完済することが一般的です。
この際、以下の費用や手続きに注意が必要です。
・繰り上げ返済手数料
金融機関によっては、ローンを一括返済する際に手数料が発生します。
一般的に数千円~3万円程度が相場ですが、事前に確認しましょう。
・抵当権抹消登記
ローンを完済したら、金融機関が設定していた抵当権を抹消する登記が必要です。
この登記を済ませないと買主への所有権移転ができません。
登録免許税(不動産1件につき1,000円、マンションでは土地・建物で計2,000円)と、司法書士への報酬(1.5万円~2万円程度が相場)がかかります。
Q4.マンション売却で消費税はかかる?
A.前述の通り、個人がご自身のマイホームとしてマンションを売却する場合、消費税はかかりません。
しかし、以下のような事業目的で所有していたマンションを売却する場合は、建物部分にのみ消費税が課税されます(土地は非課税です)。
・賃貸マンションとして貸し出していた
・事務所や店舗として使用していた
ただし、売主が「免税事業者」(前々年の課税売上が1,000万円以下の事業者)であれば、消費税は発生しません。
事業用マンション売却の消費税計算は複雑なため、具体的な計算方法や有利な選択肢については、税理士に相談することをおすすめします。
Q5.相続したマンションを売る際、税金の計算で特に注意すべきことは?
A.相続したマンションを売却する場合、通常の売却とは異なる税金計算の注意点があります。特に以下の点に気をつけましょう。
・「取得費」の算出が複雑になる場合が多い
先述した「取得費が不明な場合」のセクションでも説明した通り、相続したマンションは、いつ、いくらで取得したかを示す購入時の契約書などがないケースも少なくありません。
取得費が不明確だと、税金計算で「概算取得費」(売却価格の5%)が適用され、譲渡所得が大きくなり税金が高くなる可能性があります。
古い書類を探したり、税理士に相談したりして、正確な取得費の把握に努めましょう。
・複数の特例の併用可否を慎重に判断する必要がある
相続したマンション売却で利用できる特例には、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」や、特定の空き家の場合に適用される「被相続人の居住用財産を売った場合の特例」(いわゆる空き家の3,000万円特別控除)があります。
これらの特例は併用できません。
ご自身の状況でどちらの特例がより節税効果が高いか、事前に税理士と相談して慎重に判断することが大切です。
また、相続した不動産を売却する方法については、以下の記事で詳しく紹介しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
税金で損しないマンション売却へ!まずは査定で一歩踏み出そう

マンション売却にかかる税金は、複雑で大きな負担に感じるかもしれません。
しかし、印紙税や登録免許税といった「必ずかかる税金」と、売却益が出た場合の「譲渡所得税」の仕組みを理解することで、賢く売却を進められます。
特に譲渡所得税は、購入価格や所有期間、利用できる特例によって税額が大きく変わりますので、3,000万円特別控除や譲渡損失の特例など、利用可能な節税策を最大限に活用しましょう。
また、特例適用時には確定申告が必須となるため、必要書類を揃え、期限内に手続きを完了させてください。
税金に関する疑問や最適な節税対策については、個別の状況で判断が難しい場合もあります。
そんな時は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
そして、税金の知識を身につけたら、次は「ご自身のマンションがいくらで売れるのか」を把握することが重要です。
適正な売却価格を知ることは、税金計算の基礎となるだけでなく、売却計画を立てる上で不可欠な第一歩となります。
ぜひ、この記事で得た知識を活かし、まずは無料査定でご自身のマンションの価値を把握してみませんか?
当サイトが提供する不動産一括査定サービス「イエイ」では、安心・納得のマンション売却を実現するためのお手伝いをします。
これからマンションの売却を検討している方は、一度お試しくださいね。


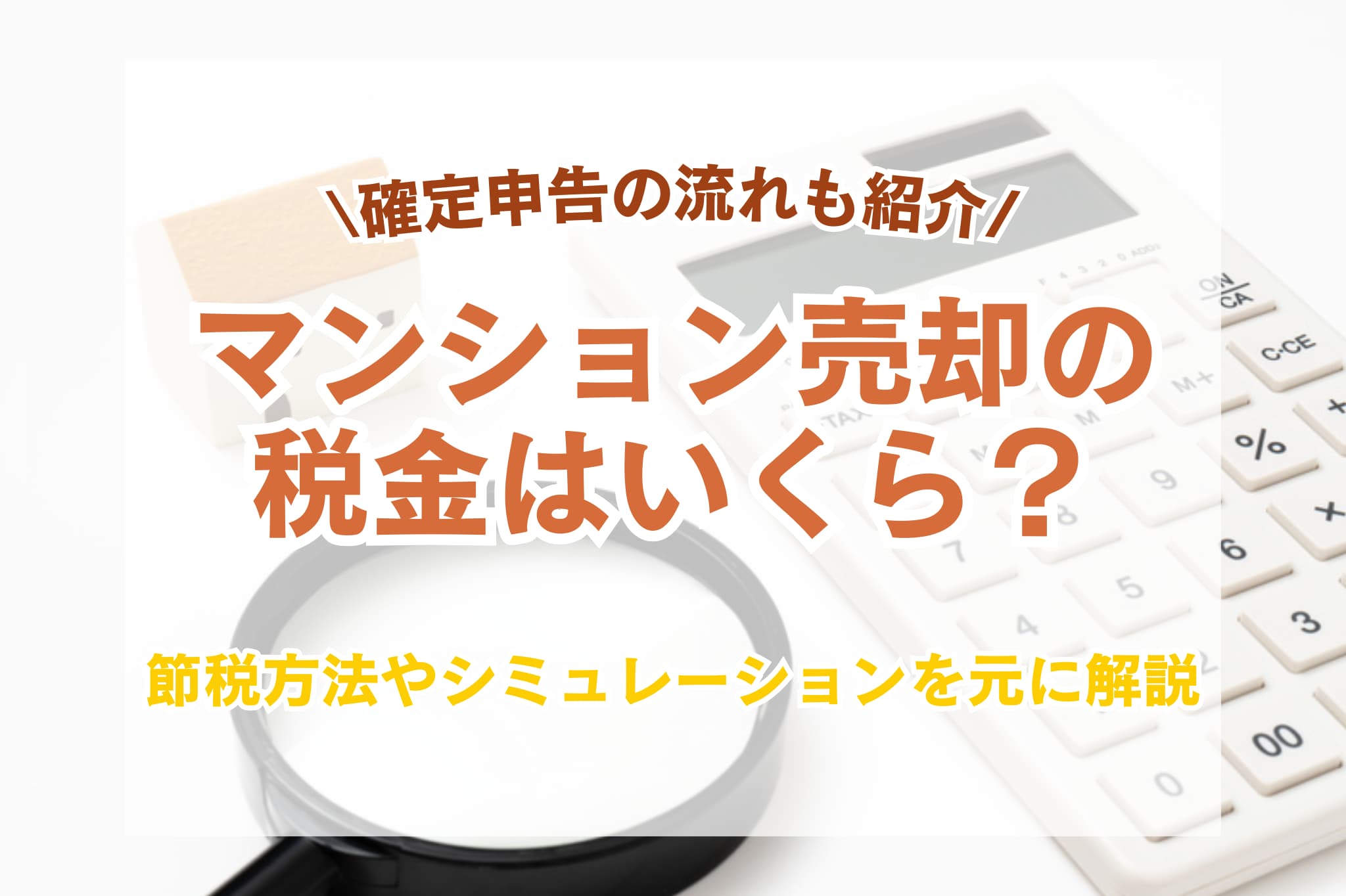


















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












