|
この記事でわかること ・離婚する際のペアローンで起こりうる4つの問題 |
家を購入する際に、夫婦でペアローンを組むことがよくあります。
二人で力を合わせて大きな買い物をしたものの、もしものことがあったらどうしよう…と不安に思っていませんか?
「ペアローンがあるから離婚できない」
「もし離婚したら、この家はどうなるんだろう?」
もしかして今、あなたは誰にも言えず、こっそりと調べているのかもしれません。
ご安心ください。ペアローンがあっても離婚はできますし、問題を解決する方法は必ずあります。
この記事では、ペアローンを組んだ夫婦が離婚する際に起こりうる問題と、その具体的な解決策をわかりやすく解説します。
専門的な知識がなくても問題ありません。
この記事を読めば、あなたの抱える漠然とした不安が解消され、次に取るべき行動がきっと見えてくるはずです。
この記事の目次
ペアローンを組んでいたら離婚できないって本当?

結論から言うと、ペアローンを組んでいても離婚はできます。
法律上、夫婦の離婚と金融機関とのローン契約は別だからです。
しかし、「ペアローンがあると離婚できない」と言われるのには理由があります。
それは、離婚によって夫婦関係は解消されても、金融機関とのローン契約はそのまま続くからです。
もし何も対策をせずに離婚した場合、家の所有権もローンの返済義務も夫婦に残ったままになります。
これが、離婚後に大きなトラブルを引き起こす原因となるのです。
離婚前に知っておきたい!住宅ローンの形態

「ペアローン」と聞くと、夫婦で組む住宅ローン全体を指すと思われがちですが、実際には複数の種類が存在します。
ここでは、あなたの状況を正確に把握するために、代表的な住宅ローンの形態とその違いをまとめました。
| ペアローン | 連帯債務 | 連帯保証 | 単独債務 | |
|---|---|---|---|---|
| ローンの契約数 | 2本 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 債務者 | 夫婦それぞれ | 夫婦の一方が主債務者、もう一方が連帯債務者 | 夫婦一方が主債務者 | 夫婦一方のみ |
| 住宅ローン控除の利用 | 夫婦それぞれ | 夫婦それぞれ | 主債務者のみ | 債務者のみ |
| 団体信用生命保険(団信)への加入 ※ | 夫婦それぞれ | 主債務者のみが加入可 (連帯債務者も有料で加入できる場合あり) |
主債務者のみ | 債務者のみ |
※団体信用生命保険(団信)とは、ローン返済中に契約者に万が一のことが発生した際に、保険会社がローンの残高を支払う生命保険のことです。
ペアローンは、夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約する仕組みです。
そのため、審査や団信の加入も二人分行われますが、その一方で申し込み手数料などの諸費用も二重にかかるというデメリットがあります。
これに対し、夫婦の収入を合算して1本のローンを組むのが、連帯債務と連帯保証です。
連帯債務は、夫婦が同等の責任を連帯して負います。
一方、連帯保証は、一方が主債務者となり、もう一方は返済が滞った場合にのみ責任を負う立場となります。
また、夫婦のどちらか一方のみが単独でローンを組む単独債務という形態も存在します。
この形態では借入額が少なくなりますが、離婚時にローンの問題が起こりにくいというメリットがあります。
この中で、離婚トラブルに最も発展しやすいのが「ペアローン」です。
夫婦それぞれが債務者であることから、問題が複雑化しやすい傾向にあります。
離婚時にペアローンで起こりやすい4つの問題

ここでは、ペアローンがある状態で離婚した場合に、実際に起こりやすいトラブルを具体的に見ていきましょう。
これらの問題を事前に知っておくことが、スムーズな解決への第一歩となります。
問題1.相手がローンを滞納し、あなたの負担が増える
ペアローンを組む際、夫婦は互いの連帯保証人になるのが一般的です。
これは、もし片方がローンの返済を滞らせた場合、もう片方が代わりに全額を支払う義務を負うことを意味します。
つまり、離婚して縁が切れても、金融機関との契約は続いているため、この義務は消えません。
たとえば、離婚後に夫がローンを滞納し始めた場合、金融機関は連帯保証人である元妻に、夫の分のローンの返済を求めます。
そうなると元妻は住んでいない家のローンまで、自分の収入から支払わなければならないという事態になりかねません。
最悪の場合、ローン残高の一括返済を求められたり、元夫の代わりに返済し続けた結果、自己破産に至るケースもあります。
問題2.家を出た後もローンを払い続けることになる
ペアローンは、夫婦が一緒に住むことを前提とした住宅ローンです。
離婚によってどちらかが家を出た場合、金融機関との契約違反となる可能性があります。
金融機関は、債務者が物件に居住していることを融資の条件としていることが多く、もし違反が発覚した場合、ローン残高の一括返済を求められるリスクがあります。
また、相手がローンの返済を続けている場合でも、名義が残っている限り、あなたは住んでいない家のローンを払い続けることになります。
問題3.家を売りたいと思っても、相手の同意が得られない
ペアローンで組んだ家は、夫婦の共有名義になっていることがほとんどです。
不動産を売却するには、名義人全員の同意が必要です。
民法第251条でも以下のように定められています。
|
【参考】民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 出典:民法-e-Gov法令検索 |
離婚時に感情的な対立があると、相手が売却に同意してくれないケースは珍しくありません。
相手と連絡が取れなくなったり、再婚相手が反対したりすることも考えられます。
もし元配偶者の同意が得られないと、家を売ることはできず、その結果、誰も住んでいない家のローンを払い続けるという苦しい状況に陥ってしまいます。
共有名義の家の売却については、以下の記事で詳しく解説しているのでこちらもご参考ください。
問題4.新しい家のローンが組めない
離婚後、あなたが新しい家を買ったり、再婚して新居を購入したりする場合、ペアローンの残債が障害になる可能性があります。
金融機関は、あなたの返済能力を審査する際、既存のペアローン残高も考慮します。
たとえ元夫がローンを支払っていたとしても、名義が残っている限り、あなたの借入可能額は減ってしまいます。
その結果、新しい住宅ローンを組めないという事態になりかねません。
ペアローンを解消する5つの解決策

ペアローンがある状態でも、夫婦で協力すれば問題を解決する方法はあります。
ここからは、ペアローンを解消するための解決策について、メリット・デメリットも踏まえてご紹介します。
あなたの状況に合った解決策を選びましょう。
解決策1.家を売却してローンを完済する
最もシンプルで、トラブルが少ない解決策です。
家を売却したお金でローンを完済し、残ったお金(売却益)を夫婦で分け合います。
【メリット】
・ローンを完済できるため、離婚後の経済的・精神的な負担がなくなる
・夫婦の経済関係をきれいに精算できる
【デメリット】
・売却益が出ない「オーバーローン」の場合は、別途不足分を準備する必要がある
・夫婦双方の同意が必要
「オーバーローン」については、【ペアローンを解消する前に準備すべきこと】で詳しく解説しているので、こちらもご参考ください。
解決策2.ローンを一本化して片方が住み続ける
夫婦のうち、一方が単独で住宅ローンを組み直し、元のペアローンを完済する方法です。
この方法を使えば、夫婦の一方が家に住み続けることができます。
【メリット】
・家を売らずに住み続けられる
・ローンを一本化することで、夫婦の経済的な関係を断ち切れる
【デメリット】
・ローンを一本化する側の収入が、残債に対して十分でなければならない
・金融機関の厳しい審査に通る必要がある
この方法は、ローンを引き受ける側の収入や信用力が重要になります。
ペアローンを組んだのは、一人では借りられない金額を借りるためだったはずです。
そのため、離婚後に一人で審査に通るのは難しい場合が多いです。
解決策3.リースバックで家を現金化し、住み続ける
リースバックとは、家を売却して現金化し、その後は賃貸として住み続ける方法です。
この方法なら、売却代金でローンを完済しつつ、引っ越しをせずに済みます。
【メリット】
・家を売却してローンを完済できる
・売却後もそのまま家に住み続けられる
【デメリット】
・売却価格が市場価格より低くなる可能性がある
・家賃を払い続ける必要がある
離婚によって家を売らざるを得ないが、子どもがいるなどの理由で引っ越しを避けたい場合に有効な選択肢です。
解決策4.夫婦で話し合い、引き続きローンを払い続ける
ペアローンを解消せずに、離婚後も夫婦で協力してローンを払い続ける方法です。
この場合、所有権も名義も夫婦の共有のままとなります。
【メリット】
・家に住み続けられる
・面倒な手続きが不要
【デメリット】
・相手のローンの支払いが滞るリスクがある
・将来、家を売却する際に相手の同意が必要(共有名義のため)
・再婚時に新しいローンが組みづらい
この方法は、夫婦の関係が円満で、離婚後も信頼関係が続く場合にのみ選択すべきです。
解決策5.任意売却で家を売る
任意売却とは、ローン返済が難しくなった場合に、金融機関の合意を得て家を売却する方法です。
【メリット】
・競売よりも高い価格で売却できる可能性がある
・売却時期や引っ越し時期を調整できる
【デメリット】
・売却後もローンが残る可能性がある
・信用情報に傷がつく
任意売却は、すでにローンの支払いが滞り始めた場合や、他の解決策が難しい場合の最終手段として検討すべき方法です。
任意売却については、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもご参考ください。
ペアローンを解消する前に準備すべきこと

先述の通り、離婚によってペアローンを解消するにはさまざまな方法があります。
しかし、どの方法を選ぶにしても、まずはあなたの家の状況を正確に把握することが大切です。
ここからは、夫婦で話し合いを始める前に、準備しておきたいことを解説します。
1. アンダーローンとオーバーローンを理解する
ローンを抱えたまま家を売却する場合、必ず耳にするのが「アンダーローン」と「オーバーローン」という言葉です。
これらを理解することは、あなたの家がいくらで売れそうか、現実的な価格を把握するために不可欠です。
アンダーローン
アンダーローンとは、家の売却価格が、住宅ローンの残高を上回っている状態です。

たとえば、ローン残高が2,000万円に対し、家が3,000万円で売れる場合がこれにあたります。
この場合、売却代金でローンを完済でき、さらに1,000万円の売却益が手元に残ります。
オーバーローン
オーバーローンとは、家の売却価格が住宅ローンの残高を下回っている状態です。

たとえば、ローンの残りが3,000万円に対し、家が2,000万円でしか売れない場合がこれにあたります。
この場合、売却代金だけではローンを完済できません。
2. ローンの一本化が可能か計算する
「ローンを一本化したいけど、一人で審査に通るか不安…」と感じているなら、まずはご自身の年収や現在のローン残高で、いくら借りられるか計算してみましょう。
金融機関のウェブサイトにあるローンシミュレーターを活用すれば、簡単に概算を知ることができます。
この計算はあくまで目安ですが、一本化が可能かどうかの判断材料になります。
3. 弁護士や不動産会社などの専門家に相談する
離婚時の夫婦間での話し合いは、感情的になりがちです。
特に住宅ローンのようなお金の問題は、こじれると大きなトラブルに発展しかねません。
こうしたトラブルを未然に避け、スムーズに解決するためには、早い段階から専門家に相談しましょう。
そうすることで、あなたの状況に合った最適な解決策が見つかります。
多くの専門家は無料相談を受け付けているので、まずは気軽に問い合わせてみましょう。
【主な相談先】
| 相談先 | 特徴 |
|---|---|
| 弁護士 | 離婚そのものや、財産分与、慰謝料といった法律的な問題について相談できます。 |
| 不動産会社 | 家の売却価格査定や、任意売却の相談に乗ってもらえます。 |
| 金融機関 | ローンの一本化(借り換え)が可能かどうか、具体的な審査や手続きについて相談できます。 |
| ファイナンシャルプランナー | 離婚後の生活設計や、お金に関する全般的な相談ができます。 |
また、家を売却することをお考えの場合は、まずは信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。
当サイトが提供する不動産一括査定サービス「イエイ」では、物件情報等を一度入力するだけで、簡単にあなたに最適な不動産会社を見つけることができます。
離婚問題に強い不動産会社とも提携しているので、トラブルを最小限にしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご活用ください。
【まとめ】離婚に伴うペアローンの問題は、冷静な準備で乗り越えられる

ペアローンがある状態で離婚を検討するのは、非常に大変なことです。
しかし、ご安心ください。
ペアローンがあるからといって、離婚を諦める必要はありません。
この記事では、離婚時に起こりうる問題から、家を売却する、ローンを一本化する、リースバックを利用するなど、5つの具体的な解決策をご紹介しました。
大切なのは、感情的にならず、まずは現状を正しく把握し、冷静に解決策を検討することです。
そのためには、家の価値を把握したり、専門家に相談したりといった、具体的な一歩を踏み出すことが重要です。
また、この問題の解決は、決して一人で抱え込むものではありません。
不動産の専門家や弁護士など、あなたの悩みに寄り添ってくれるプロは必ずいます。
もしあなたが今、この記事を読み、離婚に伴うペアローンの知識を少しでも理解できたのであれば、それは解決への第一歩をすでに踏み出している証拠です。
あなたの未来のために、今できることから始めてみましょう。


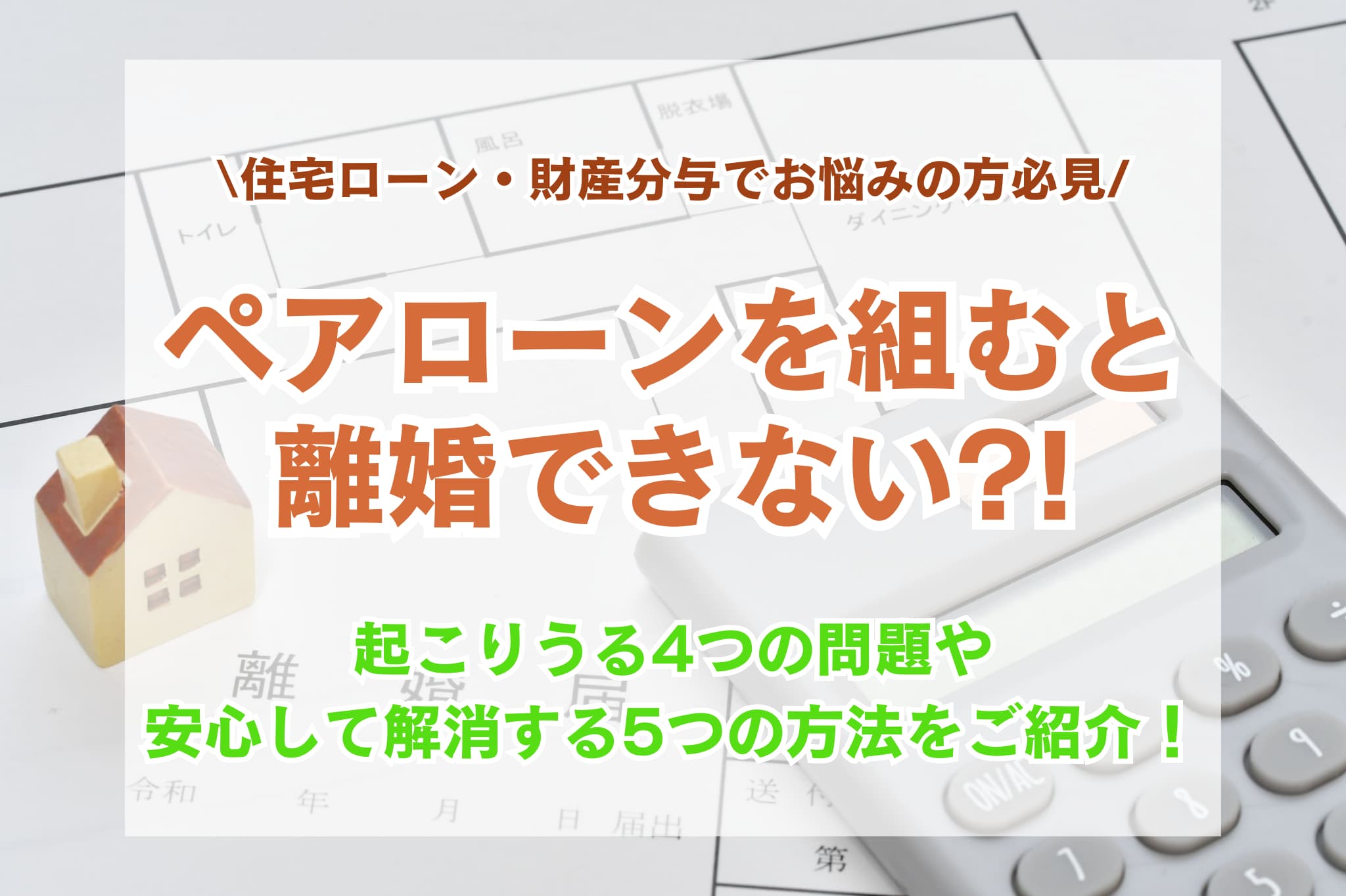
















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












