|
この記事でわかること ・第一種低層住居専用地域とは高さ10m以下の住宅が立ち並ぶ地域のこと ・第一種低層住居専用地域のメリット・デメリットやどんな人におすすめか ・土地がどの地域に区分されるかの確認方法 |
「静かで落ち着いた環境で、ゆったりと暮らしたい」「子どもをのびのびと育てたい」など、マイホームを探すとき、多くの人がそんな理想の住環境を思い描くのではないでしょうか。
じつは、その理想を法律で可能にしてくれる場所があります。
それが、今回詳しく解説する「第一種低層住居専用地域」です。
不動産情報サイトや物件のチラシで一度は目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
この記事では、第一種低層住居専用地域の基本的なルールから、具体的なメリット・デメリット、さらには他の地域との違いまで、専門的な内容を誰にでも分かりやすく徹底解説していきます。
この記事の目次
第一種低層住居専用地域とは?

家を建てたり土地を購入したりする際、「この土地にはどんな建物を建てられるのだろう?」と考えたことはありませんか。
じつは、日本の街は「好きな場所に好きな建物を自由に建てられる」わけではありません。
計画的な街づくりのために、土地の使い道には「用途地域」というルールが定められています。
以下の表のように用途地域は全部で13種類あり、大きく「住居系」「商業系」「工業系」の3つのグループに分けられます。
| 系統 | 用途地域名 | 概要 |
|---|---|---|
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な住環境を守るための最も規制が厳しい地域。 |
| 住居系 | 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な住環境を守る地域。小規模な店舗も建てられる。 |
| 住居系 | 田園住居地域 | 農業と調和した低層住宅の環境を守る地域。農産物直売所なども可能。 |
| 住居系 | 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な住環境を守る地域。大学や病院、中規模店舗も可。 |
| 住居系 | 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の環境を守る地域。やや大きな店舗や事務所も建てられる。 |
| 住居系 | 第一種住居地域 | 住居の環境を守る地域。大規模な店舗や事務所、ホテルも建てられる。 |
| 住居系 | 第二種住居地域 | 主に住居の環境を守る地域。カラオケボックスなども可能になる。 |
| 住居系 | 準住居地域 | 道路沿いの自動車関連施設などと住居が調和する地域。 |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 住民が日用品の買い物をするための地域。小規模な工場も可能。 |
| 商業系 | 商業地域 | 銀行や百貨店などが集まる都心部。ほとんどの商業施設が建てられる。 |
| 工業系 | 準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設が立地する地域。危険性の高い工場は不可。 |
| 工業系 | 工業地域 | どんな工場でも建てられる地域。住宅や店舗も建てられるが、学校や病院は不可。 |
| 工業系 | 工業専用地域 | もっぱら工業のための地域。住宅、店舗、学校、病院などは建築不可。 |
この用途地域の一つが、「第一種低層住居専用地域」です。
第一種低層住居専用地域とは高さ10m以下の住宅が立ち並ぶ地域です。
高さだけでなく、隣の家との距離も十分にとる必要があるため高級住宅街と呼ばれる事が多い地域です。
第一種低層住居専用地域という区分の場所は、都市計画法という法律によって決められています。
用途地域について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
第一種低層住居専用地域に建てられる建物

第一種低層住居専用地域は「住居専用」とあるため、住みやすさを重視した特徴があります。
そのため、建てられる建物には以下の表のように制限があります。
| 建物の種類 | 建てられるかどうか |
| 住宅 | ○ |
| 小規模な店舗または事務所兼住宅 | ○ |
| 幼稚園から高校までの教育施設 | ○ |
| 図書館 | ○ |
| 神社、お寺、教会などの宗教施設 | ○ |
| 老人ホーム | ○ |
| 交番 | ○ |
| 住宅を兼用しない事務所や店舗 | ✕ |
| ホテルなどの宿泊施設 | ✕ |
| パチンコ店 | ✕ |
| ボーリング、スケート場、プール | ✕ |
| 映画館 | ✕ |
| 工場 | ✕ |
| 駐車場 | ✕ |
このように、騒音の可能性がある商業施設や安全面に配慮が必要な工場などは建てることができません。
そのため、住宅地としてはとても過ごしやすい環境になっています。
しかし、住宅であっても建物の高さなどに制限があるため注意が必要です。
| 制限 | |
| 高さ | ~10m、~12m(※) |
| 敷地の端から住宅までの距離 | 1m~ |
| 建ぺい率 | 30%~60%(※) |
| 容積率 | 50~200%(※) |
(※地域によって異なります)

これらの制限によって圧迫感のある大きい建物が建ったり、住宅が密集することはありません。
土地がどの地域に区分されるかの確認方法

地域の特徴がわかったところで気になるのは「これから自分が買おうとしている土地はどの地域に分類されるんだろうか」ということです。
土地がどの用途地域に含まれるかを確認する方法は
- 不動産業者に聞く
- 役所が提供しているサービスで確認する
の2通りがあります。
不動産業者に聞く
土地を買おうと不動産業者へ足を運んでいる状態ならその業者へ「この土地はどの地域に該当しますか?」と聞いてみましょう。
用途地域は物件概要書などの資料に必ず記載されているので、きちんとした不動産業者であれば丁寧に教えてくれます。
これは宅建業法という法律によって不動産業者は土地の購入時に詳細な説明をすることが義務付けられているからです。
役所で調べる
まだ不動産会社に足を運んではいないけど買おうか悩んでいる土地がある場合はその土地がある役所で確認しましょう。
手軽なのはインターネットで、「〇〇(土地名)+用途地域」と調べて役所が提供している情報を確認する方法です。
以下のような手順で検索します。
- 検索エンジンを開く:GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使います。
- キーワードで検索:「〇〇市 用途地域」や「△△区 都市計画図」といったキーワードで検索します。
- 都市計画情報マップにアクセス:検索結果から、自治体が提供している都市計画情報や都市計画図のページを探します。多くの場合、地図上で住所を入力すると、その場所が色分けされた用途地域マップが表示されます 。
- 凡例を確認:地図の凡例(色の説明)を見て、目的の土地がどの色に該当するかを確認します。例えば、第一種低層住居専用地域は薄い緑色で示されることが一般的です。
もしお住まいの自治体がインターネットでの情報公開を行っていない場合は最寄りの役所にある都市計画を担当している窓口へ確認しに行く必要があります。
第一種低層住居専用地域のメリット

これまでご紹介してきたように第一種低層住居専用地域には、さまざまな制限がありますが、裏を返せば騒音の可能性がある商業施設、安全面に配慮が必要な工場などが建てられないため、住宅地としてはとても過ごしやすい環境になっているなどのメリットがあります。
以下で詳しく説明していきます。
閑静で落ち着いた住環境
最大のメリットは、何と言ってもその「静けさ」です。
用途制限により、スーパーや工場、パチンコ店といった商業・娯楽施設が建てられないため、昼夜を問わず静かな環境が保たれます。
大型トラックの往来や、不特定多数の人の出入りも少ないため、騒音に悩まされることはほとんどありません。
自宅で穏やかに過ごしたい方や、子育てに集中したい家庭にとって、これ以上ない理想的な環境と言えるでしょう。
日当たりや風通しが確保されやすい
マイホームを建てた後に「隣に高いマンションが建って、リビングが真っ暗になってしまった」という話は、都市部ではよくあるトラブルです。
しかし、第一種低層住居専用地域では、絶対高さ制限や斜線制限、日影規制によって建物の高さが厳しくコントロールされているため、そのような心配は無用です。
将来にわたって良好な日当たりと風通しが法的に守られているという安心感は、金銭には代えがたい大きな価値があります。
統一感のある街並みと良好な治安
様々な建築制限が組み合わさることで、この地域にはゆったりとした敷地に低層の住宅が建ち並ぶ、統一感のある美しい街並みが形成されます。
建ぺい率が低いため、各戸に庭などの緑が多く、開放的な景観が広がります。
また、基本的に住民以外の出入りが少ないため、地域全体のコミュニティの目が行き届きやすく、治安が良い傾向にあります。
子どもを安心して遊ばせられる環境は、子育て世代にとって大きな魅力です。
資産価値が落ちにくい
不動産の価値は、建物そのものだけでなく、周辺環境に大きく左右されます。
第一種低層住居専用地域は、法律によって良好な住環境が永続的に保護されているため、周辺環境の悪化による資産価値の下落リスクが極めて低いのが特徴です。
むしろ、その希少性と安定した住環境への高い需要から、資産価値が維持・向上しやすい傾向にあります。
マイホームを単なる住まいとしてだけでなく、長期的な資産として捉えるならば、この地域の物件は非常に堅実な投資対象と言えます。
高めの土地価格は、将来の価値を担保するための「保険料」と考えることもできるでしょう。
第一種低層住居専用地域のデメリットと注意点

住みやすさという観点から見ると第一種低層住居専用地域はメリットだらけです。
一方で暮らしやすさはどうか?と言うといくつかのデメリットがあります。
コンビニやスーパーが近くにない
第一種低層住居専用地域はあくまで快適な住環境を目的とした地域であるためスーパーやショッピングモールなどは建設することが出来ません。
同様にコンビニや飲食店なども徒歩圏内には無いと思っておいた方がいいでしょう。
自動車を持っていれば気にならないかも知れませんがちょっとした買い物に手間がかかるのは不便です。
そのため、居住者の高齢化に伴ってコンビニを求める声は年々大きくなっており、2019年6月から建築基準法の内容が改定されました。
「建築基準法第48条1項」では、「良好な住居の環境を害するおそれがない」または「公益上やむを得ない」場合には、原則以外の建物も建てることができると定められています。
つまり、コンビニが良好な住居の環境を害する恐れがないと認められれば、第一種低層住居専用地域でもコンビニを建てることができるということです。
また、2021年6月以降は建築基準法がさらに改正されたことで、第一種低層住居専用地域にコンビニ等の店舗を建てる際には、建築審査が不要となりました。
そのため、従来よりも第一種低層住居専用地域でコンビニ等は建てやすくなったと言えるでしょう。
交通の便が悪い
閑静な住環境を確保するため、第一種低層住居専用地域は、騒音源となる鉄道の駅や幹線道路から意図的に離れた場所に指定されていることが少なくありません。
その結果、最寄り駅までバスを利用したり、徒歩で長い時間がかかったりするケースも多く見られます。
通勤・通学の利便性を最優先に考える方や、車の運転をしない方にとっては、日々の移動が負担になる可能性があります。
多くの住民にとって、自動車が生活必需品となっているのが実情です。
理想の家づくりができない場合がある
統一感のある美しい街並みは、裏を返せば、個々の住宅デザインに対する自由度が低いことを意味します。
絶対高さ制限や斜線制限のため、開放感のある3階建てや、吹き抜けのあるデザインが難しくなることがあります。
また、建ぺい率・容積率の制限により、敷地がそれほど広くない場合に、十分な床面積を確保できない可能性も出てきます。
こだわり抜いたオリジナリティあふれる家を建てたいという方にとっては、これらの規制が足枷に感じられるかもしれません。
土地の価格が周辺エリアより高くなる傾向がある
これまで述べてきたように、第一種低層住居専用地域は、その良好な住環境から非常に人気が高く、需要が安定しています。
その結果、隣接する他の用途地域と比較して、土地の価格が高くなる傾向にあります。
また、敷地面積の最低限度が定められている場合、必然的にある程度の広さの土地を購入する必要があり、総額も大きくなりがちです。
予算に限りがある中で物件を探す場合、選択肢が狭まる可能性があります。
第一種低層住居専用地域はこんな方におすすめ

第一種低層住居専用地域はその特徴からマンションやアパートなどは建てることが出来ません。
反対に平屋の広々とした日当たりのよい一軒家を建てやすいため一人暮らしよりは家族で住むのに向いている地域です。
そのため、具体的には以下のような方に向いていると言えるでしょう。
- 安全で静かな環境を最優先する子育て世帯
- 自宅で過ごす時間が長く、穏やかな毎日を求めるリタイア世代や在宅ワーカー
- 自動車を所有しており、買い物のための移動が苦にならない方
- マイホームを長期的な資産と捉え、価値の安定性を重視する方
第一種低層住居専用地域に3階建ての建物を建てるには

2世帯住宅にしたい、用意できる予算の関係で広い土地が用意できないなどの様々な事情で3階建て以上の住宅を建てたい方もいらっしゃると思います。
しかし、第一種低層住居専用地域には建物の高さを原則として10mまたは12mに制限する「絶対高さ制限」が設けられています。
一般的な木造住宅では、1フロアの高さを約3mとすると、3階建てを建てた場合、全体の高さが9m〜10m程度になります。
つまり、10mの高さ制限がある地域では、3階建てを建てること自体が物理的に非常に難しくなるのです。
そのため、結論から申し上げると3階建てを建てたい場合は第一種、第二種低層住居専用地域で家を建てるのはやめたほうがいいでしょう。
というのも高さ制限をはじめとした規制をくぐり抜けて家を建てるとなるとかなり形が制限されます。
もし3階建て以上の住宅を建てたいなら第一種中高層住居専用地域がオススメです。
この地域はスーパーマーケットや飲食店を建てることは出来ますが、あくまで住居用地域であるためオフィスビルなどの建設は禁止されています。
なので利便性と、快適さをある程度両立出来ています。
「第二種低層住居専用地域」との比較

第一種低層住居専用地域を検討していると、必ずと言っていいほど比較対象になるのが「第二種低層住居専用地域」です。
名前が非常に似ていますが、この二つには明確な違いがあります。
最大の違いは「コンビニなどの小規模な店舗」が建てられるかどうかになります。
【店舗の建築に関するルール】
- 第一種低層住居専用地域:原則として、店舗の建築は認められていない(住宅兼用のごく小規模なものを除く)
- 第二種低層住居専用地域:床面積が150㎡以内で、建物の2階以下の部分であれば、コンビニエンスストアや飲食店などの店舗を建てることが許可されている
つまり、「第二種」は、低層住宅地の良好な環境を守るという大原則は共有しつつも、住民の利便性を少しだけ考慮して、ごく小規模な商業施設の立地を許容している地域なのです。
高さ制限や建ぺい率・容積率といった他の規制については、両者に大きな違いはありません。
この違いを分かりやすく表にまとめました。
| 比較項目 | 第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 低層住宅の良好な住環境を厳格に保護する | 主に低層住宅の良好な住環境を保護する |
| 店舗・飲食店の建築 | 原則不可 | 床面積150㎡以内・2階建て以下なら可能 |
| 街の雰囲気 | ほぼ住宅のみで構成される、極めて閑静な住宅街 | 閑静な住宅街の中に、コンビニや小さなカフェが点在する可能性がある |
| こんな人におすすめ | 環境の純粋性を最優先し、買い物は車で遠出することも厭わない人 | 静かな環境は欲しいが、歩いて行ける距離に最低限の店が欲しいと考える人 |
どちらの地域が自分に合っているかは、それぞれのライフスタイルや価値観によって決まります。
第一種低層住居専用地域が向いている人
- 住環境の質を何よりも優先する「環境至上主義」の方。
- 法的に保証された最大限の静けさを求め、そのための不便さは許容できる方。
- 日常の買い物は週末に車でまとめ買いするスタイルの方。
第二種低層住居専用地域が向いている人
- 静かな住宅街の雰囲気は好きだが、少しの利便性も確保したい「バランス重視」の方。
- 「いざという時に歩いて行けるコンビニがあると安心」と感じる方。
- ごくわずかな商業施設の存在による、多少の人の出入りは気にならない方。
以上のような違いを理解し、自身の生活スタイルと照らし合わせ、最適な土地選びに活かしましょう。
第一種低層住居専用地域の特徴とライフスタイルを照らし合わせよう

この記事では、都市計画法で定められた「第一種低層住居専用地域」について、その特徴から具体的な建築制限、メリット・デメリットまでを解説してきました。
第一種低層住居専用地域に家を建てるか判断する際は、自身のライフスタイルと照らし合わせて今後の生活の利便性を考慮することが重要です。
最後に低層住居専用地域のメリットとデメリットをまとめておくので、ぜひ判断に役立ててくださいね。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|


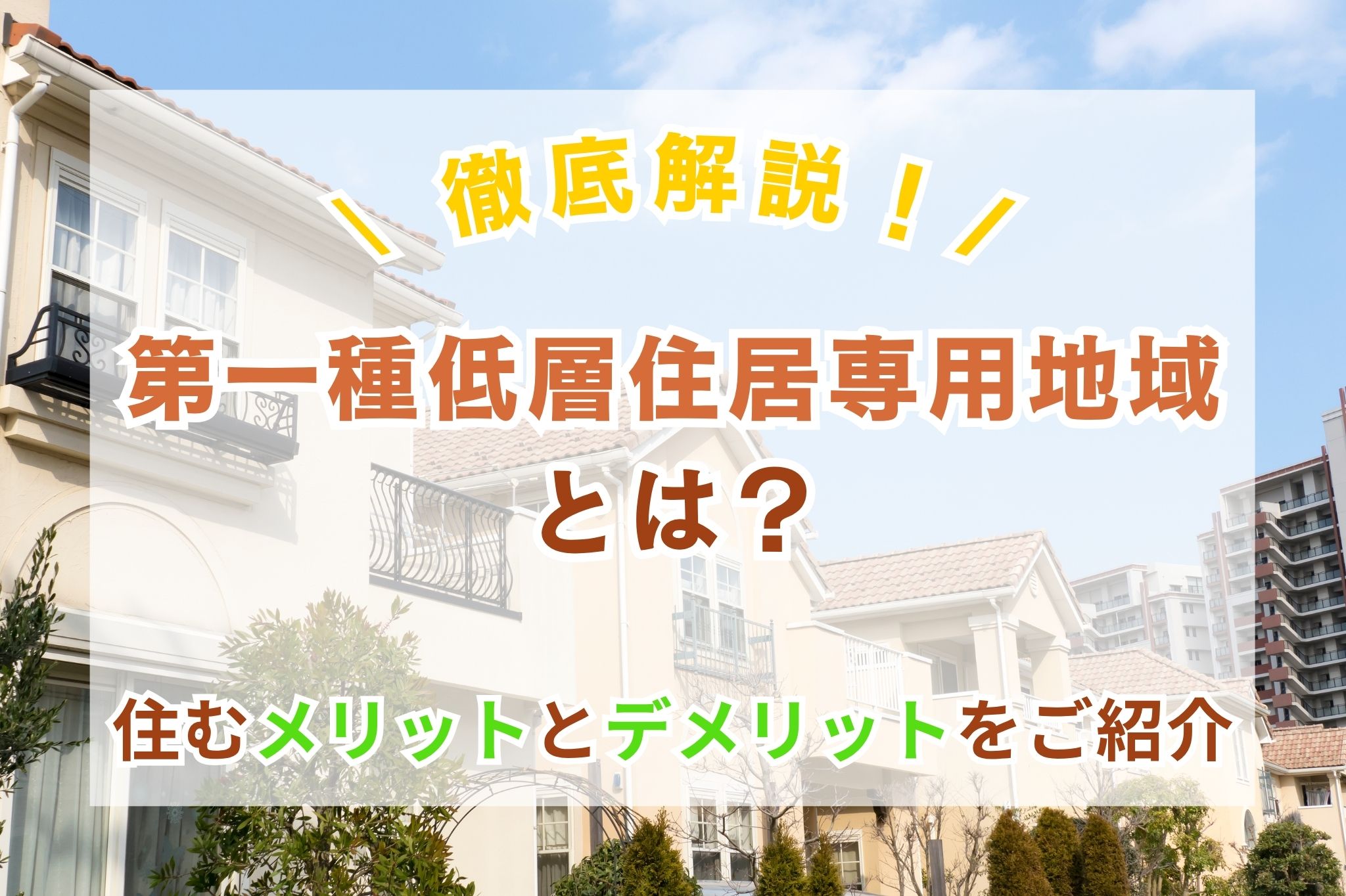















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












