|
この記事で分かること ・不動産売買契約書の基本知識 |
不動産の売買において必ず必要となるのが、「不動産売買契約書」です。
後々のトラブルを防ぐためにも、契約書を不備なく正確に作成することは非常に重要です。
しかし、不動産の専門知識や売買経験がない場合、どのような流れで不動産売買契約書が作成されるのか分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、不動産の売買時に必要となる不動産売買契約書の基本知識と押さえるべき重要事項、さらに契約時に起こりやすいリスクとその回避策について解説します。
安心して取引を進めるために、ぜひ本記事を参考にしてください。
この記事の目次
不動産売買契約書とは?基本を解説

不動産売買契約書とは、土地や建物といった不動産の売買に際し、売主と買主の間で合意した契約条件を詳細に記載した書面のことです。
この書面には、売買の対象となる不動産(物件の所在地、面積など)、売買代金の額、その支払い方法や時期、物件の引き渡し時期、所有権の移転時期など、取引の基本となる条件が明記されています。
この契約書があることで、取引の当事者双方の権利と義務が明確になります。
そして、万が一「言った、言わない」といった意見の食い違いやトラブルが発生した場合、この契約書が法的な証拠として非常に重要な役割を果たします。
高額な資産が動く不動産取引において、不動産売買契約書は安全かつ公正な取引を担保するための生命線と言えるでしょう。
|
【補足ポイント】不動産売買も電子契約が可能に 不動産売買契約書は、必ずしも「紙」である必要はありません。 |
不動産売買契約書がないとどのようなリスクが生じる?
日本の法律では、売買契約は当事者間の合意があれば口頭でも成立するとされています。
しかし、不動産売買において口頭のみで契約を進めることは現実的ではなく、極めて高いリスクを伴います。
例えば、口頭で契約して売買代金や引き渡し条件の認識にずれが生じた場合、「そんなことは言っていない」「こういう意味だと思った」といった水掛け論に発展しかねません。
特に不動産のような高額で複雑な取引では、記憶違いや解釈の相違が大きな紛争へと発展する可能性が高まります。
不動産売買契約書を作成して書面で記録することで、こうしたリスクを回避し、取引の透明性と安全性を確保することができるのです。
不動産売買契約書はいつ誰が作成するのか?
不動産売買契約書は、以下のように売買方法によって作成者が異なります。
| 売買方法 | 作成者 |
|---|---|
| 仲介 | 仲介を依頼する不動産会社 ※売主側・買主側の仲介会社が異なる場合は、一方の会社が作成する |
| 買取 | 買取を依頼する不動産会社 |
| 個人売買 | 売主・買主で話し合い個人で作成するが、司法書士、弁護士、行政書士などへの依頼が推奨される |
個人で作成する場合は、インターネット上でダウンロードできるひな形などを参考にして進めましょう。
また、不動産売買契約書は、買主からの購入申込みがあった後、売主・買主双方で契約の条件を話し合い、決まり次第作成する形になります。
そして、重要事項説明書に基づく説明が行われた後、契約締結日当日に、内容を最終確認したうえで契約書に署名・押印するという流れが一般的です。
詳しくは、以下の図解を参考にしてみてください。

重要事項説明書とは?
重要事項説明書(35条書面)とは、契約前に買主へ物件や取引条件に関する重要な情報を伝えるための書類です。
不動産売買では、契約を締結する前に、宅地建物取引士が買主に対してこの書面を交付し、内容を説明することが法律(宅地建物取引業法)で義務付けられています。
重要事項説明では、主に以下の情報が説明されます。
| 取引する物件に関する情報 | ・物件の所在地や種類、構造、床面積 ・登記された権利に関する情報(所有権など) ・法令に関する情報(建築基準法など) ・インフラ設備に関する情報(上下水道、電気、ガスなど) |
|---|---|
| 取引の条件に関する情報 | ・購入代金以外に発生するお金についての内容 ・契約解除についての内容(違約金など) ・管理委託先についての内容※マンションの場合 |
重要事項説明のより詳しい内容については、以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
押さえておきたい!不動産売買契約書の重要事項

不動産売買契約書には多くの条項が含まれますが、中でも特に注意して確認すべき重要な項目があります。
これらの項目を一つひとつ押さえることが、安心して取引を進めるための鍵となります。
ここでは、不動産売買契約書の記載されている重要事項について、分かりやすく解説していきます。
仲介や買取で契約する方はもちろん、個人売買を予定している方も、ぜひ内容を理解し、契約書を確認・作成する際に役立ててください。
売買物件の情報
まず必ず明記されているのが、売買対象となる物件の情報です。
土地であれば所在地、地番、地目、面積、建物であれば所在地、家屋番号、種類、構造、床面積などといった情報が記載されます。
これらの情報は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認することができます。
不動産売買契約書に記載された物件情報が、登記事項証明書の内容と完全に一致しているか必ず確認しましょう。
場合によっては、普段使っている住所と登記簿上の地番や家屋番号が異なるケースもあるため、注意深くチェックしてください。
売買代金や手付金、支払い条件
不動産売買契約書には、売買代金の総額をはじめとした、お金に関する重要な情報も記載されています。
具体的には、以下の情報を確認しましょう。
・契約時に買主から売主に支払われる「手付金」の額
・中間金の支払い額と期日(設定される場合)
・最終的に支払う「残代金」の額と支払い日
手付金とは、売買契約が成立した証として支払われる金銭で、一般的には売買代金の5%~10%程度が相場です。
もしこれらの金額や期日に曖昧な点があると、資金計画に狂いが生じるだけでなく、最悪の場合、契約不履行とみなされるリスクもあるため、間違いがないか必ず確認しましょう。
所有権移転と引き渡しの時期
不動産の所有権が法的に買主に移る「所有権移転日」と、実際に物件の鍵などが買主に渡され、買主が物件を使用できる状態になる「引き渡し日」は、契約書で正確に定める必要があります。
日本の不動産取引では、多くの場合、「同時履行の原則」が採用されています。
これは、買主による売買代金全額の支払いと、売主による所有権移転登記手続きと物件の引き渡しを、同じ日に行うことです。
これにより、「代金を支払ったのに、いつまで経っても物件が引き渡されない」「物件を引き渡したのに、代金が支払われない」といった一方だけが不利益を被るリスクを避けることができます。
不動産売買契約書を確認する際は、この同時履行が明確に定められているかを必ず確認しましょう。
契約解除に関する条項
不動産売買契約は一度締結すると法的な拘束力を持ちますが、特定の条件下では契約を解除できる場合があります。
その条件や手続き、ペナルティなどを定めているのが契約解除に関する条項です。
具体的には、以下のような条項が定められています。
・手付解除
契約の相手方が「契約の履行に着手するまで」であれば、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受領した手付金の倍額を買主に支払うことで、契約を一方的に解除できます。
・ローン特約による契約解除
買主が住宅ローンを利用する場合、万が一、金融機関の審査に通らなかった際に、買主がペナルティを負うことなく契約を無条件で解除することができます。
・契約違反による解除と違約金
売主または買主のどちらかに債務不履行があった場合、もう一方の当事者は契約を解除できます。
その際、契約違反をした側は相手方に対して違約金を支払わなくてはなりません。
違約金の額は、「売買代金の20%相当額」のように、あらかじめ契約書で定められているのが一般的です。
契約不適合責任
「契約不適合責任」とは、売買契約で決めた内容と違う不動産を引き渡してしまった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、購入した中古住宅に、契約時には説明のなかった雨漏りやシロアリ被害が見つかった、といったケース等が該当します。
このような契約不適合があった場合、買主は売主に対して、主に以下の権利を主張できます。
・履行の追完請求:不適合部分の修理や代替物の引き渡しなどを求める。
・代金減額請求:不適合の程度に応じて、売買代金の減額を求める。
・損害賠償請求:不適合によって被った損害の賠償を求める。
・契約解除:不適合が重大で、契約目的を達成できない場合に契約を解除する。
不動産売買契約書では、この契約不適合責任の範囲や責任を負う期間、免責事項などがどのように定められているか、必ず確認しましょう。
契約不適合責任についての詳しい内容については、以下の記事で解説しているのでこちらもご覧ください。
公租公課の分担(税金の精算)
不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税といった税金(公租公課)が課されます。
これらの税金は、その年の1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、年の途中で不動産の売買が行われた場合は、売主と買主で分担するのが一般的です。
通常は、物件の引き渡し日を基準に税額を日割り計算し、引き渡し日以降の分を買主が売主に支払う形で精算します。
契約書で、この精算の起算日や具体的な計算方法が明記されているかを確認しましょう。
反社会的勢力の排除に関する条項
不動産取引では、暴力団やその関係企業などの反社会的勢力を排除するため、取り組みが強化されています。
その一環として、不動産売買契約書には「反社会的勢力排除条項」が盛り込まれるのが一般的になっています。
この条項は、売主・買主の双方が反社会的勢力ではないこと、またその関係者ではないことを確約するものです。
万が一、相手方がこの条項に違反した場合、無条件で契約を解除できる旨が定められています。
契約書には、この条項が適切に盛り込まれているかを確認しましょう。
ここに注意!不動産売買契約書を確認する際のポイント

不動産売買契約書に記載された内容はすべて法的な効力を持つため、どの事項についても間違いがないか丁寧に確認することが大切です。
ここからは、不動産売買契約書を確認する際に特に注意したい2つの点を解説しますので、ぜひ契約書をチェックする際の参考にしてください。
ポイント1.数字に気をつける
契約金額や日付、面積などの数字は、思い込みや見落としが起きやすい部分のため、特に注意が必要です。
例えば、売買代金の場合、手付金、中間金、残代金の合計が、売買代金の総額と一致するかしっかりと確認しておきましょう。
また、固定資産税や都市計画税は、通常「引き渡し日」を基準として日割りで計算し、精算します。
さらに、特別な理由により手付解除や契約違反となった際の解除金についても、事前に合意した内容と相違がないか十分に確認しておきましょう。
ポイント2.「期日」の条件は適切か
金額だけでなく、支払期日や引き渡し時期などの「期日」が、無理のない条件になっているか確認することも重要です。
不動産の売買ではさまざまな点において期日が定められています。
ご自身の引っ越し予定や住宅ローンの手続きなども考慮し、余裕を持った日程であるか、スケジュールと照らし合わせてチェックしましょう。
また、ご自身の都合だけでなく相手方のスケジュールにも配慮して、双方が合意できる現実的な日程になっているかを確認しておくと、その後の取引がスムーズに進みます。
契約前に絶対確認!不動産売買契約のリスクと回避策

不動産売買契約には、慎重に進めても予期せぬリスクが潜んでいることがあります。
ここでは、実際に起こりうるトラブル事例を挙げながら、それらを未然に防ぐための具体的な回避策を解説します。
「こんなはずではなかった」という事態を避けるために、ぜひ参考にしてください。
契約書に記載された内容と違っていてトラブルになった
契約書の内容が曖昧であったり、重要な事項に関する不動産会社からの説明が不十分だったりしたために、トラブルに発展するケースも少なくありません。
このような場合、後から「そんな話は聞いていなかった」「説明と違う」といった問題が生じる恐れがあります。
例えば、買主側では「購入した土地に思ったような建物が建てられない建築制限があった」、売主側は、「買主から売買代金が期日通りに支払われない」といった事例が考えられます。
こうしたトラブルを回避するためには、契約書の一字一句を丁寧に確認することが基本です。
少しでも疑問に思う点や理解できない専門用語があれば、遠慮せずに不動産会社の担当者や相手方に質問し、納得できるまで説明を求めましょう。
また、口頭で受けた重要な説明はメモを取るなど、書面に残す習慣をつけるとより安心です。
契約解除できなかった・違約金が発生してしまった
手付解除が可能な期間や条件を誤解していたために、いざという時に解除できなかったというケースもあります。
また、住宅ローンの審査が通らなかった場合に適用される「ローン特約」の期日を過ぎてしまい、契約を白紙解除できず違約金が発生する、といったケースも考えられます。
このようなリスクを回避するには、以下の点を徹底しましょう。
・契約書を再確認し、解除の期日や条件、手続き方法を正確に理解する
・ご自身でスケジュール管理を徹底する
特にローン特約は買主を守るための重要な取り決めです。
特約の期限内に金融機関の審査結果が出るよう、申し込み手続きは速やかに進めましょう。
物件に瑕疵があった
不動産を購入した方が特に注意してほしいのが、瑕疵に関するトラブルです。
購入した物件に、契約時には気づかなかった瑕疵(不具合)が後から見つかるというのも、代表的なトラブルです。
瑕疵の例として、以下のようなものが挙げられます。
・シロアリ被害がある
・雨漏りがある
・建物の構造的な問題がある(外壁が剥がれているなど)
・土地の地中に障害物がある(地中埋設物)
・建築基準法に違反する建物が建っている
・接道の要件を満たしていない
・自殺や殺人事件の現場である
・近隣に暴力団事務所など嫌悪施設がある
これらのトラブルを回避するためには、契約不適合責任の範囲や責任を負う期間、免責事項などを契約書でしっかり確認することが不可欠です。
また売主は、売却の前にホームインスペクション(住宅診断)を実施し、物件の状態を客観的に把握しておくことで、後々のトラブルを減らし、安全に取引を進めやすくなります。
ホームインスペクションについては、以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。
不動産売買契約書を不備なく確認し、安心して取引を成功させよう

不動産の売買では大きな金額が動くため、万が一トラブルが生じた際の金銭的・精神的な負担はより一層大きくなることが予想されます。
取引相手への配慮はもちろん、ご自身の資産を守るためにも、トラブルを回避できる取引を行うことが大切です。
そして、後悔のない取引を行うためには、契約内容をお互いに明確にする「不動産売買契約書」の存在が重要です。
本記事で解説したポイントを改めて参考に、不動産売買契約書を不備のないよう十分に確認し、安心して取引を成功させましょう。


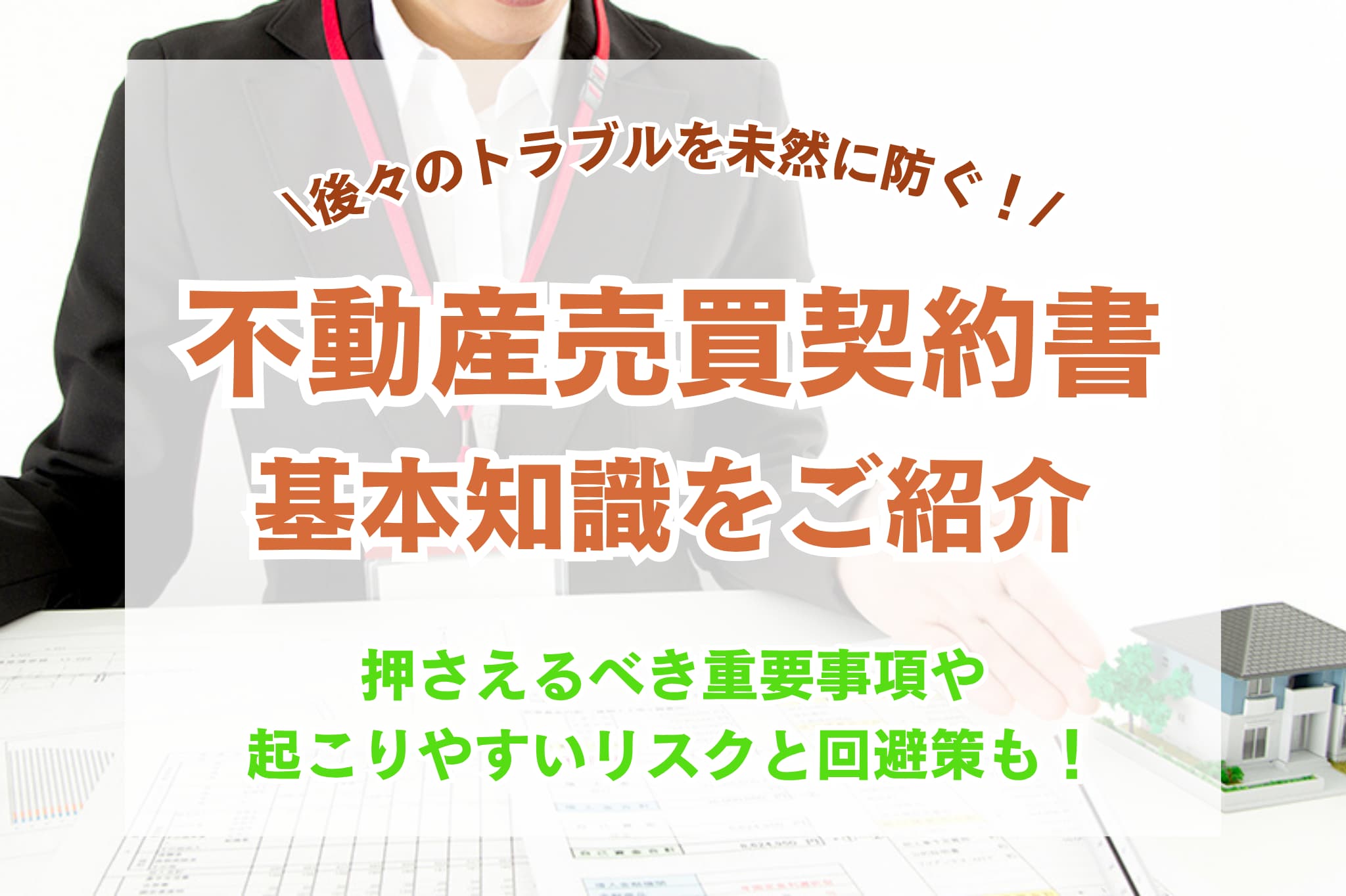

















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












