|
この記事でわかること ・共有持分の基本的な知識 |
相続などで突然不動産の「共有持分」を所有することになり、その扱いに困っている方は少なくありません。
自身の共有持分は、ほかの共有者の同意なしに売却することが可能です。
しかし、適切な方法を選択しない場合、思わぬトラブルが発生したり、適正な価格で売却できないリスクも存在します。
本記事では、共有持分の基本的な知識から、失敗せずに売却する方法、売却時に発生する費用、共有者間のトラブル解決策や対処法を解説します。
売却方法を誤るとのちにトラブルとなり、共有者間で関係性が悪化する恐れがあります。
注意点についてよく理解してから売却を進めていきましょう。
この記事の目次
不動産の共有持分とは?売却できるかをまずは確認!

不動産の「共有持分」とは、一つの不動産を複数人で共同所有している場合の、各所有者が持つ「所有権の割合」のことです。
そして、この複数人で所有している状態を「共有名義」と呼びます。
よくある誤解として、「2階部分が自分のもの」「土地の東側半分が自分のもの」といったように、不動産を物理的に分割した権利だと考える方がいますが、これは間違いです。
共有持分は、不動産全体に対して「何パーセントの権利を持っているか」という、目に見えない割合の権利です。
共有名義になる主なケースと持分割合の決まり方
共有名義となるのは、主に以下のようなケースです。
それぞれのケースで持分割合の決まり方も異なります。
・相続による共有
親の不動産を兄弟姉妹で相続する場合などです。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人(※)が法定相続分に基づいて共有持分を取得することが一般的です。
・夫婦や親子による共同購入
夫婦での支払いのもと住宅を購入したり、親子での支払いのもと二世帯住宅を購入したりするケースです。
この場合の持分割合は、通常、出資した金額の割合に応じて決まります。
このように、共有持分は一つの不動産に複数の所有者が絡むため、その利活用や処分には特有の難しさが伴います。
これが、共有持分がトラブルになりやすい本質的な理由でもあります。
|
※法定相続人とは? 法定相続人とは、民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人です。 配偶者は常に法定相続人となり、その他の血族は子→親→兄弟姉妹の順で相続人となります。 法定相続分は、これらの組み合わせによって、法律で割合が決められています。 出典:「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」-国税庁 |
自分の持分だけなら共有者の合意不要で売却できる
自分の共有持分は、ほかの共有者の合意がなくても自由に売却することが可能です。
日本の民法第206条では、所有者は自分の所有物を自由に処分する権利を持つと定められており、共有持分もこの「あなたの所有物」に該当するためです。
|
【参考】民法第206条 「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」 出典:民法-e-Gov法令検索 |
そのため、もしあなたが「ほかの共有者と話したくない」「売却に反対されている」といった状況でも、法的には単独で売却手続きを進めることが可能です。
しかし、不動産全体(建物や土地すべて)を売却するには、共有者全員の合意が必須となります。
共有持分ならではの注意点や知っておくべきことについては、次のセクションでさらに詳しく掘り下げていきます。
共有持分の売却の注意点と課題
前述の通り、自分の共有持分だけなら自由に売却できますが、不動産全体を一つの物件として市場で売却するには、共有者全員の同意が絶対に必要です。
これは、不動産全体の売却が民法第251条で定められた「変更行為」に該当するためです。
|
【参考】民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 出典:民法-e-Gov法令検索 |
つまり、共有者の一人でも売却に反対すれば、不動産全体を売却することが法的にできないということです。
あなたが「家全体を高く売りたい」と考えても、ほかの共有者が「売りたくない」と言えば、その道は閉ざされてしまいます。
多くの共有不動産トラブルは、この「自分の持分は手放したいが、ほかの共有者が全体の売却に同意してくれない」というジレンマから生じます。
さらに、共有持分を持つことには以下のような特有の課題も伴います。
・不動産利用・管理が制限される
・維持費や税金の負担でもめやすい
・権利関係が複雑化するリスクがある
・自身の売却自体が難しくなる可能性がある
これらの課題を解決し、スムーズな売却を実現するための具体的な方法は、次のセクションで詳しく解説していきます。
共有持分の売却方法4選を徹底比較

共有持分をスムーズに売却し現金化するには、主に以下の4つの方法があります。
・ほかの共有者に自分の持分を売却する
・共有者全員の合意を得て不動産をまるごと売却する
・共有持分を分筆してから売却する(土地のみ)
・自分の持分のみを専門の買取業者に売却する
それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの状況やほかの共有者との関係性によって最適な選択肢は異なるでしょう。
一つひとつを丁寧に比較し、あなたにとって最善の道を見つけていきましょう。
方法1.ほかの共有者に自分の持分を売却する
あなたが持つ共有持分を、ほかの共有者に直接売却する方法です。
これにより、あなたは共有関係から抜け出せ、買い取った共有者は持分割合を増やしたり、不動産を単独所有にしたりできます。
メリットとしては、不動産を身内で維持できるため、感情的な抵抗が少ない点や、第三者を介さない直接取引なので手続きを比較的シンプルに進められる点でしょう。
一方で、買い取る側に十分な資金力が必要となる点が課題です。
さらに、売却価格の交渉が親族間の個人的な感情と絡み合い、「安く譲ってほしい」と言われるなど、トラブルに発展しやすい傾向があります。
こうしたトラブルを避け、安心して売却を進めるためには、親しい間柄であっても、不動産鑑定士による適正な鑑定評価を受けることを強くおすすめします。
方法2.共有者全員の合意を得て不動産をまるごと売却する
共有者全員が売却に合意したうえで、一つの不動産として不動産会社に仲介を依頼し、市場で買主を探す方法です。
売却で得られた代金は、それぞれの持分割合に応じて分配するのが一般的でしょう。
例えば、4,500万円で家が売れた場合、兄弟3人が3分の1ずつの持分を持っていれば、それぞれ1,500万円ずつ受け取ることになります。
この方法のメリットは、市場価格で売却できるため手取り額が最も高くなる可能性が高い点です。
また、一般的な不動産売却と同じ流れで進むため、手続きも比較的シンプルでわかりやすいでしょう。
一方で、デメリットは、共有者全員の「売却したい」という意思と、売却価格や時期に関する合意が不可欠なことです。
一人でも反対者がいればこの方法は実現せず、多くの共有不動産トラブルがこの合意形成の難しさから生じます。
これが最大のハードルとなるでしょう。
なお、海外居住中や入院中などで売却手続きに立ち会えない場合でも、委任状を作成すれば代理人に手続きを依頼できます。
委任状の作成方法や代理人の選び方については、こちらの記事も参考にしてみてください。
方法3.共有持分を分筆してから売却する(土地のみ)
共有している土地を、あなたの持分割合に応じて複数に分割(分筆)し、単独名義に登記し直してから売却する方法です。
分筆できれば、その土地はあなたの意思だけで自由に売却できます。
この方法のメリットは、分筆によって共有関係から解放され、単独所有の土地となることです。
一方で、デメリットも存在します。
分筆後の土地は面積が縮小するため、資産価値が下がる恐れがあります。
また、分筆にはほかの共有者の同意が必要なケースが多いです。
トラブル防止のため、分筆を検討する際は、事前に不動産会社や土地家屋調査士に相談し、メリット・デメリット、そしてほかの共有者の同意が必要かどうか把握することをおすすめします。
土地家屋調査士については、以下の記事で詳しく紹介しているのでこちらもご覧ください。
方法4.自分の持分のみを専門の買取業者に売却する
あなたの共有持分のみを、専門の買取業者に直接売却する方法です。
この方法の最大のメリットは、ほかの共有者の同意が一切不要な点です。
あなたの判断だけで売却を完結でき、数週間での現金化も可能なため、非常にスピーディーに共有関係から解放されます。
加えて、ほかの共有者との交渉や接触が不要となり、精神的な負担も少ないでしょう。
また、買取業者が直接買主となるため、仲介手数料がかからない場合も多いです。
一方、デメリットは、売却価格が市場価格より低くなることです。
これは、買取業者が複雑な権利関係の解消にかかる手間や費用、さらには将来的な売却や活用に伴うリスクを引き受けるためです。
買取業者に依頼する際は、悪質な業者に注意し、信頼できる業者選びが重要です。
共有持分の買取を取り扱っている業者を効率良く探すには、不動産一括査定サービスのご利用がおすすめです。
当サイトが提供する「イエイ」では、1700社以上の優良不動産会社との取引実績があります。
共有持分の売却にあたって、買取業者をお探しの方は、ぜひ活用してみてくださいね。
共有持分の売却にかかる費用と税金

共有持分の売却時には、さまざまな費用や税金がかかります。
主な諸費用として、以下のものがあります。
・不動産会社へ払う仲介手数料
・登記費用と登録免許税
・譲渡所得税
・印紙税
それぞれの内容や具体的に支払う金額の目安についてご紹介します。
不動産会社へ払う仲介手数料
不動産会社に売却を依頼し、売買契約が成立した場合、成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
この仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。
| 売却価格 | 必要となる仲介手数料 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税(10%) |
| 200万円~400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税(10%) |
| 400万円以上 | 売却価格×3%+6万円+消費税(10%) |
例えば、売却価格が1,500万円だった場合の仲介手数料の上限は、以下の計算で求められます。
|
1,500万円は400万円以上なので、「売却価格×3%+6万円+消費税(10%)」で計算する。 1,500万円×3%=45万円 |
※自分の共有持分を専門の買取業者に直接売却する場合や、ほかの共有者が直接買い取る場合など、不動産会社が「仲介」に入らない取引では、仲介手数料は発生しません。
登記費用と登録免許税
共有持分の不動産を売却する際には、以下の登記費用と登録免許税がかかります。
・登記費用(司法書士報酬)
不動産の売却に伴う所有権移転登記や、住宅ローンの完済による抵当権抹消登記などの手続きは、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
この際に支払う報酬が司法書士報酬であり、「登記費用」として扱われることが多いです。
目安として、所有権移転登記や抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の報酬は、一般的に数万円から10万円程度となることが多いでしょう。
・登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記手続きを行う際に国に納める税金です。
共有持分の売却に伴う所有権移転登記、または住宅ローンの残債があり、その担保となっている抵当権を抹消する登記の際に課税されます。
例えば、抵当権抹消登記の場合、不動産1つにつき1,000円の登録免許税がかかります。
また、これらの費用については以下の記事で詳しく解説しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
譲渡所得税
不動産の売却時に利益(譲渡所得)が生じた場合、その利益に対して譲渡所得税が課されます。
この税金は、所得税と住民税を合わせたものです。
譲渡所得税を計算するには、最初に「課税譲渡所得金額」を算出する必要があります。
計算式は以下の通りです。

課税譲渡所得金額が算出できたら、次に適用される税率を乗じて譲渡所得税額を算出します。
この税率は、不動産の所有期間によって以下のように異なります。
売却した年の1月1日時点での保有期間が基準となります。
| 不動産の保有期間(売却した年の1月1日時点) | 税率の内訳 | 合計税率 |
|---|---|---|
| 5年以上(長期譲渡所得) | 所得税15.315%+住民税5% | 20.315% |
| 5年以内(短期譲渡所得) | 所得税30.63%+住民税9% | 39.63% |
また、2037年までは、上記の税率に加えて復興特別所得税が課されます。
これは、所得税額の2.1%に相当する金額で、所得税と合わせて納税することになります。
特別控除とは?
課税譲渡所得金額を算出する際の計算式にある「特別控除額」は、特定の条件を満たすことで適用される優遇措置です。
ここでは、代表的な2種類の控除についてご紹介します。
・居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除
ご自身が住んでいた家(居住用財産)を売却し、一定の要件を満たす場合に、課税譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できます。
・被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の特別控除
相続した空き家を売却し、一定の要件を満たす場合に、課税譲渡所得金額から最大3,000万円を控除できます。
これらの控除の詳しい内容や条件については、以下の記事で紹介しているので、こちらもご参考ください。
印紙税
不動産売買契約書の作成時には、印紙税がかかります。
印紙税額は売却価格によって異なり、契約書に収入印紙を貼り付ける形で納税します。
具体的な印紙税額は以下の通りです。
なお、2027年3月31日までの間に作成される契約書については、印紙税の軽減措置が適用されています。(表の右列)
共有持分の売却相場

「共有持分」の売却を検討しているなら、一番気になるのは「いくらで売れるのか」ですよね。
共有持分の売却価格は、売却相手によっても相場が異なるのが実情です。
ここからは、「ほかの共有者」と「専門の買取業者」に共有持分を売却した場合の相場がどれくらい変わるのかをご紹介します。
ほかの共有者が買い取る場合
不動産を共有しているほかの人があなたの持分を買い取る場合、不動産全体の市場価格にあなたの持分割合をかけた金額が目安となります。
例えば、市場価格が3,000万円の不動産で、あなたが3分の1の持分を持っている場合、1,000万円(3,000万円×1/3)程度の金額で売却できる可能性があります。
その理由として、ほかの共有者があなたの持分を買い取ることで、不動産を単独所有にしたり、自身の持分割合を増やしてより自由に活用したりできるようになるからです。
そのため、ほかの共有者に売却する場合は、比較的高値で売れることが期待できます。
専門の買取業者が買い取る場合
専門の買取業者にあなたの持分を売却する場合、不動産全体の市場価格にあなたの持分割合をかけた金額の、さらに3割から5割程度の価格が目安となることが多いです。
買取業者は、あなたの持分を買い取った後、ほかの共有者との交渉や法的な手続きを通じて、最終的に不動産全体を収益化しようとします。
そのため、これらの手間や費用、リスクを負うため、その分を差し引いた価格で買い取ることになります。
つまり、専門の買取業者に売却する場合は、前述したほかの共有者が買い取る場合と比較して、売却価格が安くなる傾向があります。
共有持分の売却価格は査定で決まる
前述の通り、共有持分の売却相場は、売却相手や不動産の状態によって大きく変動します。
買取業者だけでなく、ほかの共有者に売却する場合であっても、適正な価格を知ることは非常に重要です。
最終的な売却価格は、不動産の専門家による査定で、物件の立地や状態、権利関係などの点に注目して、価格が算出されます。
ご自身の共有持分がいくらで売れるのか、具体的な査定額を知りたい方は、まず不動産一括査定サービスをご利用ください。
当社が提供する「イエイ」でも、共有持分の査定を依頼することは可能ですので、ぜひ活用してみてくださいね。
共有持分を売却する際の必要書類

共有持分の売却手続きを進めるにあたって、以下のような書類が必要になります。
スムーズな売却のためにも、早めに準備を始めましょう。
| 書類名 | 概要 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 権利証(登記識別情報) | 不動産の所有者であることを証明する、最も重要な書類です。 | ・紛失しても再発行はできません。 ・紛失時は、司法書士に相談し、別の方法で本人確認手続きを行う必要があります。 |
| 土地測量図・境界確認書 | 売却する土地の面積や隣地との境界線を明確にする書類です。 | ・土地が含まれる場合に必要です。 ・作成されていない場合は、土地家屋調査士に測量と書類の作成を依頼する必要があります。 |
| 身分証明書や住民票 | 売主本人であることを証明する書類です(運転免許証、マイナンバーカードなど)。 | ・登記上の住所と現住所が異なる場合は、3ヶ月以内に発行された現住所の住民票が必要です。 ・共有者全員分の身分証明書と住民票が必要になることがあります。 |
| 印鑑登録証明書・実印 | 売買契約書に押す実印と、その印影が本物であることを証明する書類です。 | ・3ヶ月以内に発行されたものが有効です。 ・共有者全員分の印鑑登録証明書と実印が必要になることがあります。 |
売却する状況によっては、上記以外にも書類が必要となる場合があります。
詳しくは不動産会社などの専門家にご確認ください。
共有持分の売却でありがちなトラブルと解決策・対処法

ここでは、共有持分の売却時に起こりがちなトラブルと、それぞれの効果的な解決策や対処法について解説します。
もしもの時のためにも知っておき、安心して共有持分の売却を進めましょう。
よくあるトラブルと解決策
共有持分を売却する過程で、多くの方が遭遇する具体的な問題点が存在します。
ここでは、それらの代表的なトラブルを回避する方法や、万が一発生した場合に円滑に対応するための対策を掘り下げていきます。
1.ほかの共有者を知らない・連絡が取れない
相続登記がされないまま相続が続くと、共有者の数が増え、中には連絡先が分からない、あるいは音信不通の共有者がいるケースがあります。
このようなケースの場合、全員の同意が必要な不動産全体の売却はもちろん、自身の持分を売却する際も、共有者を把握できないと手続きが難航する恐れがあります。
【解決策】
ほかの共有者を知らなかったり、連絡が取れなかったりした場合は、以下のような解決策を講じると良いでしょう。
・司法書士に相談する
共有者の把握が難しい場合、司法書士に依頼することで、不動産の権利関係を調査し、共有者を特定することが可能です。
依頼する際は、必ず不動産や共有持分の売却に強い司法書士を選ぶようにしましょう。
・不在者財産管理人を選任する
共有者が行方不明の場合、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任し、その管理人と交渉を進める方法があります。
不在者財産管理人とは、行方不明の共有者の財産を管理するため、家庭裁判所によって選任される人物です。
この管理人によって、不在者の共有持分を含めた不動産の手続きを進めることが可能になります。
・相続時に共有名義を避ける
相続が発生した際に、不動産を共有名義にせず、遺産分割協議で「単独所有」もしくは「換価分割」を検討しましょう。
単独所有とは、一つの不動産を一人だけが所有している状態を指します。こうすることで、その不動産を自由に売却したり、活用したりできるようになります。
一方、換価分割とは、共有している不動産を売却し、その売却代金を共有者間で持分割合に応じて分ける方法です。
これにより、不動産を物理的に分けることなく、金銭で公平に分配することが可能になります。
2.意見の食い違いから共有者間の関係性が悪くなる
売却の合意や売却価格、時期などを巡って共有者同士の意見が食い違うと、関係性が悪くなるケースがよくあります。
たとえ親しい間柄であっても、金銭が絡むと感情的な対立に発展しやすい傾向があります。
また、自分の共有持分だけ売却する際に、ほかの共有者に何も報告をしないまま進めると、後々大きな溝ができてしまう恐れもあるでしょう。
【解決策】
共有持分の売却により共有者間の関係性が悪化した際は、以下のような解決策を講じると良いでしょう。
・売却価格で揉める場合は不動産鑑定士による鑑定を活用する
不動産には「定価」がないため、売却価格で意見が割れた際は、国家資格を持つ不動産鑑定士に適正な評価額を算出してもらうのが有効です。
公平な第三者の評価であれば、納得感を得やすいでしょう。
・合意が得られない場合は共有物分割請求を行う
共有者間の話し合いがどうしてもまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てると良いでしょう。
共有物分割請求とは、共有者が不動産の共有状態を解消するためにほかの共有者に対して、裁判所を通じて分割を求める法的な手続きです。
この請求が認められると、不動産が売却されたり、特定の共有者の単独所有になったりする形で、共有関係が解消されます。
ただし、この方法は弁護士費用や時間がかかります。
また、関係性が完全に敵対的になるリスクも伴うため、こうした点も理解したうえで検討しましょう。
・共有持分のみであっても勝手に売却しない
自分の持分は同意不要で売却できますが、後々の関係性悪化やトラブルを避けるためにも、ほかの共有者に事前に相談し、理解を得る努力をすることが賢明です。
特に、今後も良好な関係性を築き続けたいのであれば、必ず相談するようにしましょう。
3.売却価格が低いと贈与税を課される可能性がある
親しい親族間で共有持分を売却する際、「安く譲りたい」「無償で手放したい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、相場から著しく低い価格で売却したり、無償で譲渡したりすると、税務署から「贈与」とみなされ、受け取った側(買主)に贈与税が課されてしまう可能性があります。
【解決策】
・適正価格での売却を徹底する
親族間への売却であっても、不動産会社や不動産鑑定士による適正な価格で売却することが重要です。
適正な価格を提示してもらうことで、税務署に「これは適正な売買です」と証明することができます。
これにより、贈与とみなされるリスクを回避できます。
特定の状況下で起こりやすいトラブルと対処法
共有持分の売却においては、一般的な問題に加え、特定の状況下で発生しやすいトラブルも存在します。
ここでは、離婚や共有者による予期せぬ売却など、具体的な場面で直面しがちな問題とその対処法を解説します。
1.離婚時の共有名義不動産の売却トラブル
離婚に伴い、夫婦共有名義の不動産を売却したいと考えるケースは多いでしょう。
しかし、財産分与の対象となるため、安易な売却はトラブルの原因になります。
特に、住宅ローンが残っている場合は、名義変更や売却が複雑になる可能性があります。
【対処法】
離婚時の共有名義不動産の売却トラブルに対しては、以下の対処法を検討しましょう。
・財産分与の協議で不動産の扱いを決定する
まず離婚を成立させ、財産分与の協議の中で不動産を「売却するのか」「どちらかが住み続けるのか」など、今後の扱いを明確に決めましょう。
この決定が、その後の手続きの出発点となります。
・住宅ローンが残る場合は金融機関に相談する
住宅ローンが残っている場合は、金融機関に相談し、以下の行動を検討しましょう。
・一方が単独名義でローンを借り換える
・住み続ける側が、相手の持分相当額を代償金として支払う
・不動産全体を売却し、ローンを完済した上で残った代金を分ける
なお、住宅ローンは完済するまで原則として名義変更ができない点に注意が必要です。
2.共有者が勝手に持分を売却したトラブル
ほかの共有者が、あなたの知らない間に自身の持分を専門の買取業者などの第三者に売却してしまうケースがあります。
これにより、見知らぬ相手が新たな共有者となるため、今後の不動産の管理や売却がさらに難しくなる可能性があります。
【対処法】
共有者が勝手に持分を売却するといったトラブルを避けるには、以下の行動を検討しましょう。
・売却された持分を自分で買い取ることを検討する
不動産を共有したままにしたい場合、売却された持分をあなたが買い取り、新しい共有者となることを避ける選択肢があります。
・自分の共有持分を売却する
活用しない不動産であれば、あなた自身の持分も不動産会社などに売却し、共有関係から完全に抜け出すことも可能です。
・弁護士と連携している不動産買取業者に相談する
新たな共有者が強引な交渉をしてくるなど問題が生じた場合、弁護士と連携している買取業者に相談し、専門的な立場から対処してもらうのも一つの手です。
共有持分の売却は不動産会社への相談から始めよう

名義人が複数人いる共有持分の不動産では、ケースによって最適な売却方法が異なります。
ほかの共有者に売却する方法や、ほかの共有者の合意を得て不動産をまるごと売却する方法、不動産会社に買取してもらう方法などがあるでしょう。
共有持分の売却は、一般的な単独名義の売却よりも複雑です。
そのため、共有者間のトラブルに発展しないよう、慎重に進める必要があります。
まずは、不動産一括査定の「イエイ」で、複数の不動産会社から無料査定を始めてみませんか?
売却価格だけでなく、相続に関する疑問点など、あなたの状況に合った相談しやすい実績のある業者を見極めることができるでしょう。
不動産の売却をご検討なら、独自の基準に基づいた安心と信頼の「イエイ」まで、ぜひご依頼ください。










 出典:
出典:
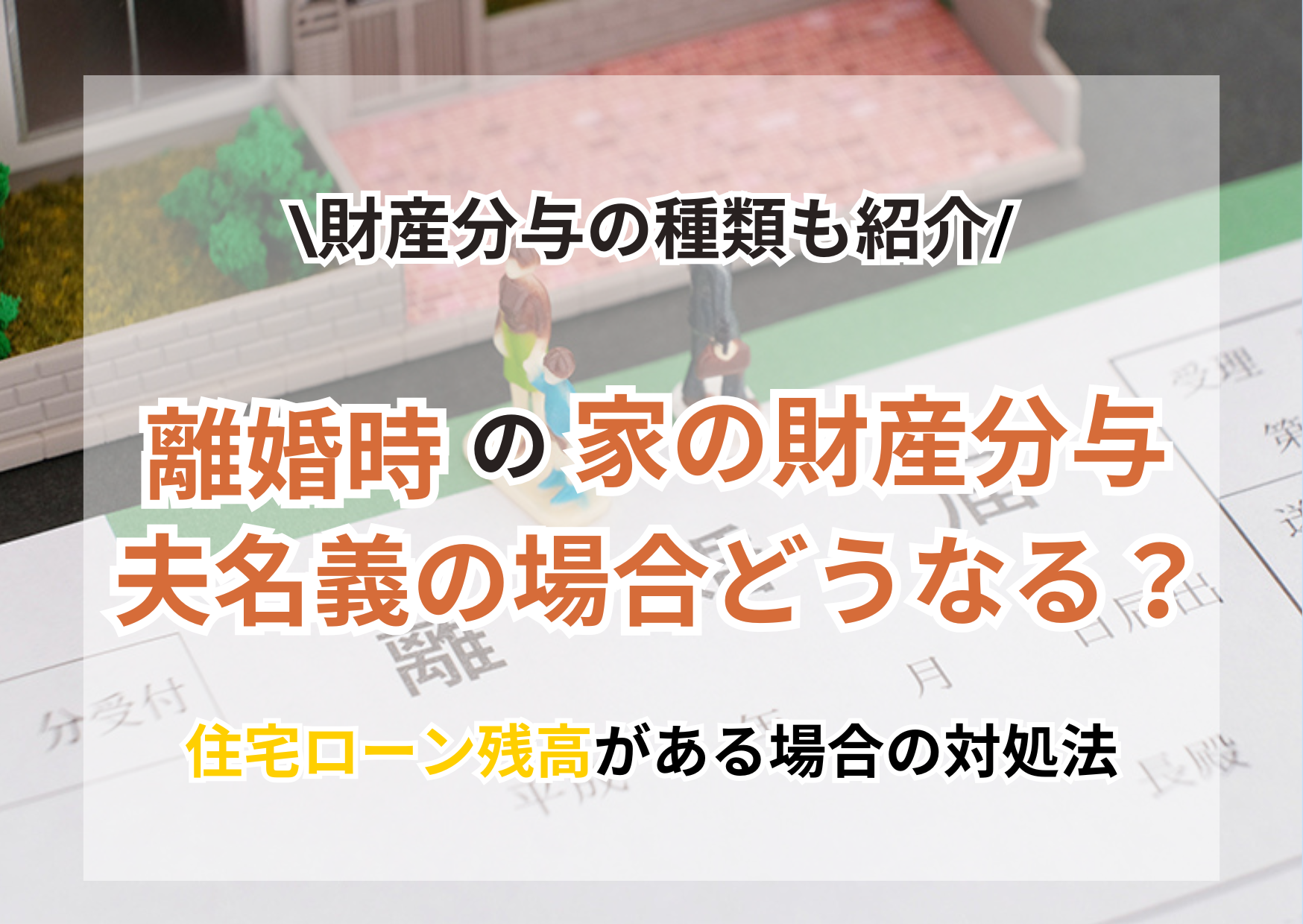












 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












