この記事で分かること
|
・地上権とは民法に定められた非常に強力な権利のこと |
親から土地を相続し、その活用方法を検討し始めた途端、不動産会社から「地上権を設定してはどうか」と言われ、聞き慣れない言葉に戸惑っていませんか?
「地上権とは何なのか?」「借地権や賃借権とはどう違うのか?」
こうした専門用語は、土地活用のスムーズなスタートを妨げる障害のように感じるかもしれません。
しかし、地上権は、不動産を売買するうえで重要なポイントの一つです。
この記事では、不動産の専門家でなくても「地上権」の全体像を深く理解できるよう、基礎からわかりやすく解説します。
読み終える頃には、あなたの土地に地上権を設定すべきか、あるいは設定された土地をどう活用すべきか、その判断材料が手に入っているはずです。
この記事の目次
地上権とは?「物を所有する」ための強力な権利

地上権とは、他人の土地の上に、工作物や竹木を「所有する」ための権利として、民法に定められた非常に強力な権利です。
分かりやすく言うと、あなたがAさんの土地を借りて家を建てる場合、通常の賃貸借契約では「土地を借りる権利」しかありません。
しかし、地上権を設定すれば、その土地の上に建てた家を「自分のものとして所有し、登記する」ことができるようになります。
この権利は非常に強力で、土地所有者が変わったとしても、地上権はそのまま効力を持ち続けます。
これが、一般的な賃貸借契約と決定的に違う点です。
地上権を知る上で知っておきたい借地権とは?

地上権を理解するには、まず「借地権」について知っておくことが大切です。
借地権とは、他人が所有する土地を借りて、その上に建物を建てたり利用したりするための権利を指します。
この借地権には「地上権」と「賃借権」の2種類があり、両者をひとまとめにした呼び方が「借地権」です。
そのため、「借地権=地上権」と誤解してしまうケースも少なくありません。
以下では、両者の特徴や相違点について整理していきます。
地上権と賃借権の違いを比較

土地を借りて建物を建てるといった目的で使われる権利には、地上権のほかに「賃借権」があります。
この2つは混同されがちですが、その性質は全く異なります。
「賃借権」とは、「賃借人が土地を使用して収益できる権利」のことで、賃貸借契約に基づいて、賃料を支払ったうえで第三者の土地を使用する権利です。
「賃借権」と「地上権」の最も大きな違いは、「登記」と「第三者への対抗力」です。
|
項目 |
地上権 |
貸借権 |
|---|---|---|
|
法的根拠と権利 |
民法(物権) |
民法(債権) |
|
登記 |
第三者に対抗するには登記が必要 |
地主に登記義務はない |
|
対抗力 |
非常に強い |
弱い |
|
地代 |
支払い義務はない(契約による) |
支払い義務がある |
|
地上権に設定できる |
設定できない |
|
|
売買・相続 |
自由に売買・相続が可能 |
土地所有者の承諾が必要 |
なぜ地上権が特別なのか?
上の表にある通り、地上権は「物権」に分類される点が最大の特徴です。
・物権(地上権):物を直接支配する権利。土地所有者の意思に関係なく、誰に対してもその権利を主張できます。
・債権(借地権・賃借権):特定の人(土地所有者)に特定の行為を要求する権利。
地上権は単独で登記できるため、土地の所有者が変わっても、新しい所有者に対して「私はこの土地に建物を建てる権利を持っている」と堂々と主張(対抗)できます。
賃借権は、登記ができない(あるいは通常行わない)ため、土地が売買された場合、新しい土地所有者から立ち退きを求められるリスクが地上権よりも高くなります。
地上権設定登記の仕方

ここからは、地上権設定登記の仕方についてご紹介していきます。
登記は住んでいる地域の法務局(登記所)で行うことができます。
下記でご紹介する必要な書類を準備して登記を行いましょう。
また、申請が登記簿に反映されるまでの時間は1~2週間です。
自分が土地の所有者で地上権設定契約を結んだ場合は、契約後すみやかに登記申請を行いましょう。
地上権設定登記に必要な書類一覧
地上権を設定して登記する際には、いくつかの書類を事前に準備する必要があります。
主なものを以下に整理しました。
|
必要書類 |
詳細 |
|---|---|
|
登記申請書 |
地上権の設定登記を申請するために、法務局へ提出する基本書類。 |
|
登記識別情報または権利証 |
登記済みの不動産について、所有権や権利の存在を証明するための書類。 |
|
登記原因証明情報 |
・地上権を設定する契約に基づき作成される資料。 ・契約書そのものを添付する場合と、契約内容を要約した報告書形式を提出する場合がある(法務局でも取得可能) |
|
固定資産評価証明書 |
・登録免許税を算出する際に必要となる証明書。 ・申請人自身で市区町村役場から取得する。 |
|
印鑑証明書 |
・地上権を設定する側(登記義務者)の印鑑が本人のものであることを確認する書類。 ・発行から3か月以内のものを使用。 |
|
地上権設定契約書 |
地上権者と土地所有者(地上権設定者)との間で交わした契約内容を示す書類。 |
|
代理権限証書 |
・本人に代わって代理人が登記申請を行う場合に必要。 ・司法書士へ依頼するケースでは、司法書士が用意してくれる。 |
地上権設定登記にかかる費用
登記にかかる費用は「登録免許税」と司法書士に依頼する場合は「司法書士報酬」も必要です。
司法書士に依頼した場合は司法書士報酬として3~5万程度の費用がかかります。
また、登録免許税は登記の理由によって税率が異なります。
詳しくは下記でご紹介します。
登記の理由ごとの税率
①設定・転貸の登記
地上権の登記は「はじめて地上権を設定したとき」だけでなく、その地上権を他の人に貸す(=転貸)ときにも登記できます。
このときの税率はどちらも同じで
| 「固定資産税評価額×1%」 |
②共有している土地を分けるとき
兄弟や親子など、複数人で地上権を共有している場合に、共有状態を解消して持分を整理する手続きをすると、登記の内容が変わります。
この場合の登録免許税は
| 「固定資産税評価額 × 0.2%」 |
③相続や会社の合併で地上権を引き続くとき
土地を持つ人が亡くなって相続したり、会社が合併して地上権を引き継ぐときには、登記を変更する必要があります。
この場合の登録免許税は
| 「固定資産税評価額 × 0.2%」 |
④売買や贈与などで地上権を移すとき
地上権を売買や贈与によって他の人に移す場合にも、登記変更が必要です。
この場合の登録免許税は
| 「固定資産税評価額 × 2%」 |
地上権のメリット・デメリット

地上権は、土地を所有する人だけでなく、その土地を借りて利用する人の立場にも影響を及ぼします。
そこでここでは、地上権を設定することで得られる利点と、注意すべき不利な点について分かりやすく整理していきます。
土地所有者から見たメリット・デメリット
|
メリット |
・一度設定すると長期間安定した地代収入が得られる。 ・土地に地上権を設定することで、相続税評価額を下げられるケースがある。 |
|---|---|
|
デメリット |
・地上権は非常に強力な権利のため、一度設定すると土地の利用が著しく制限される。 ・簡単に解約できないため、土地を自由に使いたい場合に大きな制約となる。 ・土地の売買や活用が難しくなり、売却価格が低くなる可能性がある。 |
地上権者(土地を借りる側)から見たメリット・デメリット
|
メリット |
・土地所有者が変わっても、地上権はそのまま維持されるため、安心して長期的な土地利用ができる。 ・地上権は自由に売買や相続が可能であり、権利としての資産価値が高い。 |
|---|---|
|
デメリット |
・賃借権と比較して、設定登記の手続きが複雑で費用がかかることがある。 ・土地所有者の承諾なく権利を売却できるため、土地所有者との関係が悪化する可能性がある。 |
地上権が設定されるケース
地上権にはいくつかの種類がありますが、代表的なのは 「区分地上権」 と 「法定地上権」 の二つです。
名称は似ていますが、成立する経緯や利用されるシーンが異なるため、それぞれの特徴を次に分かりやすく説明していきます。
区分地上権とは?

「ここからここまで」と範囲を限定して設定する地上権の事を「区分地上権」といいます。
通常であれば、地上権つきの不動産は、敷地内であれば地下や上空、地上を範囲の限定なく自由に使うことができます。
しかし、「区分地上権」がついていると、地下や上空の一部に「何メートルから何メートルまで」と設定がされており、範囲内のみの使用に限定されるものです。
区分地上権が設定されるケース
| ・他人や所有する土地の地下にトンネルを掘る場合※ ・上空に高架道路を造ったりする場合 ・太陽光発電パネル |
※地下鉄が通る区間や高圧送電線が通る空中に地上権を設定し、土地所有者の利用を制限せずにインフラ整備を進めることができます。
法定地上権とは?

元々一人の人が所有していた土地と建物において、抵当権の利用により、持ち主が分かれた場合に発生する地上権のことを「法定地上権」といいます。
例えば、最初に物件を購入した人が、ローンの返済ができなくなり、金融機関によって競売にかけられ、新たにその物件を購入した人が「法定地上権」を得ることになります。
この法定地上権を設定した建物は、地代の支払いをきちんと行い、住環境を整え、条件を満たしているのであれば、ほとんどの場合永久に使用が可能です。
法定地上権が成立する条件
| ・抵当権を設定した当時に既に土地の上に建物が存在していたこと ・抵当権を設定した当時に、土地と建物の所有者が同じであったこと ・土地か建物のどちらか1つか、2つともに抵当権が設定されていること ・土地か建物のいずれかが競売にかけられて、それぞれの所有者が別々になっていること |
地上権が設定された土地を相続するときの注意点

相続した土地にすでに地上権が付いている場合、その扱いには注意が必要です。
主な確認事項は以下のとおりです。
|
土地の利用制限 |
地上権が設定された部分については、所有者であっても自由に利用したり、別の目的で貸し出したりすることは基本的にできません。 |
|---|---|
|
売却の難しさ |
地上権付きの不動産は買い手から敬遠されやすく、市場での取引が難航したり、通常より低い価格でしか売却できないケースが多く見られます。 |
|
相続税評価 |
地上権がある土地は、その分だけ土地の評価額が下がるため、相続税評価額も低めに算定されるのが一般的です。 |
なお、相続後に土地を有効活用したい場合には、地上権者と条件変更や利用方法について協議する余地があります。
ただし、地上権は非常に強い権利であるため、交渉を進める際には弁護士や司法書士など専門家のサポートを受けるのが安心です。
地上権について相談するなら?専門家と相談のポイント

地上権に関して、不動産会社、弁護士、司法書士、税理士など、相談すべき専門家は多岐にわたります。あなたの目的によって相談先を選びましょう。
・不動産会社: 土地の売買や活用方法について広く相談したい場合。
・弁護士・司法書士: 地上権の契約書作成や、地上権者とのトラブル解決を相談したい場合。
・税理士: 相続税や固定資産税など、税務上の問題について相談したい場合。
相談に行く際は、以下の情報を事前に準備しておくとスムーズです。
・土地の登記簿謄本や権利証
・地上権設定契約書(もしあれば)
・固定資産税の納税通知書など、土地に関する書類一式
地上権に関するよくある質問

地上権は専門的な制度のため、実際に取引や相続に関わる際に多くの疑問が生まれます。
ここでは、利用者から特に質問の多いテーマを取り上げ、基本的な考え方を整理しました。
理解の手助けとしてご覧ください。
【地上権に関するよくある質問】
・地上権を登記しなかった場合、どんな問題が起きますか?
・地上権は相続の対象となりますか?
・地上権と抵当権はどちらが優先されますか?
Q:地上権を登記しなかった場合、どんな問題が起きますか?
A:地上権は登記をして初めて、第三者に対して効力を主張できます。
もし土地所有者がその土地を他人に売却した場合、登記を行っていないと、新しい所有者に対して地上権を主張できなくなる可能性があります。
そのため、地上権の設定契約を締結したら、速やかに登記手続きを済ませることが重要です。
登記を忘れると、権利を守るための法的な優位性が失われることもあるため注意が必要です。
Q:地上権は相続の対象になりますか?
A:地上権は相続の対象となります。
地上権は土地を利用するための大切な権利であり、財産の一つと考えられます。
そのため、持ち主が亡くなった場合には、土地や建物と同じように相続の対象となります。
例えば、親が地上権をもっていて亡くなったときには、その子供が地上権を引き継ぎます。
ただし、地上権を相続する際には相続税がかかることがあるので、注意が必要です。
相続税は、基礎控除額があり、
| 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) |
までの財産には税金はかかりません。
Q:地上権と抵当権はどちらが優先されますか?
A:どちらの権利が先に設定されたかで結果が変わります。
土地に「地上権」と「抵当権」が両方ある場合、先に設定された権利が優先されます。
|
先に設定された権利 |
後から設定された権利の影響 |
|---|---|
|
地上権が先の場合 |
土地が競売にかけられても、地上権者はそのまま土地を使い続けられる。 |
|
抵当権が先の場合 |
土地が競売にかけられると、後から設定された地上権は消えてしまう可能性がある |
まとめると
地上権 → 抵当権 の順に設定された場合:競売されても地上権は残る。
抵当権 → 地上権 の順に設定された場合:競売されると地上権は消える可能性が高い。
つまり、「どちらを先に設定したか」がとても重要になるのです。
まとめ ❘ 地上権の理解が土地活用の第一歩

この記事では、地上権の基礎から、借地権・賃借権との違い、そして相続した際の注意点までを解説しました。
・地上権は、物を「所有する」ための強力な「物権」
・借地権や賃借権と異なり、単独で登記が可能で、第三者への対抗力が強い。
・相続した土地に地上権が設定されていたら、利用や売却に制限があることを理解し、専門家に相談する。
複雑で難しく感じるかもしれませんが、地上権について正しく理解することは、大切な資産である土地をどう活かすか、そして家族の未来をどう守るかを決める上で不可欠な第一歩です。
不動産会社からすすめられた地上権設定が本当にあなたの土地活用に最適なのか、ご自身で判断できるよう、この記事がその手助けになれば幸いです。
もし具体的な土地活用のアイデアが見つかったら、次は不動産会社や信頼できる弁護士・税理士に相談して、一歩踏み出してみましょう。


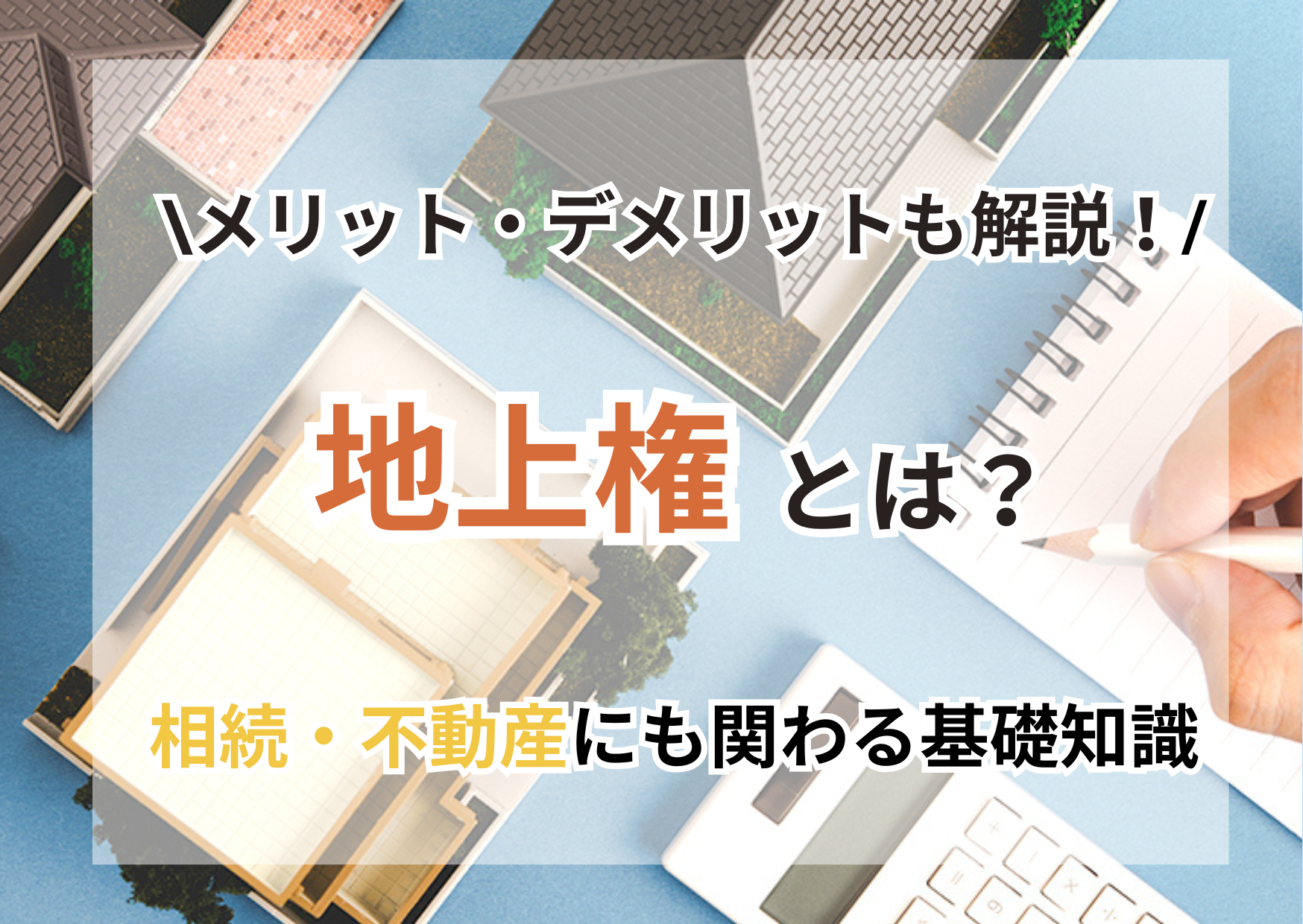














 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












