|
この記事でわかること ・贈与税の計算方法 |
「将来の相続に備え、自分のお金を子どもや孫に渡したい」「今住んでいる家を、子どもに譲りたい」
このように、ご自身の将来を見据え、大切なご家族のために生前贈与の準備を始めようとお考えではないでしょうか。
しかし、財産を贈与すると、受け取ったお子さんやお孫さんに「贈与税」がかかるケースがあります。
せっかくの想いを込めた贈与で、ご家族に余計な負担はかけたくないですよね。
そこでこの記事では、贈与税の計算方法から、具体的なケース別の計算シミュレーション、そして贈与税を少しでも節約するための方法まで、専門的な知識がない方にもわかりやすく解説します。
さらに、贈与額を入力するだけで税額の目安がすぐにわかる「贈与税計算シミュレーター」もご用意しました。
ぜひご家族の方とも一緒に本記事を読み進め、あなたにとって最善の贈与方法を見つけていきましょう。
この記事の目次
贈与税とは?
贈与税とは、個人から現金や不動産、株式といった財産を無償で受け取ったときにかかる税金です。
この税金は、財産を渡す側(贈与者)ではなく、受け取る側(受贈者)に納税の義務があるのが大きな特徴です。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があり、どちらを選択するかによって税金の計算方法が大きく変わります。
それぞれの仕組みを見ていきましょう。
暦年課税

暦年課税とは、受贈者1人あたりが1年間に贈与された財産の合計額に対して贈与税が課税される制度です。
暦年課税には年間110万円の「基礎控除(非課税枠)」が設けられており、贈与額の合計がこの範囲内であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
例えば、1年間で父から200万円の贈与を受けた場合は、基礎控除である110万円を超えるため、超えた分の90万円に対して贈与税が課税されます。
一方、1年間で父から100万円の財産を受けた場合は、基礎控除の110万円を超えないため、贈与税は課税されません。
また、暦年課税の税率は、誰から贈与を受けたかによって「一般贈与」と「特例贈与」の2種類に分かれます。
それぞれの違いについては、以下の通りです。
・一般贈与
直系尊属(祖父母、父母など)以外からの贈与のことです。
兄弟間、夫婦間、友人などからの場合の贈与は、これに該当します。
(※直系尊属からの贈与でも、受贈者が18歳未満の場合は、一般贈与に該当します)
・特例贈与
祖父母や父母などの直系尊属から、その年の1月1日において18歳以上の者に対する贈与のことです。
それぞれの税率や控除額については、【ケース別計算例あり】贈与税の基本的な計算方法のセクションで解説します。
【注意】暦年課税には「生前贈与加算」というルールが定められている
生前贈与加算とは、相続が開始する前3年以内に、相続人に対して行われた贈与(生前贈与)は、相続財産に含めて相続税を計算するルールのことです。
これまでは、「3年以内」と期間が定められていましたが、2024年1月1日以降からは、この加算される期間が7年になります。
つまり、2024年1月1日以降に贈与する場合については、亡くなる前7年以内に行われた贈与が相続税の課税対象となります。(※)
これにより、暦年贈与による相続税対策の効果が以前よりも薄れることになります。
※加算の期間はいきなり延びるのではなく、段階的に延長されます。
例えば、2027年に相続が発生した場合の加算期間は約3年、2028年なら約4年となり、完全に7年間になるのは、2031年以降に発生した相続からです。
今すぐに7年分が加算されるわけではないので、過度に心配する必要はありません。
出典:「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」-国税庁
相続時精算課税

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上の子や孫に対して贈与をする際に選択できる制度のことです。
この制度の最大の特徴は、累計2,500万円までの贈与が非課税になる「特別控除」が設けられている点です。
この枠を超えるまでは、複数年にわたって何度でも利用できます。
さらに、2024年1月1日以降の贈与からは制度が改正され、この特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除もあわせて利用できるようになりました。
ただし、受贈された財産の累計が2,500万円以下でも年間110万円を超える場合は、贈与税の申告をしなくてはなりません。
また、一度この課税方式を選択した場合、二度と暦年課税に戻すことはできないため、選択する場合は注意が必要です。
「暦年課税」と「相続時精算課税」どちらを選ぶべき?

前述の通り、贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
しかし、実際に課税方式を選択する際に、どちらを選べばいいのか悩んでしまう方も多いはずです。
そこで、ここからはそれぞれを選ぶべき代表的なケースをご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、課税方式を決める際の参考にしてみてください。
暦年課税を選ぶべきケース
暦年課税が有効な選択肢となるのは、以下のようなケースです。
・孫や子の配偶者など「相続人以外」へ贈与する場合
亡くなる前の贈与を相続財産に加算する「生前贈与加算」の対象となるのは、原則として「相続または遺贈により財産を取得した人」です。
そのため、通常は相続人とならないお孫さんや、お子さんの配偶者への贈与であれば、亡くなる直前であっても加算の対象外となり、確実に相続財産を減らすことができます。
ただし、お孫さんが代襲相続によって相続人になる場合や、遺言によって財産を受け取る場合は、生前贈与加算の対象になることがあります。
・贈与者が若く、長期間にわたり贈与を続けられる場合
贈与者がまだ若く、今後10年、15年と長期にわたって贈与を続けられる見込みがある場合、亡くなる前の7年間の加算期間を考慮しても、それ以前の贈与分は確実に相続財産から切り離されます。
長く続けるほど、暦年課税による相続税の節税メリットは大きくなります。
・多くの人に少額ずつ、幅広く贈与したい場合
暦年課税の基礎控除110万円は、「贈与を受ける人」一人ひとりに対して適用されます。
例えば、お子さん2人とお孫さん3人の合計5人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間で合計550万円を非課税で次世代に移転できます。
相続時精算課税を選ぶべきケース
相続時精算課税が有効な選択肢となるのは、以下のようなケースです。
・7年以内の相続発生に備え、確実に非課税で贈与したい場合
ご高齢の方など、7年以内に相続が発生する可能性を考慮する場合、この制度は非常に有効です。
2024年から新設された年間110万円の基礎控除は、いつ贈与しても相続財産への加算対象にならないため、「安全」に毎年財産を移転できます。
・将来値上がりしそうな財産を贈与する場合
相続時精算課税を使って贈与した財産は、将来相続税を計算する際に「贈与した時点の時価」で評価されます。
例えば、将来有望な株式を評価額がまだ低い2,000万円の時点で贈与したとします。
その後、相続発生時にその株の価値が5,000万円に上がっていても、相続財産に加算されるのは贈与時の2,000万円のままです。
結果として、3,000万円の値上がり益分については、相続税の課税対象から外すことができます。
・一度に大きな金額を非課税で渡したい場合
お子さんが住宅を購入する際の資金援助など、まとまった資金を一度に渡したい場合に非常に有効です。
生涯の特別控除枠2,500万円とその年の基礎控除110万円を合わせれば、最大2,610万円を非課税で一度に贈与できます。
【ケース別計算例あり】贈与税の基本的な計算方法

贈与税は、選択した課税方式によって計算方法が大きく異なります。
ここからは、「暦年課税」と「相続時精算課税」、それぞれの基本の計算方法と、具体的なケースを用いた計算例をご紹介します。
暦年課税を選択した場合の計算方法
暦年課税の場合は、以下の計算方法で贈与税額を求めることが可能です。
| 贈与税額=(贈与額-基礎控除110万円)×税率-控除額 |
この計算式で使う税率や控除額は、「一般贈与」か「特例贈与」かによって異なります。
それぞれの税率と控除額については、以下の表をご参考ください。

出典:「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」-国税庁をもとに作成
これらの計算方法や税率、控除額をもとに実際に具体的な計算例を見てみましょう。
|
【計算例1】祖父(70歳)が孫(20歳)に600万円を贈与した場合(特例贈与) 1.基礎控除を差し引いた課税価格を計算する 2.上記表の税率と控除額を確認する 3.贈与税を計算する |
|
【計算例2】夫(68歳)が妻(65歳)に1,000万円を贈与した場合(一般贈与) 1.基礎控除を差し引いた課税価格を計算する 2.上記表の税率と控除額を確認する 3.贈与税を計算する |
これらの計算の流れを理解し、実際にご自身でも計算してみてくださいね。
相続時精算課税を選択した場合の計算方法
相続時精算課税の場合は、以下の計算方法で贈与税の税額を求めることが可能です。
| 贈与税額={(贈与額-基礎控除110万円)の累計額-特別控除2,500万円}×20% |
前述の通り、相続時精算課税では、財産の累計額が2,500万円までであれば、非課税で贈与できます。
しかし、超えた部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。
この計算方法を踏まえ、相続時精算課税の場合の計算例も見てみましょう。
|
【計算例】祖父(75歳)が孫(28歳)へ、相続時精算課税を利用して3年間にわたり贈与した場合 [1年目]300万円の贈与 2.特別控除の残額を計算する [2年目]100万円の贈与 2.特別控除の残額を計算する [3年目]3,000万円の贈与 2.課税価格を計算する 3.贈与税額を計算する |
今すぐ贈与税額がわかる!計算シミュレーター

贈与税の計算方法が理解できたら、次は実際に贈与税がいくらくらいかかるのかを調べてみましょう。
しかし、いざ自分で計算するのは少し大変ですよね。
そこで、贈与額などを入力するだけで、税額を自動で計算できるシミュレーターをご用意しました。
「暦年課税」と「相続時精算課税」のそれぞれに対応していますので、ぜひご活用ください。
【暦年課税対応】贈与税計算シミュレーター
暦年課税対応 贈与税かんたん計算
【計算シミュレーターの使い方】
1.「贈与された金額(円)」の欄に金額を入力する。
2.「計算する」をクリック(タップ)する。
3.「計算結果」が【特例贈与】【一般贈与】それぞれ表示される。
【相続時精算課税対応】贈与税計算シミュレーター
相続時精算課税対応 贈与税かんたん計算
【計算シミュレーターの使い方】
1.「今年贈与された金額(円)」に今年分の金額を入力する。
2.「これまでの累計贈与額(円)」に前年度までの贈与額を入力する。※今年分は含めない
3.「計算する」をクリック(タップ)する。
4.「今年の贈与税額」と「計算後の累計贈与額」がそれぞれ表示される。
|
【ご利用にあたっての注意点】 このシミュレーション結果は、入力された情報に基づく簡易的な概算値です。 個別の事情によっては税額が異なる場合があります。 正確な税額については、税務署または税理士などの専門家にご相談ください。 |
贈与税を賢く節税するには非課税制度の活用がおすすめ

基礎控除や特別控除とは別に、特定の目的の贈与には、まとまった金額が非課税となる強力な特例制度が用意されています。
これらを活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。
ここからは、暦年課税と併用できるほか、制度によっては相続時精算課税とも組み合わせられる、代表的な非課税制度について解説します。
住宅取得等資金の特例(2026年12月末まで)
マイホームの新築や購入、リフォームのために親や祖父母から資金を援助してもらう場合、最大1,000万円まで贈与税がかからなくなる制度です。
省エネ性能などが高い質の良い住宅なら1,000万円、一般的な住宅は500万円が非課税の上限となります。
ただし、この特例は自動で適用されるわけではなく、贈与税がゼロになる場合でも必ず税務署への申告が必要です。
また、年間の基礎控除110万円と併用することも可能で、その場合は最大1,110万円まで非課税で贈与できます。
特例を受けるための詳しい要件については、国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご参考ください。
教育資金の一括贈与の特例(2026年3月末まで)
30歳未満のお子さんやお孫さんの教育資金として、親や祖父母から最大1,500万円までを非課税で一括贈与できる制度です。
お金は専用の口座(教育資金口座)で管理し、実際に支払った授業料などの領収書と引き換えに引き出す仕組みになっています。
一番の注意点は、お子さんやお孫さんが30歳になった時に口座にお金が残っていると、その残額に贈与税が課税されてしまうことです。
本当に必要な金額を見極めて贈与しないと、かえって税金の負担が増える可能性もあるため、計画的な利用が求められます。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例(2026年3月末まで)
18歳から50歳未満のお子さんやお孫さんの結婚や子育てを応援するため、親や祖父母が最大1,000万円まで非課税で資金を贈与できる制度です。
出産や育児費用のほか、結婚費用(挙式や新居の家賃など)にも使えますが、結婚関連に使えるのは300万円までと上限が決められています。
この制度も教育資金の特例と同様に、50歳になった時点で使い残したお金には贈与税がかかってしまうため注意が必要です。
将来のライフプランをよく話し合い、必要な額だけを計画的に贈与することが、この制度を賢く使うコツです。
また、以下の記事ではここで挙げた非課税制度について、さらに詳しく解説しています。
こちらもぜひ参考にしてみてください。
【まとめ】贈与税対策の鍵は「制度の理解」と「シミュレーション」

この記事では、贈与税の基本的な仕組みから、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの制度の違い、そして具体的な計算シミュレーションまで詳しく解説しました。
さらに、基礎控除だけでなく、住宅取得や教育資金といった目的別の非課税制度をうまく活用することで、税金の負担を大きく軽減できることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
まずは記事内のシミュレーターを使って、ご自身のケースでは贈与税がいくらになるのか、目安を掴んでみてください。
贈与は、あなたと大切なご家族の将来に関わる重要な選択ですので、どの制度が最適か、今一度ご家族でよく話し合ってみましょう。
この記事が、あなたの想いを最善の形で実現するための助けとなれば幸いです。


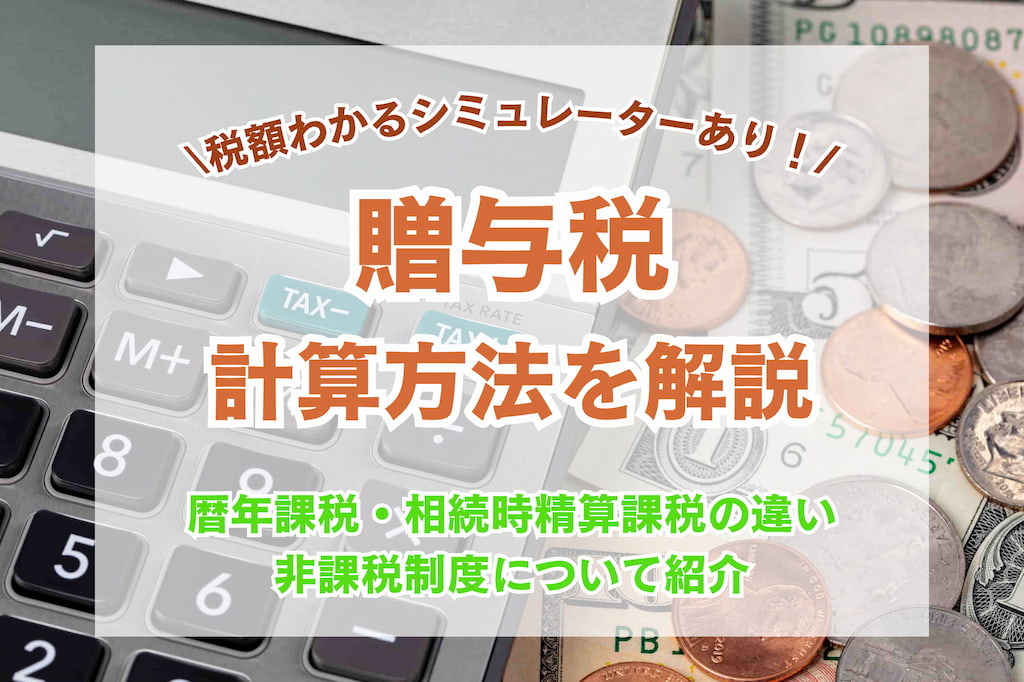















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら










