この記事の概要
|
「相場よりずっと安い土地を見つけた」「庭付きの理想的な中古住宅だけど、価格が驚くほど手頃だ」など、そんな魅力的な物件情報に心惹かれたとき、備考欄に小さく書かれた「市街化調整区域」という言葉に戸惑った経験はありませんか?
また、相続した空き家を改築しようとしたところ「市街調整区域では難しい」と言われた、土地を売りたいが「市街調整区域だから買い手がつかない」と断られたなど、何かと問題になることが多い、市街化調整区域。
今回は、市街化調整地域とは何か?家を建てることはできるのか?将来的に売却は可能か?メリット・デメリットについてもご紹介していきます。
この記事の目次
市街化調整区域とは?

簡単に説明すると
| 「都市開発を行わず、建物をむやみに建てないと定められた地域」 |
=田んぼや畑などの農地、森林などの土地がこれにあたります。
もし、どこにでも自由に家や工場を建てられるとしたら、どうなるでしょうか?
田んぼの真ん中にポツンと一軒家が建ったり、山の中に工場ができたりして、電気・水道・ガスなどの整備が追いつかなくなったり、自然環境が損なわれたりするかもしれません。
そうした無秩序な開発を防ぎ、計画的に街づくりを進めるために、「ここは街として発展させよう(市街化区域)」「ここは自然や農地として守ろう(市街化調整区域)」と分けているのです。
自身の土地が市街化調整区域かどうか調べるには

自身の土地が、市街化調整区域か調べるには一番手軽な方法として、市町村や区が提供しているwebサービスを利用することです。「〇〇(地域名) 市街化区域」など検索することで、自身の土地がどのような場所か知ることが出来ます。
調べてもわからなかった場合や土地のある地域がwebサービスを提供していない場合は、少々手間がかかるものの、市役所や区役所にある「都市計画課」に調べたい住所を伝える事で、知ることが出来ます。
また、その市街化調整区域の見直し時期が気になる場合も、教えてくれます。ただし、見直しが行われても市街化調整区域から外れるかはわからないため、注意が必要です。
市街化調整区域に家を建てることはできる?

市街地調整区域内にある土地に家を建てることはできるのでしょうか。
原則として自治体の許可なく建物の建築はできませんが、次のような例外もあります。
- 農家住宅や住宅兼用店舗など
- 市街化調整区域に指定される以前から本家がある
- 宅地利用が承認されている土地
- ディベロッパーが開発許可を取得した土地
農家住宅や住宅兼用店舗など
その地域で農業を営む人のための家(農家住宅)や、地域住民の生活に必要な最低限の店舗(住宅兼用店舗)、病院、学校などの公共施設などは、自治体の許可を得て建てられる場合があります。
| 林業・漁業・農業を行うのに必要な建物 そこで働く人の住居駅や公民館といった公共の施設など |
ただし、誰でも簡単に家を建てられるわけではなく、厳しい条件が定められています。
そのため、市街化調整区域の土地を購入して家を建てたいと考えている場合は、専門家や自治体に必ず確認することが非常に重要です。
市街化調整区域に指定される以前から本家がある
市街化調整区域に指定される前からその地域に住んでいる「本家」の子供や孫などが、結婚などを機に独立して新たな世帯を構える際に、本家が所有する土地の一部に住宅を建てることも可能です。
その際の要件は以下のようになります。
|
申請を行う際は、戸籍謄本や住民票、土地の登記簿謄本などを用いて、長年にわたる居住実態や親族関係を厳密に証明する必要があります。
また、これらの適用条件は自治体によって大きく異なるため、あくまで一般的な知識として捉えてください。
宅地利用が認められた土地
市街化調整区域でも宅地利用が認められた土地であれば家を建てることができます。
また、土地の用途を「宅地」に変更するための開発許可を取る必要もありません。
ただし、法を守った設計なのかなどを審査してもらうために、自治体の「建築確認申請」をクリアしなければなりません。
また、宅地利用が認められた土地だとしても、自由に家が建てられるわけではなく、都市計画法第34条に該当する以下の建物に限定されます。
- 住宅兼用店舗
- 分家住宅
- 既存住宅の建て替え
住宅兼用店舗、分家住宅に関しては上述した通りであり、既存住宅の建て替えは、基本的に同規模・同用途の建物なら建て替えることが可能です。
ディベロッパーが開発許可を取得した土地
不動産開発業者が既に開発許可を取得している分譲住宅地であれば、一般の個人でも家を建てることが可能です。
宅地としてライフラインなども整備され、後は家を建てて売るだけの状態になっており、見た目も市街化区域にある住宅地と変わらず利用できます。
建築の際は一定の要件もありますが、その範囲内であれば基本的には自由に家を建てることが可能です。
ただし、市街化調整区域内の分譲住宅地は非常に珍しく、早期に完売してしまう恐れもあります。
市街化調整区域は将来的に売却できる?

市街化調整区域の土地を購入したとしても、将来的に売却したいと思ったときに手放すことができるのか不安になる方もいるかと思います。
市街化調整区域は、市街化区域と比較して水道やガス、電気などのインフラが整備されていなかったり、住宅ローンが通りづらいなどのデメリットがあり、買い手に懸念されがちです。
こちらでは、「そもそも不動産会社は対応してくれるの?」「売れる可能性はあるの?」といった市街化調整区域の売却に伴い多くの方が抱える疑問についてご紹介していきます。
そもそも不動産会社は対応してくれるのか?
市街化調整区域の不動産売却において、重要なのが不動産会社選びです。すべての不動産会社が積極的に対応してくれるわけではありません。
都市計画法や建築基準法、農地法など、様々な法律や自治体の条例が複雑に絡み合うため、市街化調整区域の取引には高度な専門知識が求められます。
調査や手続きに手間がかかることや、売却の難易度が高いことから、取り扱いを敬遠したり、断ったりする不動産会社は少なくありません。
特に、都市部の物件を中心に扱う大手不動産会社は、対応に消極的な傾向が見られます。
一方で、以下のような不動産会社は、市街化調整区域の売却を積極的にサポートしてくれます。
市街化調整区域を専門・得意とする不動産会社
これらの会社は、専門知識と豊富な経験を持ち、複雑な法規制をクリアしながら売却を進めるノウハウを持っています。
中には、直接物件を買い取ってくれる専門の買取業者も存在します。
地域密着型の不動産会社
そのエリアの条例や開発許可の基準、地域の需要などを熟知しているため、的確なアドバイスと販売戦略を期待できます。
しかし、こういった不動産会社を自力で探すのは大変な作業ですよね。
株式会社じげんの運営する「イエイ」であれば、経験豊富な信頼のおける複数の不動産会社から一括査定を受けることができます。
不動産会社を探す際には、ぜひご活用ください。
売れる可能性はあるのか?
「売却は難しい」と言われる市街化調整区域ですが、物件の条件や売却する相手次第で、十分に売れる可能性はあります。
以下の条件に当てはまる物件は、買い手が見つかりやすく、比較的スムーズに売却できる可能性があるでしょう。
-
「既存宅地」である、または再建築が可能である
市街化調整区域に指定される前から宅地として利用されていた土地(既存宅地)や、一定の要件を満たして建物の再建築が認められている物件は、一般的な住宅を探している人にとって魅力的なため、売却しやすくなります。 -
開発許可を取得している(または取得見込みがある)
建物を建てるための開発許可が既に下りている、または取得の見込みが立っている土地は、利用価値が高く評価されます。 -
市街化区域に隣接している
水道・電気・ガスなどのインフラが整備されている可能性が高く、生活の利便性が良いため、需要が見込めます。 -
インフラが整備されている
土地の利用にあたって追加の工事費用が発生しにくいため、買い手がつきやすくなります。
また、通常の不動産市場での売却が難しい場合でも、以下のような相手に売却できる可能性があります。
-
隣地の所有者
自身の土地と一体化させることで、敷地の拡張や資産価値の向上につながるため、有力な買主候補となります。 -
地域の事業者
資材置き場や駐車場、農業用倉庫など、建物を建てる必要のない用途で土地を探している場合があります。 -
特定の目的を持つ個人や法人
古民家カフェやアトリエ、家庭菜園など、市街化調整区域の特性を活かした利用を考えている層もターゲットになります。
市街化調整区域の不動産売却は、確かに簡単ではありません。
しかし、物件のポテンシャルを正しく見極め、その価値を理解してくれる買主を見つけ出すことで納得のいく売却に繋げることができるでしょう。
市街化調整区域のメリット・デメリット

市街化調整区域にはどのようなメリット・デメリットがあるのか把握しておきたいですよね。
メリット・デメリットには以下のようなものがあります。
比較して何を重視するべきかを判断する材料に役立てましょう。
【メリット】
- 圧倒的な価格の安さ
- 税金の負担が軽い
- 静かで自然豊かな住環境
【デメリット】
- 建築・建て替え・増築が原則できない
- インフラが未整備の可能性が高い
- 資産価値が低く、将来売却が困難
- 住宅ローンの審査が非常に厳しい
- 生活の利便性が低い
- 自然災害のリスク
- 近隣コミュニティの問題
【メリット】圧倒的な価格の安さ
最大の魅力は、何と言っても価格です。
市街化区域の同様の土地と比較して、価格が7〜8割程度になります。
場合によっては半額近くになることも珍しくありません。
土地の購入費用の負担を大きく抑えられるため、その分建物にお金をまわしたり、より広い敷地を手に入れたりすることが可能になります。
【メリット】税金の負担が軽い
土地の公的な評価額が低く設定されているため、毎年課税される固定資産税も安くなる傾向があります。
さらに、市街化区域では通常課される「都市計画税」が、市街化調整区域では非課税となる自治体が多いことも長期的なメリットとなります。
【メリット】静かで自然豊かな住環境
開発が抑制されているため、将来的に近所に高層マンションや大規模な商業施設が建設される心配がほとんどありません。
これにより、騒音の少ない静かで落ち着いた暮らしが保証されます。
また、敷地面積が広く取れるケースが多いため、隣家との距離も保ちやすく、プライバシーを重視する方にとっては理想的な環境と言えるでしょう。
【デメリット】建築・建て替え・増築が原則できない
建築・建て替え・増築が原則できないことが最大かつ最も根本的なデメリットです。
家を新築することはもちろん、たとえ敷地内に古い家が建っていても、それを自由に建て替えたり、増築したりすることはできません。
すべての行為に自治体からの特別な許可が必要であり、その許可は保証されていません。
【デメリット】インフラが未整備の可能性が高い
市街化を抑制する区域であるため、公共下水道や都市ガス、場合によっては舗装された道路さえ整備されていないことがあります。
これらのインフラを利用するためには、自己負担で高額な引き込み工事を行わなければならないケースが多く、想定外の出費に繋がります。
【デメリット】資産価値が低く、将来売却が困難
購入時の価格が安いということは、裏を返せば資産価値が低いということです。
建築制限があるため、将来土地を売却しようとしても、買い手の対象が極端に限られます。
そのため、売却には時間がかかり、希望価格で売れる可能性は低く、地価の上昇もほとんど期待できません。
【デメリット】住宅ローンの審査が非常に厳しい
多くの金融機関、特にメガバンクやネット銀行は、市街化調整区域の物件への融資に非常に消極的です。
これは、担保価値が低く、万が一返済が滞った場合に債権回収が困難になるリスクを懸念するためです。
そのため、ローンを組む際は地元密着のJAや信用金庫など、そのエリアの特性を知っている金融機関がおすすめです。
【デメリット】生活の利便性が低い
区域の目的上、スーパーやコンビニ、学校、病院といった生活利便施設や、駅・バス停などの公共交通機関が乏しいことが一般的です。
日常生活において自動車が必須となる、いわゆる「車社会」を覚悟する必要があります。
【デメリット】自然災害のリスク
郊外の山林や田園地帯に位置することが多いため、場所によっては土砂災害や洪水といった自然災害のリスクが高い場合があります。
近年、法改正によりハザードマップで危険とされる区域での建築規制はさらに厳格化されています。
【デメリット】近隣コミュニティの問題
昔から住んでいる高齢者が多い、あるいは人口がまばらであるなど、新しく移り住んだ家族、特に子育て世帯が地域に溶け込みにくい、同世代の交流が少ないといった孤立感を感じる可能性があります。
市街化調整地域を購入する時の注意点

市街化調整区域を購入する際は、事前に以下の点を確認するように注意しましょう。
- 自治体の都市開発計画や規制について
- 土地の地目
- 線引き前の建物か、線引き後の建物か
- 区域指定
自治体の都市開発計画や規制について
都市の開発計画や条例や規制などは、自治体によって異なります。
そのため、購入前に確認しておくようにしましょう。
同じ市街化調整区域内でも、家を建てやすい土地とそうでない土地があり、増改築にも許可が必要で、売りたいと思っても売却するのが困難な場合があります。
購入後に長期にわたって快適な暮らしを送れるのか、リフォームや修繕工事はできるのかなど、将来的な視野を見据えて住みやすさやメンテナンスのしやすさを確かめておきましょう。
土地の地目
土地には地目があり、宅地・田・畑・山林・雑種地などに分類されます。購入を検討している土地がどの地目に該当するのか事前に確認しておきましょう。
市街化調整区域にある土地の場合でも、地目が宅地で、かつ指定前から継続して宅地として利用されているものであれば、建築許可を取得できる対象になる可能性があります。
しかし、農地を住宅として活用したい場合には、農地の利用目的を変更する「農地転用」を行わなければなりません。
これを行うにも都道府県知事の許可が必要になります。
市街化区域との違いは
| 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|
| 転用届を出すだけ | 転用許可申請表を出す必要がある |
です。
農地転用については、以下の記事でも取り扱っているので参考にしてください。

農地活用の可能性と気をつけておくべきポイント
線引き前の建物か、線引き後の建物か
市街化区域と市街化調整区域に指定された日のことを「線引き」といいます。
すでに建っている物件の購入を検討している場合には、線引き前の建物か、線引き後の建物かを確認するようにしましょう。
なぜなら、物件が建てられた時期によって、建築許可に対する要件が変わってくるからです。
建替えや増築の際には重要な部分になるため、必ず事前に確認を行う必要があります。
物件資料で分からない場合は、固定資産税課税台帳などを調べるようにしましょう。
区域指定
市街化調整区域内でも開発・建築が可能な区域に該当するケースもあります。
そのため、購入を検討している土地の区域指定を確認しましょう。
開発・建築が可能な土地であれば、利用度が高くなるので後に売却をする際にも有利になる可能性があります。
建築許可が取得できれば、都市計画事業や土地区画整理事業などの開発地域の場合も建物を建てることが可能です。
市街化調整地域を購入する流れと費用

実際に市街化調整区域の土地を購入する際の流れや費用はどのようなものになるのでしょうか。
こちらでは、その流れを4つのステップに分けて解説していくので、ぜひシュミレーションに役立ててください。
ステップ1:専門家への相談と事前調査
-
市区町村の担当窓口(都市計画課など)に相談する
検討中の土地の地図や資料を持参し、「この土地で自己用の住宅を建てることは可能か」「特別な条例指定区域(11号区域など)に該当するか」を直接確認しましょう。 -
市街化調整区域に詳しい不動産会社に依頼をする
一般的な不動産会社の担当者では、複雑な規制を理解していない可能性があります。市街化調整区域の取引経験が豊富な専門家は、地域の条例や特有の課題を熟知しており、致命的な見落としを防いでくれます。 -
行政書士に依頼をする
開発許可や建築許可の複雑な申請書類を作成し、行政との折衝を代行してくれます。
ステップ2:住宅ローンとインフラの整備
上述の通り、市街化調整区域の物件は担保価値が低いため、多くの金融機関が融資をためらいます。
時間と労力を無駄にしないためにも、融資の可能性が高い金融機関に的を絞って相談することが賢明です。
金融機関別に市街化調整区域への住宅ローン対応方針を表にまとめました。
| 金融機関 | 対応方針 |
|---|---|
| メガバンク・都市銀行 | 非常に消極的、原則融資は困難。担保価値評価が厳しく、リスクを避ける傾向が強い。 |
| ネット銀行 | ほぼ不可、審査受付もされないことが多い。低金利を売りにする分、審査は画一的で例外対応が苦手。 |
| 地方銀行・信用金庫 | 比較的柔軟、相談の価値あり。地域の事情に精通しており、担保評価も個別に判断する傾向。 |
| JAバンク(農協) | 最も積極的。農家住宅や分家住宅に慣れており、調整区域案件の融資実績が豊富。 |
また、インフラが未整備の場合は以下のような高額な追加費用が発生します。
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 浄化槽設置工事 | 80万円~150万円(5~10人槽) | 下水道がなければ必須。家族の人数に応じたサイズで変動。自治体の補助金も要確認。 |
| 上水道引込工事 | 30万円~50万円以上 | 前面道路の水道本管から敷地までの距離で変動(1mあたり約1.5万〜2万円)。 |
| ガス管引込工事 | 10万~15万円程度 | 都市ガスが利用可能な場合。なければプロパンガス契約となり、月々の料金は割高になる。 |
これらの費用を考慮すると、土地代が安いという価格的なメリットが大きく減少する可能性があります。
必ず事前に見積もりを取り、総額で判断することが重要です。
ステップ3:開発許可・建築許可の申請
開発許可・建築許可の申請は専門家と協力して進める必要があり、数ヶ月以上かかることも珍しくないため、家づくりのスケジュールに大きく影響します。
開発許可・建築許可の申請は以下の流れで行います。

ステップ4:「停止条件付契約」でリスクを回避する
全てのステップの中で、財産を守るために最も重要なのが「停止条件付契約」を結ぶことです。
これは、「万が一、予定していた開発許可や建築許可が下りなかった場合には、この売買契約は白紙撤回となり、支払った手付金は全額返還される」という特約を付けた契約です。
この特約がなければ、もし許可が下りなかった場合、「家を建てられない土地」だけを抱えてしまうことになります。
これは買主にとってのセーフティネットであり、経験豊富な不動産会社であれば、必ずこの契約形態を提案するはずです。
この条件を付けずに契約を急かすような業者には、絶対に注意してください。
市街化調整地域に適しているか見極めよう
ここまで、市街化調整区域がどのようなものなのかや、家を建てることはできるのか、売却はできるのか、メリット・デメリットや注意点などについてご紹介してきました。
市街化調整区域に家を建てるには、様々な条件があり、自治体に建築許可を取る必要があります。
自身の状況が当てはまっているのかしっかり確認し、将来的なことや経済面も見据えて計画を立てるようにしましょう。



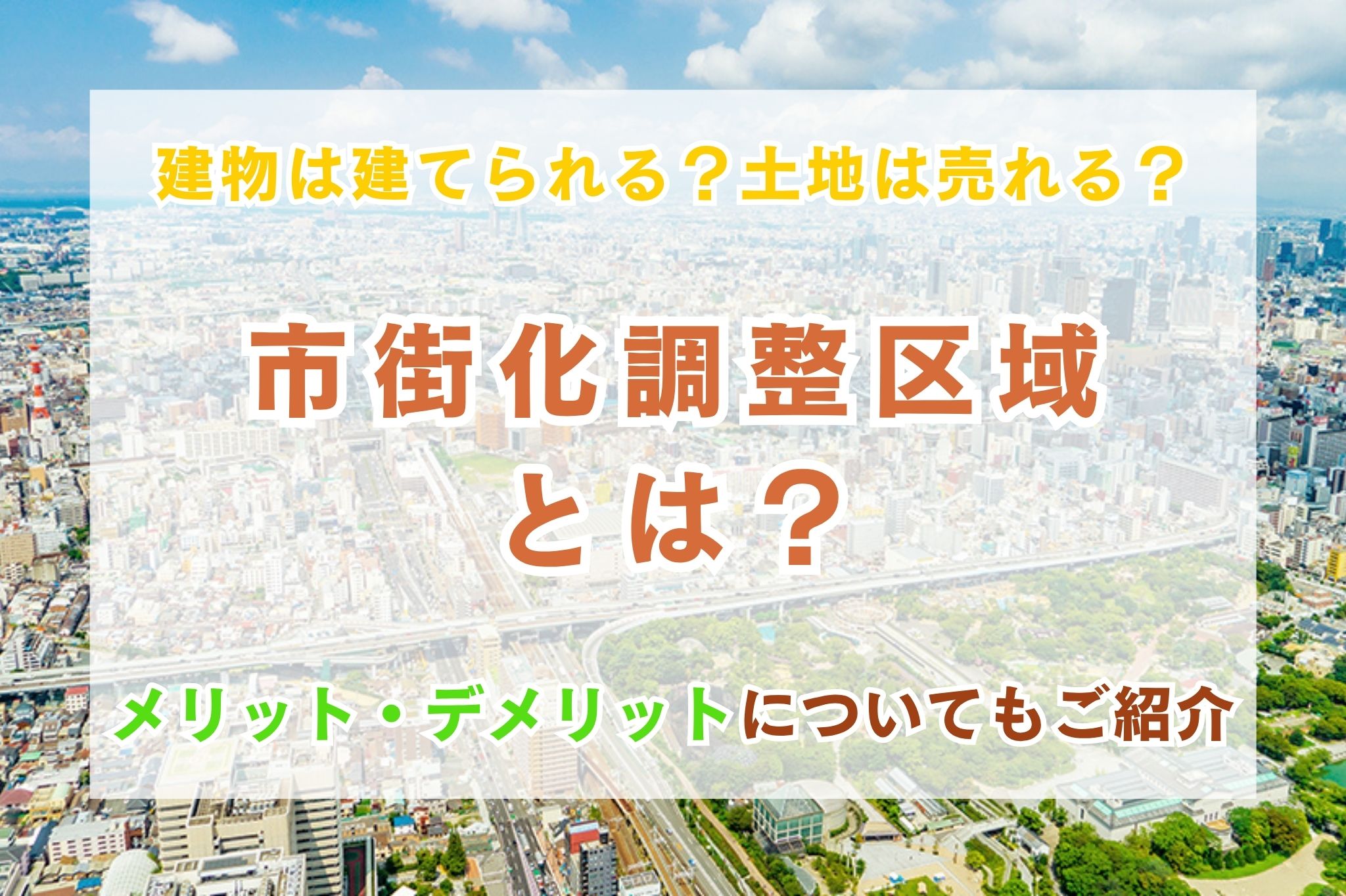














 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












