この記事の概要
|
土地の評価額がいくつもあって混乱していませんか?実は土地には「一物五価」と呼ばれる複数の評価方法があり、目的によって使い分ける必要があるのです。
こちらの記事では、公示価格から路線価、固定資産税評価額まで、土地評価額の種類と計算方法を徹底解説します。
さらに相続税対策など評価額を適正に下げる合法的な方法もご紹介します。
自分の土地の正確な価値を知り、売却や相続、税金対策に役立てるための実践的な知識を身につけましょう。
土地評価額の基本と種類

土地評価額について正しく理解することは、不動産所有者にとって大切なことです。
一つの土地に対し「一物五価」と呼ばれる5つの異なる評価額が存在します。
それぞれの評価額は、目的や算出方法が異なります。
公示価格、基準地価、相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格の違いや、それらが使われるシーンを知ることで、土地の真の価値を把握することができます。
評価額は土地の用途や立地条件によって変動し、税金負担にも直結する重要な要素です。
ここでは、土地評価額の基本と種類について詳しく解説していきます。
土地評価額とは?
土地評価額とは、土地の価値を公的に評価した数値のことです。
上述した「一物五価」という5つの評価額は、目的に応じて使い分けられています。
実勢価格・公示価格・路線価は、土地評価額の中でも特に重要です。
実勢価格は実際の市場取引で成立する価格のことで、売主と買主の需給バランスによって決まります。
公示価格は国が毎年発表する標準的な土地価格です。
公共事業や一般取引の基準となります。
路線価は国税庁が相続税計算のために設定する道路ごとの価格です。
各価格の主な特徴を以下の表にまとめました。
| 価格の種類 | 公表主体と更新頻度 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 実勢価格 | 市場(日々変動) | 不動産売買の参考 |
| 公示価格 | 国(年1回) | 土地活用計画の指標 |
| 路線価 | 国税庁(毎年7月) | 相続税・贈与税の計算 |
活用シーンとしては、不動産の売買では、実勢価格がもっとも優先されます。
土地活用の計画を立てる際には公示価格が信頼性の高い基準となります。
相続対策では路線価を基に税額を試算するのが一般的です。
相続税評価額と固定資産税評価額の違い
相続税評価額と固定資産税評価額は、同じ土地でも異なる価格が設定されることが一般的です。
これは、それぞれの評価額が異なる税金の計算に使用されるためです。
相続税評価額は公示価格の約80%を目安とし、路線価方式で算出されます。
一方、固定資産税評価額は公示価格の約70%程度とされています。
それぞれの使用目的は、相続税評価額が相続税や贈与税の計算に使われるのに対し、固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税の計算に用いられます。
更新頻度にも違いがあります。
相続税評価額は国税庁が毎年7月に更新されるのに対し、固定資産税評価額は市町村が3年ごとに見直しをします。
これらの違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 相続税評価額 | 固定資産税評価額 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 相続税・贈与税の計算 | 固定資産税・都市計画税の計算 |
| 算出方法 | 路線価方式や倍率方式 | 市町村による評価 |
| 更新頻度 | 毎年7月(国税庁) | 3年ごと(市町村) |
評価額が土地の用途や状況で変わる理由と影響
土地評価額は、土地の用途や状況によって大きく変動します。
たとえ同じ面積でも、立地条件や用途地域が異なると評価額は変わってきます。
これは土地の利用可能性や需要が直接反映されるためです。
例えば、商業地域では住宅地域より高い評価がつきやすい傾向にあります。
道路への接し方や形状も価格に影響します。
評価額の変動は税負担に直結します。
これは、固定資産税や相続税の算定基礎となるためです。
評価額が上昇すれば納税額も増加し、所有者の財務計画に大きな影響を与えます。
都市計画やインフラ整備といった周辺環境の変化も評価額を左右します。
新たな駅の開業や商業施設の進出は価値を押し上げる一方、騒音の増加など環境悪化は下落要因となり、資産価値に長期的な影響を及ぼします。
自分の土地の評価額を正確に調べる方法

自分の土地の評価額を正確に知ることは、相続税対策や資産管理において非常に重要です。
土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があります。
これらの評価方法は、土地の形状や立地条件によって計算方法が異なります。
角地や変形地などの特殊な形状の土地では、各種補正率が適用され評価額が調整されます。固定資産税評価額は市区町村の窓口で確認することができます。
公示価格や基準地価はオンラインシステムで簡単に調べることが可能です。
ここでは、土地の正確な評価額を自分で調べる具体的な方法と計算手順を詳しく解説します。
路線価方式の計算方法と実例
路線価方式では、土地の評価額を「路線価×奥行価格補正率×面積」で計算します。
路線価は国税庁ホームページの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
路線価は道路ごとに千円単位で設定されていて、例えば「200C」は1平方メートルあたり20万円を意味します。
奥行価格補正率は土地の奥行距離に応じて適用されます。
こちらは、国税庁の表で確認可能です。
「財産評価基本通達15((奥行価格補正))の定めによる奥行価格補正率等の適用について」(国税庁)
また、特殊な形状の土地には補正が加わります。
角地では、複数の道路に接していることから一般的な土地よりも価値が高いと判断されるため、側方路線の影響が加算されます。
反対に、間口が狭い土地は幅が狭いことで生じる利用価値の低下を反映させるために、間口狭小補正が適用されます。
不整形地でも同様に使いにくさを考慮して土地の評価額を減額する補正として、形状補正率が乗算され、評価額が調整される仕組みです。

【具体的な計算例】
路線価20万円、奥行補正率0.86、面積300平方メートルの場合:20万円 × 0.86 × 300 = 5,160万円となります。
計算時は借地権割合(路線価のアルファベット表記)や地区区分の確認が必須です。
借地権割合は、その土地に対する借主の権利を示しており、土地の値段の何割まで借地権に相当しているかを表しています。
以下の表にまとめたので参考にしてください。
| アルファベット表記 | 借地権割合 |
|---|---|
| A | 9割 |
| B | 8割 |
| C | 7割 |
| D | 6割 |
| E | 5割 |
| F | 4割 |
| G | 3割 |
そのため、対象地に「200C」と記載されている場合は、対象地の路線価は20万円で借地権割合は7割であるということが分かります。
地区区分は、路線価図に記載されている丸や六角形などの記号で判断することができ、以下のような区分に分けられています。
| 記号 | 区分 |
|---|---|
| 六角形 | ビル街地区 |
| 八角形 | 繁華街地区 |
| 楕円形 | 高度商業地区 |
| 丸 | 普通商業・併用住宅地区 |
| ひし形 | 中小工場地区 |
| 長方形 | 大工場地区 |
とくに地区区分をあらわす記号が入っていない場合は、普通住宅地区を指します。
借地権割合も地区区分も複雑な補正が絡むため、正確な評価には税理士などの専門家の助言をおすすめします。
倍率方式が適用される地域と計算手順
路線価が決められていないエリアは「倍率地域」といいます。
倍率地域の相続税評価額を算出する際に用いられる方式が「倍率方式」になります。
調べたいエリアが倍率地域に該当するかも国税庁の運用する「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で調べることができます。
倍率方式を用いて土地の評価額を求める際は「固定資産税評価額×評価倍率」で計算します。
評価倍率の調べ方は、国税庁ホームページの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」にて調べたいエリアの都道府県を選択し、「目次」にある「評価倍率表」で知ることができます。
【具体的な計算例】
対象の土地の固定資産税評価額が「6,000万円」で評価倍率が「1.1倍」という条件だった場合:6,000万円×1.1倍=6,600万円となります。
複数道路に面した角地・変形地の評価額算出法
角地や変形地など特殊な形状の土地については、その形状に応じた補正が評価額に適用されます。
角地の場合、「角地加算」として二方路線影響加算や側方路線影響加算が適用され、交差点の利便性を反映して評価額が上昇します。
変形地(不整形地)では、間口距離と実測面積から計算上の奥行距離を導き、「不整形地補正率」を適用します。
この補正率は、正方形や長方形からの形状のズレを数値化し、評価額を調整する役割を持ちます。
複数道路に面する土地の場合、路線価が最も高い道路が正面路線として扱われます。
他の道路については、影響加算率を乗算します。
これにより、接道状況による利便性の差を公平に評価できるのです。
主な評価ポイント
- 角地加算:交差点の利便性を数値化した補正
- 不整形地補正率:間口距離÷面積で算出した奥行距離をもとに適用
- 複数道路対応:最高路線価の道路を基準に他路線を加算
固定資産税評価額を市区町村で確認する手続き
固定資産税評価額を市区町村で確認するには、窓口で固定資産課税台帳の閲覧申請を行います。
申請時には本人確認書類が必要です。
代理人の場合は委任状も必要となります。
閲覧には300円の手数料がかかります。
また、1月1日時点の所有者には毎年5月頃に固定資産税納税通知書が送付され、同封の課税明細書に評価額が記載されています。
公示価格・基準地価をオンラインで調べる最新方法
公示価格と基準地価をオンラインで調べるには、国土交通省の「不動産情報ライブラリ」が便利です。
住所や地図から検索でき、最新の公示価格を無料で確認できます。
スマートフォンやPCからアクセス可能です。
具体的な土地の価格をピンポイントで調べられるのが特徴です。
基準地価も「不動産情報ライブラリ」で調べることが可能です。
住所入力時は「丁目」まで正確に入力すると、対象地をスムーズに特定できます。
林地を含む多様な用途の土地価格が公開されており、毎年9月下旬に更新されます。
主要なオンライン検索ツール
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」:公示価格の公式検索サイト
- 土地価格相場サイト:地図上で視覚的な価格比較が可能
これらのツールを活用すれば、役所に出向かずに自宅で最新の地価情報を入手できます。 特に土地取引や資産評価の事前調査時に役立ちます。
土地評価額を賢く下げる5つのコツ

土地評価額を下げることで、相続税や固定資産税の負担を軽減することができます。
こちらでは、小規模宅地等の特例による最大80%の評価減や、借地権設定、共有名義化といった合法的に評価額を下げる方法を紹介します。
さらに、土地の形状や接道状況を活かした評価減の申請方法や、間口狭小補正・奥行価格補正の効果的な活用術も解説します。
専門家の知識を借りながら、あなたの土地に最適な評価額の下げ方を見つけていきましょう。
1. 相続税評価額を合法的に下げる方法
相続税評価額を合法的に下げるには、主に以下の3つの方法があります。
- 小規模宅地等の特例
- 借地権設定
- 共有名義化
1.小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地について一定の条件を満たすことで評価額を最大80%減額できます。
具体的には相続開始時から遡って3年以上継続した居住や事業利用が要件となります。
特例を受けるためには、市区町村への申請書類提出が必要です。
2.借地権設定
土地所有者が第三者に貸すことで評価額を引き下げられます。
地代は適正な相場価格に設定し、契約期間は10年以上が効果的です。
定期借地権を活用する場合、更新条項の有無が評価に影響します。
3.共有名義化
親族間で持分割合を調整することで分割評価が適用され、相続税負担を分散できます。
遺産分割協議を円滑にするため、持分比率は法定相続分に沿った設定が推奨されています。
2. 小規模宅地等の特例で最大80%評価減の活用法
小規模宅地等の特例は、相続税の負担軽減に効果的な制度です。
適用条件は土地の用途ごとに異なります。
| 区分 | 具体的な例 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 居住用 | 自宅部分の土地 | 330㎡まで | 80% |
| 事業用 | 不動産貸付業以外の事業に供している土地 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付用 | 賃貸物件の土地 | 200㎡まで | 50% |
適用には、被相続人が生前に実際に居住や事業利用していた実績が必要です。
また、相続人が相続後も継続して利用することが要件です。
申請時は相続税申告書に加え、登記簿謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
3. 土地の形状・接道状況による評価減の申請方法
土地の形状や接道状況による評価減を申請するには、まず必要書類を準備します。
土地登記簿謄本、公図、実測図などが求められるため、税務署へ提出する必要があります。
特殊な土地形状では、以下のような条件で評価減が認められます。
- 間口狭小地:間口が狭い土地で、間口狭小補正率が適用されます。
- 奥行長大地:奥行が長い土地で、奥行長大補正率が適用されます。
- 不整形地:形状が不整形な土地で、補正率が適用されます。
- 無道路地:接道要件を満たさない土地で、評価減が可能です。

申請のタイミングは相続発生前後や確定申告期限です。
専門家である税理士に依頼するのが良いでしょう。
4. 間口狭小補正や奥行価格補正の効果的な適用術
「間口狭小補正」や「奥行価格補正」を効果的に適用するには、具体的な補正率の理解が不可欠です。
「間口狭小補正」は、間口が狭い土地に対して適用されるものです。
例として、普通住宅地区で間口4m未満の場合、補正率0.90で評価額が1割減額されます。
「奥行価格補正」は奥行距離が標準値と異なる土地に適用されます。
奥行き距離を間口距離で除した値が2以上の場合、補正率0.98などが用いられます。
補正率の具体例と注意点
両補正を併用すると最大40%程度の評価減が可能ですが、補正率は地区区分(普通住宅地区や商業地区)や土地の形状によって変動します。
特に角地や変形地では適用条件が厳格化されるため、地域ごとの路線価図で確認が必要です。
また、確実な適用には客観的資料の整備が効果的です。
土地測量図で正確な寸法を証明し、不動産鑑定士の意見書を添付すれば、税務署との交渉で補正の必要性を合理的に主張できます。
5. 税理士・不動産鑑定士の専門知識を最大限活用する方法
税理士と不動産鑑定士の専門知識を活用することで、土地評価額をより効果的に下げる方法を見出すことができます。
税理士には相続税や固定資産税の評価額を引き下げる戦略を相談しましょう。
小規模宅地等の特例適用や名義変更のアドバイスなどがもらえます。
不動産鑑定士には土地の形状や接道状況といった特殊性を活かした評価減の可能性を相談するのが有効です。
間口狭小補正や奥行価格補正の適用可否を客観的に判断してもらえます。
複数の専門家比較が重要
初回相談を無料で行う専門家も多いため、複数に相談して戦略を比較検討しましょう。
各専門家のアプローチの違いを理解することで、土地の特性に合った最適な方法を選択できます。
依頼時の準備必要書類
専門家への依頼時は以下の書類を事前に準備しておくとスムーズです。
- 登記簿謄本
- 公図
- 実測図
- 固定資産税評価証明書
専門知識を借りることで、個人では気づかない評価減のアドバイスを受けることができ、税負担軽減につなげられます。
土地評価額の知識を活かそう

土地評価額は不動産取引や相続において重要な指標です。
土地評価額には「一物五価」と呼ばれる5つの異なる評価額が存在し、公示価格や路線価、固定資産税評価額など各種評価方法の特徴と計算方法を解説しました。
また、土地評価額を下げることで相続税や固定資産税の負担軽減へと繋がります。
土地評価額を下げるには特例や控除制度を把握し、適切な評価方法の選択と税理士などの専門家への相談が大切です。
こちらの記事で身につけた土地評価額の知識を活かして、節税対策に役立てましょう。


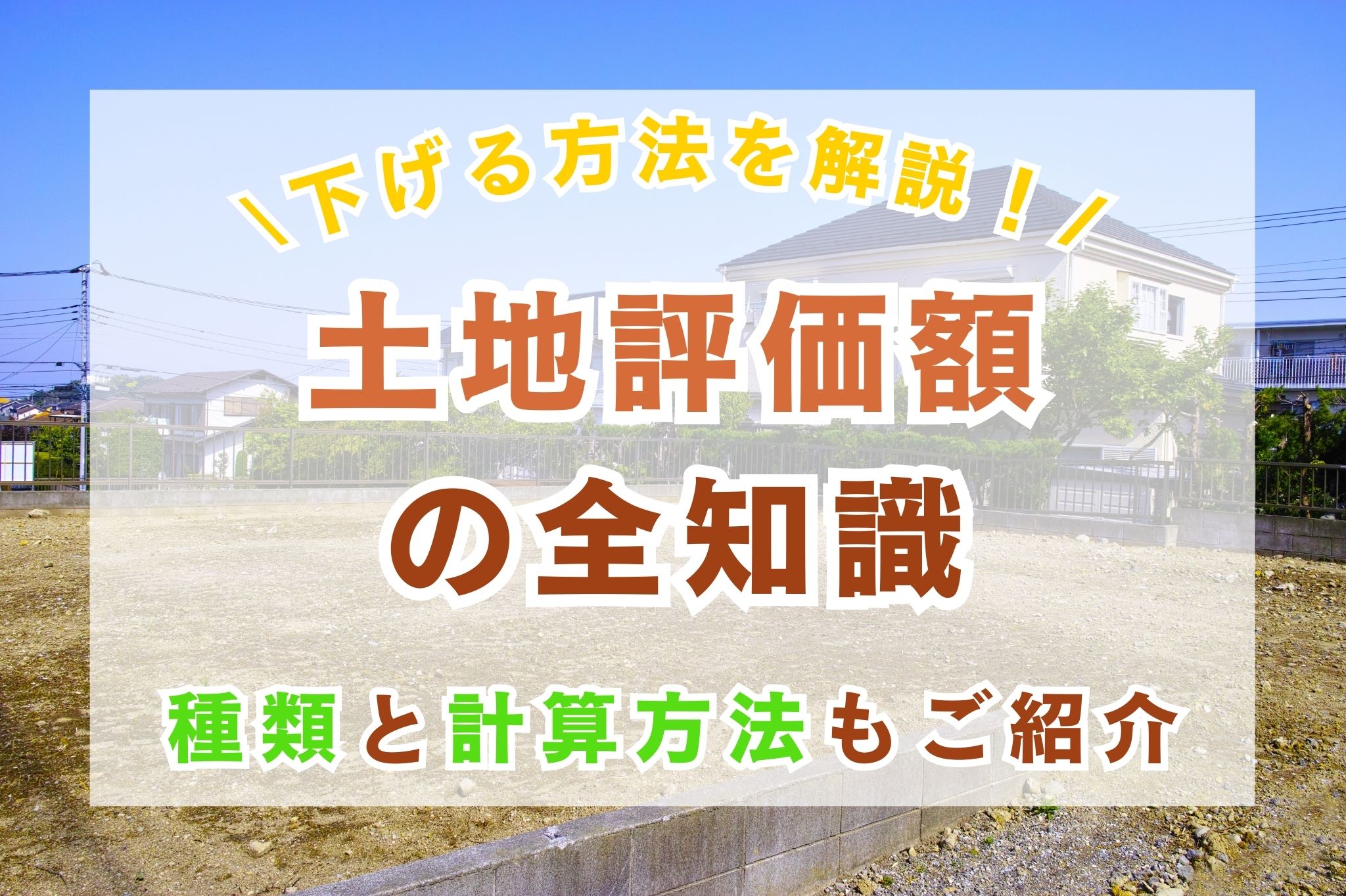














 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












