|
この記事でわかること ・土地にかかる相続税の目安と計算方法 |
「大切な土地を家族に引き継ぎたい。でも、相続税はいくらかかるの?」
そう考えたとき、きっと不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
「税金で土地を手放すことになったら…」「家族が困らずに相続するにはどうすればいいの?」といった悩みは尽きません。
ご安心ください。
この記事は、専門知識に自信がない方でも、あなたの土地にかかる相続税の目安から、税金を抑えるための具体的な方法、さらにはご家族間のトラブルを未然に防ぐヒントまで、すべてをわかりやすく解説します。
大切な土地と、なにより大切なご家族の将来を守るために、「知る」ことから始めてみませんか?
この記事を読み終える頃には、きっと漠然とした不安が、具体的な安心へと変わるはずです。
この記事の目次
そもそも相続税ってなに?基本を知ろう

大切なご家族が亡くなられたとき、その方が持っていた財産は、残されたご家族(相続人)が受け継ぐことになります。
このとき、受け継いだ財産にかかる税金が「相続税」です。
財産には、現金や預貯金、株式だけでなく、ご自宅の土地や建物といった不動産も含まれます。
そのため、土地を受け継ぐ場合も、原則として相続税がかかる可能性があるのです。
相続税に設けられている基礎控除とは
相続が発生したからといって、必ずしも全員が相続税を支払うわけではありません。
相続税には、ある一定の金額までは税金がかからない「基礎控除」という仕組みが設けられています。
この基礎控除とは、まさに「税金がかからない財産の合計額」のことです。
財産の合計額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、以下の簡単な式で計算できます。
|
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人※の人数) ※法定相続人とは、法律で定められた相続人のこと。 例えば、亡くなった方(被相続人)に配偶者と子供が2人いた場合、法定相続人は3人となる。 |
【計算例】
・亡くなった方に配偶者しかいない(法定相続人1人)場合
3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
この場合、3,600万円までの財産なら相続税はかからないということになります。
・もし、亡くなった方に配偶者と子供2人がいる(法定相続人3人)場合
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
この場合、4,800万円までの財産なら相続税はかからないということになります。
つまり、ご家族の人数によって、相続税がかからない金額も変わってくるということです。
ご自身の財産がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありませんので、まずはご家族の人数と財産の合計額をざっくりと把握してみることが大切です。
相続税の申告・納税の期限
相続税には、税務署への申告と、税金の納税に期限が設けられています。
これは、被相続人(亡くなられた方)が亡くなったことを知った日の翌日から、わずか10ヶ月以内と法律で定められているのです。
お葬式の手配や、その後のさまざまな手続きで慌ただしい日々を送る中で、この10ヶ月という期間は、思いのほかあっという間に過ぎ去ってしまうものです。
「もっと早く知っていれば…」と後悔しないためにも、万が一の事態に備えて、早めに動き出すことが非常に大切になります。
相続税の最重要ポイント「土地の相続税評価額」はどう決まる?

土地の相続税の計算をする際に大切なのが、あなたの土地の「相続税評価額」を出すことです。
「土地の値段なんて、時価ではないの?」と思われるかもしれません。
しかし、相続税を計算する上での土地の値段は、国が定めた特別な方法で評価されるのです。
この特別な評価額の出し方には、主に2つの方法があります。
路線価方式【都市部の土地の評価】
ご自宅の土地が都市部や住宅街にある場合、多くはこの「路線価(ろせんか)方式」で評価されます。
路線価とは、道路ごとに国が定めた、1平方メートルあたりの土地の評価額のことです。
たとえるなら、道路に「この道の脇の土地は1平方メートルあたり○○円ですよ」という値札が貼られているようなイメージです。
【路線価の調べ方と計算例】
路線価は、国税庁のウェブサイトで公開されている「路線価図」から調べられます。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。
|
1.国税庁のウェブサイト「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にアクセスする 2.該当の住所を選択する 3.路線価図で土地を探す 4.路線価を読み解く |
路線価がわかったら、あとは簡単です。
以下の計算式で土地の相続税評価額を求めます。
| 土地の相続税評価額=路線価(1平方メートルあたりの金額)×土地の面積(平方メートル) |
たとえば、路線価が1平方メートルあたり18万円で、あなたの土地の面積が200平方メートルだった場合は以下の通りです。
18万円×200平方メートル=3,600万円
この土地の相続税評価額は3,600万円となります。
倍率方式【路線価がない地域の土地の評価】
もしあなたの土地が、路線価が定められていない郊外や地方にある場合、「倍率方式」で評価されます。
この方法は、毎年役所から送られてくる「固定資産税評価額」という金額に、国が地域ごとに定めた「評価倍率」をかけることで求められます。
【倍率方式の計算式】
| 土地の相続税評価額=固定資産税評価額×倍率 |
倍率は、路線価と同じく国税庁ウェブサイトにある「評価倍率表」で確認できます。
また、固定資産税評価額の確認方法は、以下の記事で紹介しているのでこちらもご覧ください。
土地の形で評価額が変わる?評価額を下げる「補正率」とは
すべての土地がきれいな四角形とは限りません。
使い勝手の悪い土地は、その分だけ評価額が下がる仕組みがあります。
これを「画地調整(かくちちょうせい)」と言い、さまざまな「補正率」を用いて評価額を減額します。
代表的な補正には以下のようなものがあります。

・不整形地補正:三角形や旗竿地など、いびつな形の土地
・間口狭小補正:道路に接する幅(間口)が狭い土地
・奥行長大補正:間口に対して奥行きが長すぎる土地
・がけ地補正:土地の一部にがけがある場合
これらの補正を適用することで、相続税評価額がさらに下がる可能性があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
あなたの土地にかかる相続税をシミュレーションしてみよう!
いよいよ、あなたの土地にかかる相続税がいくらになるのか、一緒に計算してみましょう。
「計算は苦手…」と感じる方もご安心ください。
ここでは、専門的な知識がなくても、ご自身の状況に置き換えて理解できるよう、具体的な例を交えながら、一つひとつ丁寧に見ていきます。
相続税の計算は、大きく分けて4つのステップで進みます。

では、早速見ていきましょう。
ステップ1.相続遺産をすべて合計する
まず、故人(亡くなられた方)が残されたすべての財産を合計します。
これには、現金や預貯金、株式などの金融資産だけでなく、土地や建物などの不動産もすべて含みます。
この合計額から、もし故人に借金などのマイナスの財産があった場合、それらを差し引くことができます。
また、葬儀にかかった費用も差し引くことができます。
| プラスの財産 | マイナスの財産 | 差し引ける費用 |
|---|---|---|
| ・土地 ・建物 ・現金 ・預貯金 ・株式 ・車 など |
・借金 |
・葬式費用 (お通夜、お葬式の費用、火葬料、埋葬料など) |
【計算例】
|
前提条件 この場合の合計は… →これが、このケースでの「遺産総額」となります。 |
ステップ2.非課税枠(基礎控除)を差し引く
ステップ1で出した遺産総額から、前述した「基礎控除額」を差し引きます。
この残りの金額が、相続税の対象となる「課税遺産総額」です。
課税遺産総額は以下の計算式で求めることができます。
課税遺産総額=遺産総額-基礎控除額
【計算例】
|
先ほどの遺産総額8,800万円のケースで、相続人が「配偶者と子供2人」だったとします。(法定相続人が3人) 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円です。 この場合の課税遺産総額は… →この4,000万円が、相続税を計算する元となる金額です。 |
ステップ3.相続税の総額を出す
次に、ステップ2で出した課税遺産総額(この例では4,000万円)を、「もし法定相続分どおりに分けたとしたら」という仮定で、それぞれの相続人に割り振ります。
そして、その割り振られた金額ごとに税率をかけて、相続税の総額を計算します。
相続税の税率は、以下の表のように財産の金額に応じて変わります。
金額が高いほど税率も高くなります。
【相続税の速算表】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【計算例】
|
課税遺産総額4,000万円を、法定相続人(配偶者、子供A、子供Bの3人)で法定相続分どおりに分けると… ・配偶者(法定相続分1/2):4,000万円×1/2=2,000万円 次に、この金額を上記の速算表に当てはめて、それぞれの税額を仮計算します。 ・配偶者:2,000万円(3,000万円以下) ・子供A:1,000万円(1,000万円以下) ・子供B:1,000万円(1,000万円以下) これらを合計したものが、相続税の「総額」となります。 |
ステップ4.最終的な納税額を出す
最後のステップです。
ステップ3で計算した相続税の総額を、実際に受け継いだ財産の割合に応じて、それぞれの相続人に割り振ります。
遺言書があればその内容に従い、遺言書がなければ相続人全員で話し合った「遺産分割協議」の結果に従って計算します。
【計算例】
|
相続税総額が450万円のケースで、もし実際に次のように財産を分けたとします。 配偶者:全遺産8,800万円のうち、6,000万円(自宅の土地・建物と一部預貯金) この場合の、相続税総額450万円の割り振りは… ・配偶者:450万円×(6,000万円÷8,800万円)=約306.8万円 ただし、相続税には「配偶者の税額軽減」という非常に大きな控除があります。 最終的にこのケースで実際に支払う相続税は、子供Aが約71.6万円、子供Bが約71.6万円の合計約143.2万円ということになります。 |
土地の相続税を「グンと抑える」節税対策

ここまで、あなたの土地にかかる相続税の目安を一緒に計算してきました。
しかし、「やっぱり税金は少しでも安くしたい」と考えるのは当然のことです。
相続税には、税金の負担を大きく減らせる、国が定めた特別な制度がいくつかあります。
ここでは、特に知っておきたい「特例」や「控除」について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。
これらの制度を上手に活用すれば、相続税を大幅に抑え、大切な土地をご家族に無理なく引き継ぐことができます。
小規模宅地等の特例を活用する
ご自宅の土地に相続税がかかる可能性がある場合、まず第一に検討すべきなのが「小規模宅地等の特例」です。
この制度は、相続する方がその土地に引き続き住み続ける場合に、土地の評価額を最大80%も減額できるという、非常に強力なものです。
例えば、もし5,000万円と評価された土地でも、この特例を適用すれば評価額を1,000万円にまで圧縮できるため、相続税を大きく抑えたり、場合によってはゼロにしたりすることも可能になります。
これは、相続税の負担を軽減し、納税のために大切な自宅を手放す事態を避けるための重要な仕組みです。
【適用要件】
この特例の対象となる土地は、主に以下の4つの種類に分けられます。
それぞれの土地には、適用できる面積の上限や減額される割合、そして誰が相続するかの要件が以下のように定められています。
| 利用区分 | 概要 | 限度面積 | 減額割合 | 主な取得者の要件(例) |
|---|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 亡くなった方の自宅の敷地 | 330㎡ | 80% | ・配偶者 ・同居していた親族 ・一定の要件を満たす別居の親族(家なき子) |
| 特定事業用宅地等 | 亡くなった方の事業の敷地 | 400㎡ | 80% | ・事業を引き継ぎ、申告期限まで保有・継続する親族 |
| 貸付事業用宅地等 | 亡くなった方が営んでいた賃貸アパート等の敷地 | 200㎡ | 50% | ・貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで保有・継続する親族 |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 亡くなった方が経営していた同族会社の事業の敷地 | 400㎡ | 80% | ・その会社の事業を引き継ぎ、申告期限まで保有・継続する親族 |
特に、ご自宅の土地(特定居住用宅地等)の場合、「誰が土地を相続するか」によって適用されるための条件が異なります。
・配偶者が相続する場合:特別な条件なく適用されることがほとんどです。
・同居していた親族(子どもなど)が相続する場合:相続税の申告期限までその土地を所有し、引き続き自宅として住み続けることが条件です。
・同居していなかった親族が相続する場合:亡くなった方に配偶者や同居の相続人がいないこと、さらにその親族自身が過去3年以内に自分の持ち家に住んだことがないなど、非常に厳しい条件を満たす必要があります。(通称:家なき子特例)
この特例は、自動的に適用されるものではなく、相続税の申告書に「この特例を使います」という意思を記載して提出する必要があります。
また、原則として相続税の申告期限までに、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)が完了していることが適用されるための条件となります。
配偶者の税額軽減の適用を受ける
亡くなった方(被相続人)の配偶者が財産を相続する場合、「配偶者の税額軽減」という、手厚い控除が適用されます。
これは、残された配偶者の生活を守るために設けられた制度で、以下のどちらか「多い金額」までは、相続税がかかりません。
・1億6,000万円
・相続した財産のうち、配偶者の法定相続分に相当する金額
たとえば、遺産総額が3億円あっても、配偶者がその半分(1億5,000万円)を相続するなら、配偶者にかかる相続税はゼロになるということです。
これは、相続税における強力な節税策の一つと言えます。
その他の控除も活用する
上記で紹介した特例・控除以外にも、状況によっては相続税を安くできる控除があります。
・未成年者控除
相続人が18歳未満の未成年である場合、18歳になるまでの年数×10万円を相続税から差し引けます。
・障害者控除
相続人が特定の障害をお持ちの場合、85歳になるまでの年数に応じて、相続税から一定額を差し引けます。
・相次相続控除
短期間(10年以内)に立て続けに相続が発生した場合に、税負担が重くならないよう、以前の相続で納めた税金の一部を差し引ける制度です。
・贈与税額控除
亡くなる前の一定期間内に、故人から贈与を受けてすでに贈与税を払っていた場合、その贈与税額を相続税から差し引いて、二重に税金がかからないようにする制度です。
これらの控除は、ご自身の状況に合わせて活用できる可能性があります。
「うちの場合はどうだろう?」と思ったら、確認してみることをおすすめします。
生前贈与を検討する
相続税対策は、亡くなってから考えるだけでなく、ご存命のうちに準備を始めることが非常に大切です。
その代表的な方法が「生前贈与」です。
生前贈与とは、財産を生きているうちに、ご家族などに贈与することです。
通常、贈与には「贈与税」がかかりますが、年間110万円までなら贈与税はかかりません(暦年課税)。
もし将来、土地の価値が上がる前に贈与しておけば、贈与した時点での評価額で税金がかかるため、将来の相続税の負担を抑えられる可能性があります。
また、贈与税には、相続時精算課税制度という選択肢もあります。
これは、60歳以上の父母や祖父母から、成人しているお子さんやお孫さんへ財産を贈与する際に、最大2,500万円までなら贈与税をかけずに贈与できる制度です。
この制度を利用すると、相続が発生したときに、生前贈与した財産と相続財産を合算して相続税を計算することになります。
詳しくは、以下の記事で解説しているので、こちらもご覧ください。
「土地活用」で相続税評価額を下げる
土地を有効活用することで、相続税評価額を下げられる可能性もあります。
例えば、ご所有の土地にアパートやマンションを建てて人に貸す「土地活用」を始めることです。
アパートやマンションなどの賃貸物件が建っている土地は、「貸家建付地(かしやたてつけち)」とされ、通常の土地よりも評価額が低くなる傾向があります。
これは、土地を自由に売買したり利用したりする権利が、貸していることで制限されると見なされるためです。
また、貸家建付地であれば、前述の小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の対象となり、評価額を最大50%減額できる可能性もあります。
土地活用は、相続税対策だけでなく、安定した家賃収入を得られるというメリットもありますので、ご興味があれば不動産の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
土地活用の詳しい方法については、以下の記事でも紹介しているので、こちらもご参考にしてください。
土地の相続でありがちなトラブル例と回避策

相続は、ご家族の財産を受け継ぐ大切な機会です。
しかし、残念ながら、土地の相続がきっかけでご家族の間で思わぬトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
特に、土地は現金のように簡単に分けられないため、トラブルの火種になりやすい傾向があります。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、どのようなトラブルが起こりうるのか、そしてそれをどのように回避できるのかを知っておくことが大切です。
ここでは、土地の相続時によくあるトラブルの例とその回避策についてご紹介します。
ありがちなトラブル例
土地の相続では、以下のようなトラブルが起きやすい傾向にあります。
トラブル例1.遺産分割でご家族が揉めてしまう
土地は、現金のようにきっちり分けられないため、公平な分割が非常に難しい財産です。
誰がどの土地を相続するかで意見が分かれ、「私だけ損をしたくない」といった気持ちから、ご家族の仲が悪くなることがあります。
また、安易に土地を「共有名義」にすると、将来の売却や活用時に全員の同意が必要となり、さらに複雑なトラブルにつながりかねません。
トラブル例2.相続税が払えなくなる
「財産は土地しかないから大丈夫」と安心していると、思わぬ事態になることもあります。
相続税は原則現金で一括払いです。
しかし、相続財産のほとんどが土地などの不動産で、手元に現金が少ないと、納税資金が足りなくなる恐れがあります。
最悪の場合、大切な土地を税金を払うために手放さざるを得なくなることも珍しくありません。
トラブル例3.土地の「評価額」で意見が対立する
遺言書がない場合、ご家族で遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行います。
この際、相続税計算の基準となる土地の「評価額」をめぐって意見が対立することがあります。
同じ土地でも評価方法によって金額が異なり、「この土地はもっと価値がある」「いや、安い」といった主張が、ご家族間の不信感や争いにつながるケースも少なくありません。
トラブルを避けるための対策
上記のようなトラブルを避けるためには、ご自身がご存命のうちに、対策を考えておくことが最も重要です。
回避策1.「遺言書」で意思を明確にする
ご自身の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」引き継がせたいのかを遺言書で明確にしておくことが、トラブル回避の最も確実な方法です。
遺言書があれば、ご家族はあなたの意思に従ってスムーズに手続きを進めることができ、遺産分割での意見の食い違いを防げます。
回避策2.「家族会議」で事前に話し合いをする
ご家族と相続について話し合うのは難しいと感じるかもしれませんが、ご自身の口から「将来、この土地をどうしてほしいか」「税金で困らないように、こんなことを考えている」と話しておくことで、ご家族の理解を得られ、不要なトラブルを避けられます。
また、相続税の計算例や節税対策などを共有するのも良いでしょう。
回避策3.土地の「時価」を把握しておく
相続税評価額だけでなく、もし将来売却するならいくらになるのかという「時価」を把握しておくことも大切です。
時価を知ることで、遺産分割をより公平に進められ、納税資金が必要になった場合の売却計画も立てやすくなります。
時価は不動産会社に査定を依頼することで無料で知ることができます。
もし、どの不動産会社に相談すれば良いか迷われる場合は、当サイトが提供する不動産一括査定サービス「イエイ」をぜひご活用ください。
ご自宅にいながら、効率よく、無料で土地の正確な時価を知る良い機会となります。
相続対策の第一歩として、ぜひご検討ください。
回避策4.納税資金の準備も視野に入れる
土地以外の現金や預貯金が少ない場合は、相続税を支払うための資金をどうするか、事前に考えておくことが重要です。
生命保険を活用したり、あらかじめ土地の一部を売却しておくなどの選択肢もあります。
困ったときはプロへ|土地の相続税に関する相談先

ここまで、土地の相続税について、その計算方法から節税対策、そして起こりうるトラブルとその回避策まで、詳しく見てきました。
「なんとなく理解できたけれど、やっぱり自分だけでは不安だな…」「うちの場合はどうすれば一番良いんだろう?」そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。
相続は一生に一度あるかないかの出来事であり、土地の評価や税金の計算には専門的な知識が欠かせません。
そんなときは、一人で抱え込まず、プロの専門家に相談するのが最も確実で安心な方法です。
ここからは、土地の相続や、相続税に関する悩みがあった際に、有効な相談先についてご紹介します。
税理士
税理士は、相続税の計算、申告書の作成、そして何より相続税をできるだけ安くするための節税対策のプロです。
特に、土地の評価額を正しく算出し、最適な特例や控除を適用してもらうためには、相続税に詳しい税理士の力は不可欠です。
もし税務署への申告や納税に不安があるなら、まず税理士に相談することをおすすめします。
司法書士・弁護士
司法書士や弁護士は、遺産分割の話し合いがまとまらないときや、土地の名義変更(相続登記)の手続きを進めたいときに頼りになります。
また、万が一、ご家族間で相続トラブルが起きてしまった場合には、弁護士が法的な解決に向けてサポートしてくれます。
もし相続トラブルが起きてしまい、弁護士を探す必要が出てきた場合は、当サイトの提携サービスである「ベンナビ相続」のご活用がおすすめです。
あなたの状況に合った弁護士を見つける手助けとなるでしょう。
不動産会社
不動産会社は、土地の「時価」を知りたいときや、相続した土地を売却したり、有効活用したりしたいときの専門家です。
相続税の納税資金を土地の売却でまかないたい場合や、今の土地の価値を知りたい場合は、不動産会社に相談してみましょう。
不動産会社を探す際は、当サイト提供の不動産一括査定サービス「イエイ」もぜひご検討ください。
土地を相続するなら税金対策が不可欠!

土地の相続は、税金の問題やご家族間の調整など、複雑に感じるかもしれません。
しかし、この記事で「いくらかかるのか」「どうすれば税金負担を減らせるのか」「トラブルを避けるには」といった、あなたの疑問や不安が解消されたのではないでしょうか。
相続税には、税金がかからない「基礎控除」や、ご自宅の土地の評価額を大きく下げられる「小規模宅地等の特例」、そして配偶者への手厚い「配偶者の税額軽減」といった、強力な節税制度が存在します。
また、遺言書の作成や事前の家族会議が、ご家族間のトラブルを防ぐ大切な一歩になることもお伝えしました。
大切な土地とご家族の将来を守るためには、「知ること」そして「早めに準備すること」が何より重要です。
もし、さらに詳しい情報や相談が必要だと感じたら、一人で抱え込まず、プロの専門家を頼りましょう。
この記事が、あなたの相続に関する不安を和らげ、具体的な一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。


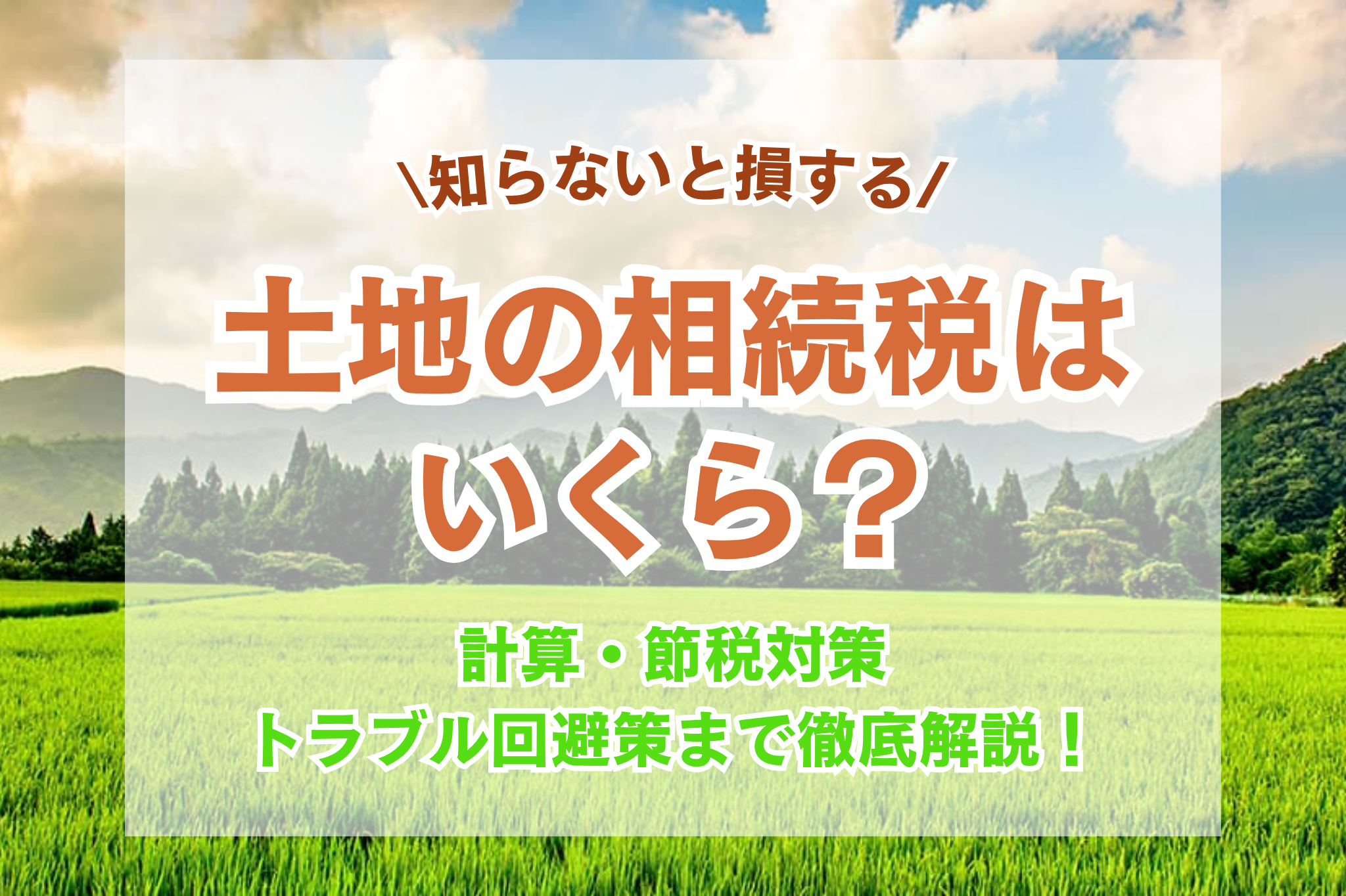


















 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら












