この記事の概要
|
病気や失業など、予期せぬ事情で生活が困窮してしまうことは、誰にでも起こり得ることです。
そのような時に、最後のセーフティーネットとなるのが「生活保護制度」ですが、「持ち家があると、利用できないのでは?」と不安になる方も多いかと思います。
大切な我が家を手放さなければならないという不安から、相談することさえためらっている方も少なくないかもしれません。
結論から言うと、持ち家に住み続けながら生活保護を受給することは、一定の条件を満たせば可能です。
この記事では、生活保護と持ち家の関係について、厚生労働省の公式な考え方に基づき徹底的に解説します。
一人で悩まず、正しい知識を身につけて、生活再建への第一歩を踏み出しましょう。
この記事の目次
そもそも生活保護制度とは?

まず、生活保護制度がどのようなものかを正しく理解することが重要です。
この制度は、日本国憲法第25条が保障する「生存権」によって、生活に経済的な負担を抱えているすべての国民に対し、国が対象者の困窮の度合いに合わせて相応な援助を行い、最低限度の生活を確保し、その後の自立を手助けすることを目的としています。
8種類の「扶助」
生活保護は、単にお金が支給されるだけの制度ではありません。
生活の様々な側面を支えるために、以下の8種類の「扶助(ふじょ)」に分かれています。それぞれの世帯の状況に応じて、必要な扶助が組み合わせて支給されます。
持ち家がある場合、家賃の支払いは発生しないため、原則として「住宅扶助」は支給の対象外となります。
しかし、それ以外の7つの扶助は、必要性が認められれば受給することが可能です。
| 扶助の種類 | 内容 | 持ち家所有者との関連 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 食費、被服費、光熱水費など、日常生活に必要な費用 | 支給対象。生活の根幹を支える基本的な扶助です |
| 住宅扶助 | アパートなどの家賃、地代など | 原則対象外。 持ち家のため家賃が発生しないためです |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費、給食費など | 子どもがいる場合、支給対象となります |
| 医療扶助 | 病気やケガの治療に必要な医療費(診察、薬、入院など) | 支給対象。 医療費の自己負担がなくなります |
| 介護扶助 | 介護保険のサービスを利用する際の費用 | 支給対象。 介護サービスの自己負担がなくなります |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 | 支給対象となります |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能の習得や、高校等への就学にかかる費用 | 支給対象となる場合があります |
| 葬祭扶助 | 葬儀を行うために必要な費用 | 支給対象となる場合があります |
なぜ「持ち家は売却必須」と誤解されるのか?
「持ち家があると生活保護は受けられない」という誤解が生まれる背景には、制度の「資産活用の原則」があります。
生活保護は、国民の税金によって支えられている制度です。
そのため、保護を受ける前に、まず自分の持っている資産や能力、あらゆるものを生活の維持のために活用することが求められます 。
具体的には、以下のようなものが「活用すべき資産」と見なされます 。
- 預貯金、現金
- 生命保険(貯蓄性の高いもの)
- 株式、有価証券
- 利用していない土地や家屋(空き家など)
- 自動車、バイク(一部例外あり)
- 貴金属、ブランド品などの高価な品物
このリストに「不動産(土地・建物)」が含まれているため、「持ち家=売却しなければならない資産」というイメージが定着してしまっています。
しかし、ここが重要なポイントです。
厚生労働省は、申請者が住んでいる家(居住用財産)については、一律に売却を求めるのではなく、その保有を認める場合があるとはっきりと示しています。
これは、住む家を失うことが、かえって生活の自立を妨げてしまう可能性があるためです。
つまり、居住用の持ち家の場合、「住み続けること」自体が資産の有効な「活用」であるみなされる場合があります。
この原則と例外のバランスを理解することが、持ち家と生活保護の問題を解く鍵となるのです。
持ち家に住み続けられる3つの公式条件

具体的にどのような条件を満たせば、持ち家に住み続けながら生活保護を受けられるのでしょうか。
そのためには、厚生労働省が示す方針に基づき、福祉事務所が判断する際の基準となる公式な条件を満たす必要があります。
大切なポイントは全部で3つありますので、こちらで一緒に確認していきましょう。
条件1:申請者本人または家族が「居住」していること
最も基本的な条件は、その家に申請者本人または生計を同一にする家族が実際に住んでいることです。
生活保護制度が持ち家の保有を例外的に認めるのは、あくまで「居住の安定」を確保するためです。
したがって、以下のような不動産は「居住用」とは見なされず、原則として売却して生活費に充てるよう指導されます。
- 現在住んでいない、別荘やセカンドハウス
- 親から相続したが、誰も住んでいない空き家
- 他人に貸して家賃収入を得ている投資用物件
これらの不動産は、生活の基盤ではなく、換金可能な「資産」と判断されるため、売却が前提となるのです。
条件2:住宅ローンが「完済済み」または「ごくわずか」であること
次に重要なのが、住宅ローンの状況です。
原則として、住宅ローンが完済していることが求められます。
その理由は、生活保護費の原資が税金であるためです。
もし住宅ローンの返済が残っている状態で生活保護費を受け取ると、税金で個人の資産(ローン完済後の家)形成を手助けすることになってしまうため、制度の趣旨に反すると考えられています。
ただし、これは絶対的なルールではありません。
一部の自治体では、ローンが完済していなくても、以下のような「ごくわずか」な状態であれば、例外的に保有が認められるケースがあります。
- ローン残債の目安: 300万円以下
- 完済までの期間の目安: おおむね5年以内
これらの数字はあくまで目安であり、法的な決まりではありません。
福祉事務所の担当者が、ローンの残額、今後の返済計画、そして転居した場合にかかる費用(敷金・礼金など)を総合的に比較検討し、「このまま住み続けてローンを完済した方が、社会全体のコストが低い」と判断した場合にのみ、認められる可能性があります。
もしローンが少しだけ残っている場合は、諦めずに福祉事務所に相談してみる価値はありますが、「完済済み」が最も確実な条件であることは覚えておきましょう。
条件3:家の資産価値が「著しく高すぎない」こと
最後の条件は、家の資産価値です。
厚生労働省は、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合は、売却等を指導する」としています。
簡単に言えば、「住むための価値」と比べて「売った時の値段(資産価値)」があまりにも高すぎる、いわゆる「豪邸」に住んでいる場合は、売却して、より一般的な住宅に移り住むことが求められるということです。
この「著しく大きい」の具体的な目安として、厚生労働省は約2,000万円という基準額を提示しています。
ただし、この2,000万円という金額は、絶対的な上限ではありません。
あくまで売却指導を検討する際の「きっかけ」となる目安です。
実際の判断は、以下の要素を総合的に考慮して、ケースバイケースで行われます。
- 地域の住宅事情: 都市部と地方では、同じ広さでも資産価値は大きく異なります。その地域の一般的な持ち家の水準と比較されます。
- 世帯の状況: 家族の人数や年齢、障害の有無なども考慮されます。例えば、一人暮らしなのに4LDKや5LDKといった広い家に住んでいる場合は、利用価値が低いと判断され、売却を指導される可能性が高まります。
- 特別な事情: 通院の利便性や、障害に対応するためのバリアフリー改修が施されているなど、その家に住み続けなければならない特別な理由があれば、資産価値が目安を超えていても保有が認められることがあります。
自分の家の価値が2,000万円を超えているからといって即座に諦めるのではなく、なぜその家に住み続ける必要があるのか(利用価値)を具体的に説明できるように準備しておくことが重要です。

持ち家の売却を指導される4つのケース

ここまでは持ち家を保有できる条件を見てきましたが、反対に、どのような場合に売却を指導されるのでしょうか。
以下の4つのケースに該当する場合は、原則として家の売却が求められます。
ケース1:住んでいない家や土地を所有している
前述したように、生活保護制度で保有が認められるのは、あくまで「居住用」の不動産に限られます。
親から相続した実家が空き家になっている、アパート経営をしている、将来のために土地を持っているといった場合は、それらをまず売却し、得た資金を生活費に充てることが求められます。
ケース2:家の資産価値が目安(約2,000万円)を大幅に超えている
資産価値の判断は総合的に行われますが、誰が見ても「豪華な家」と判断される場合は、売却指導の対象となります。
例えば、都心の一等地にある広い邸宅や、地域の水準からかけ離れた高級住宅などがこれに該当します。
社会通念上、税金で生活を支えながら過大な資産を保有し続けることは認められない、という考え方に基づいています。
ケース3:多額の住宅ローンが残っている
住宅ローンがまだ多額に残っている場合も、売却を指導されます。
生活保護費をローンの返済に充てることはできないため、返済を続けることが困難であれば、家を手放して生活を立て直すことが優先されるからです。
この場合、競売にかけられる前に金融機関と交渉して市場価格に近い価格で売却する「任意売却」という方法を検討するよう、福祉事務所から助言されることもあります。
ケース4:世帯人数に対して家が明らかに広すぎる
家の資産価値が2,000万円以下であっても、世帯の状況に見合わないほど広すぎる家は、売却指導の対象となる可能性があります。
典型的な例は、子どもが独立した後に高齢の親が一人で4LDKや5LDKの家に住んでいるケースです。
この場合、「利用価値が低い」と判断され、売却して得た資金で、より適切な規模の住居に移り、残りを生活費に充てるよう指導されることがあります。
持ち家で生活保護を受ける際のメリット・デメリット

持ち家を保有したまま生活保護を受けられることになった場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
現実を冷静に理解し、後悔のない選択に役立てましょう。
メリット:住み慣れた家で、精神的な安定を保ちながら生活再建を目指せる
最大のメリットは、何と言っても住み慣れた環境を変えずに済むことです。
家は単なる建物ではなく、家族との思い出が詰まった、心の拠り所でもあります。
経済的な苦境の中で、さらに住環境まで失うことは、精神的に大きな負担となります。
住み慣れた家で生活を続けられることは、精神的な安定を保ち、落ち着いて仕事を探したり、病気の治療に専念したりといった、生活再建に向けた前向きな活動の土台となるでしょう。
また、引っ越しの手間や費用、新しい地域での人間関係の再構築といったストレスからも解放されます。
デメリット1:家賃分にあたる「住宅扶助」は支給されない
最も重要なデメリットは金銭面です。
生活保護では、アパートなどに住む人には家賃相当額として「住宅扶助」が支給されます。
しかし、持ち家の場合は家賃が発生しないため、この住宅扶助は支給されません 。
つまり、賃貸住宅に住む受給者と比較して、毎月の支給総額がその分だけ少なくなるということです。
生活を切り詰める中でこの差は決して小さくありません。
デメリット2:固定資産税の支払い義務は残る(ただし減免制度あり)
持ち家を所有している限り、毎年固定資産税を納める義務があります。
生活保護費の中からこの税金を支払うのは大きな負担です。
しかし、これには救済策があります。
ほとんどの市区町村では、生活保護受給者を対象とした固定資産税の「減免(げんめん)制度」を設けています。
これは、申請をすれば固定資産税が全額免除または大幅に減額されるという制度です。
重要なのは、この減免は自動的に適用されるわけではなく、生活保護の決定が出た後に、自分で市区町村の税務課に申請する必要があるという点です。
福祉事務所とは別の窓口なので注意しましょう。
また、不動産が共有名義の場合、手続きが複雑になることがあるため、事前に確認が必要です。
生活保護の相談から受給開始までの流れ

それでは、実際に生活保護を申請しようと決めた場合は、どのような流れで進むのか知りたいですよね。
ここでは、相談から受給開始までの全手順を5つのステップに分けて解説します。
ステップ1:事前の準備と福祉事務所への「相談」
まず向かうのは、お住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口です。
最初の訪問は、いきなり「申請」ではなく、まずは「相談」から始めましょう。
「生活に困窮しており、持ち家があるのですが、生活保護の利用は可能でしょうか」という形で、自分の状況を正直に話すことが大切です。
相談に行く前に、以下の情報を整理しておくと、話がスムーズに進みます。
- 世帯全員の収入と支出の状況(給与明細、年金通知書、家計簿など)
- 預貯金の金額がわかるもの(通帳など)
- 生命保険の契約内容
- 持ち家の状況(住宅ローンが残っているか、固定資産税の金額など)
この相談の段階で、ケースワーカーから生活保護以外の制度(各種手当や貸付制度など)を提案されることもあります。
ステップ2:生活保護の「申請」
相談の結果、生活保護の要件を満たす可能性があると判断されれば、次に「申請」手続きに進みます。
福祉事務所の窓口で申請書を受け取り、必要事項を記入して提出します。
一般的に、申請時には以下の書類の提出を求められます。
- 生活保護申請書
- 収入申告書(給与明細の写しなど)
- 資産申告書(通帳の写しなど)
- 扶養義務者に関する書類
- その他、世帯の状況を説明する書類
ここで重要なのは、必要な書類がすべて揃っていなくても、申請書を提出する意思を示せば、申請は受理されるということです。
これは法律で定められた国民の権利です。
「書類が揃うまで申請させない」といった対応は違法ですので、覚えておきましょう。
ステップ3:ケースワーカーによる「調査」
申請が受理されると、受給の可否を判断するために、担当のケースワーカーによる調査が行われます。調査は主に以下の内容です。
- 家庭訪問: 実際の生活状況や住居の様子を確認するために、ケースワーカーが自宅を訪問します。
- 資産調査: 銀行や生命保険会社などに照会し、申告された以外の預貯金や保険がないかを確認します。
- 収入調査: 勤務先や年金事務所などに照会し、収入状況を確認します。
- 扶養照会: 親や子、兄弟姉妹といった扶養義務者(原則3親等以内)に対して、「援助が可能かどうか」を確認する手紙が送られます。ただし、DVや虐待の過去があるなど、連絡を取ってほしくない正当な理由がある場合は、事前に相談すればこの照会を止めることができます。
ステップ4:「決定」通知と保護費の支給開始
調査が完了すると、福祉事務所は生活保護の開始を「決定」するか、「却下」するかを判断します。
この決定は、原則として申請から14日以内に行われ書面で通知されます。
決定が下りると、定められた支給日から毎月、保護費が口座に振り込まれます。
ステップ5:受給開始後の生活(ケースワーカーとの関わり)
生活保護の受給が始まると、担当のケースワーカーとの関わりが続きます。
- 定期的な訪問: ケースワーカーが定期的に自宅を訪問し、生活状況に変化がないか、困っていることはないかなどを確認します。
- 収入の申告義務: アルバイトなどで収入を得た場合は、金額にかかわらず毎月すべて申告する義務があります。
- 就労指導: 働く能力があると判断された場合は、ハローワークに通うなど、就労に向けた指導や助言が行われます。
これらは監視ではなく、あなたの自立を支援するためのものです。
ケースワーカーと良好な関係を築き、正直に状況を報告することが、安定した生活を続ける上で大切です。
生活保護以外の選択肢は?

生活保護の条件や実情を知った上で、「自分には合わないのではないか」と感じる方もいるでしょう。
そのような場合は、生活保護以外にも持ち家を活用して生活資金を得る方法があります。
高齢者世帯向け:不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)
これは、主に低所得の高齢者世帯(原則65歳以上)を対象とした公的な融資制度です。
自宅の土地・建物を担保にして、お住まいの地域の社会福祉協議会から生活資金を月々借り入れます。
契約者が亡くなった際に、担保となっていた不動産を売却するなどして借入金を一括返済する仕組みで、「リバースモーゲージ」とも呼ばれます。
主な特徴としては、以下のようなものがあります。
- 自宅に住み続けながら、生活費を確保できる。
- 対象は主に一戸建てで、マンションは対象外となることが多い。
- 土地の評価額が一定以上(例:1,000万円〜1,500万円以上)必要。
- 生活保護の受給が必要となる世帯向けの「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」という制度もある。
生活保護と異なり「借金」ではありますが、行政の指導を受けずに自宅で生活を続けたい高齢者にとっては、有力な選択肢の一つです。
不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
住宅ローンが残っている方向け:任意売却とリースバック
住宅ローンが多額に残っており、生活保護の受給が難しい場合は、以下の方法も検討されます。
- 任意売却: ローンの返済が困難になった際に、金融機関の合意を得て、競売よりも有利な条件で自宅を売却する方法です。売却後も残ったローンは返済義務がありますが、生活を再スタートさせるための一つの手段です。
- リースバック: 自宅を不動産会社や投資家に売却し、その後、買主と賃貸契約を結んで、家賃を払いながら同じ家に住み続ける方法です 。まとまった売却資金を得られる一方、家賃が発生するため、安定した収入の見込みが必要です。売却代金でローンを完済し、手元にお金が残らなければ、生活保護(住宅扶助を含む)の対象となる可能性も出てきます。
利用できる制度や支援を理解し正しく活用しよう

この記事では、持ち家に住みながら生活保護を受給するための条件やメリット・デメリットについて詳しく解説してきました。
「居住している」「住宅ローンが完済済み(またはごくわずか)」「資産価値が著しく高すぎない(目安約2,000万円)」という3つの条件を満たせば、持ち家に住み続けながら受給できる可能性は十分にあります。
しかしその反面、家賃分の「住宅扶助」は支給されず、固定資産税(減免制度あり)などの負担もあります。
そのため、長期的な視点で本当に持ち家を維持し続けることが最善の選択か、冷静に考えることも大切です。
まずは、この記事で得た知識を元に、勇気を出してお住まいの地域の福祉事務所、または信頼できるNPOや専門家へ相談することから始めてください。
生活の困窮は、決して恥ずかしいことではありません。
利用できる制度や支援を正しく活用することが、あなたの生活を再建するための確かな第一歩となるはずです。


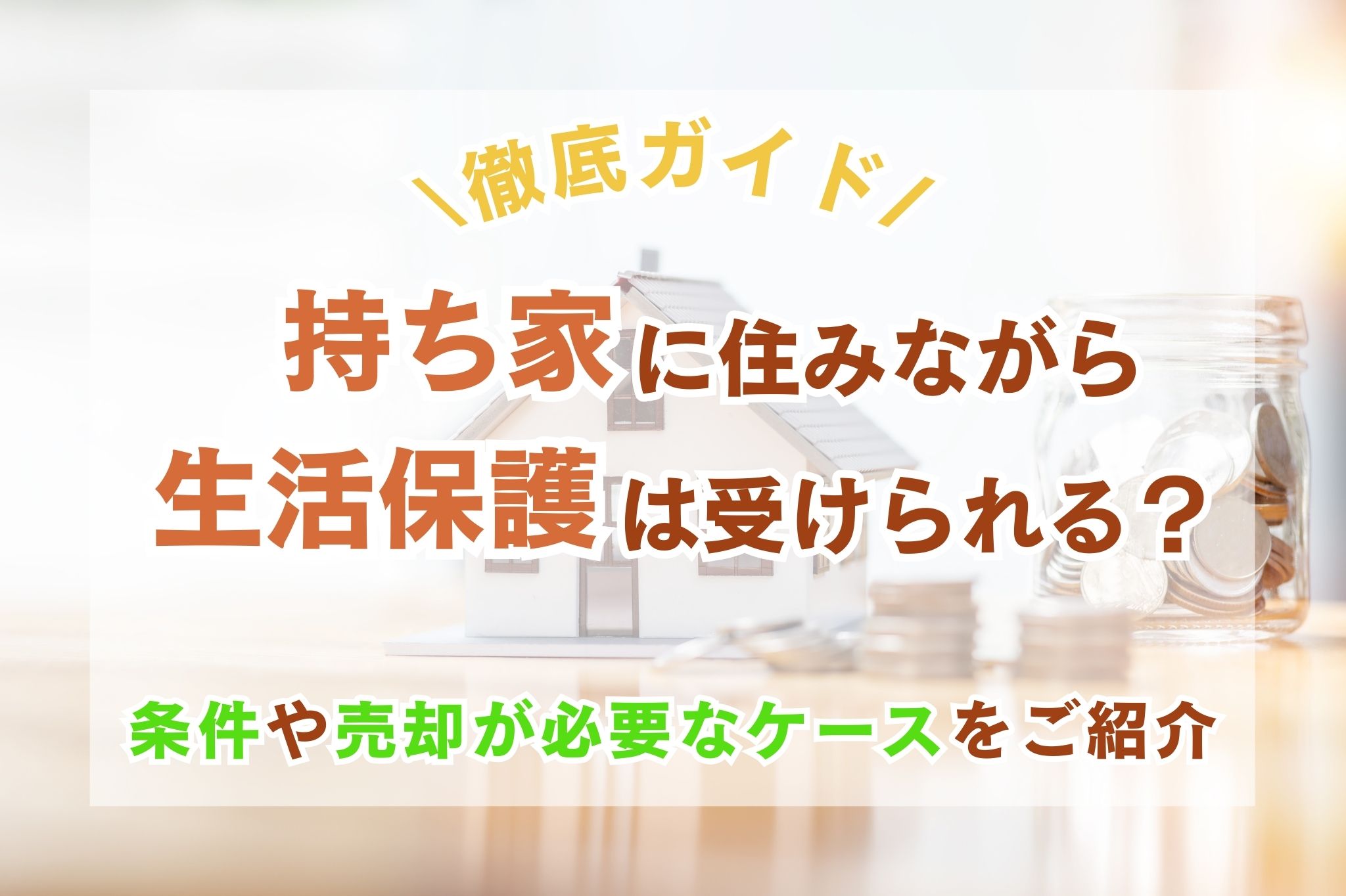














 無料一括査定はこちら
無料一括査定はこちら













